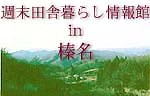|
| ▼ログハウスの作り方 |
|
面 作 成 ▼ |
構想が決まったら図面を作成します。私が相談にのりながら行えるため、ご安心下さい。 |
|
立 基 礎 ▼ |
建築位置を決めて、遣り方を行い、基礎の位置を出します。 この地の凍結深度がおよそ25cm程度あるため、それより深くおよそ40cm程度掘り下げて地固めを行います。地固めをした後に大き目の石および砕石を入れて、さらに地固めを行います。また、傾斜している場所や地盤が柔らかい粘土質のところの基礎は基礎面を大きくとって捨てコンを打つようにします。 次に、型枠(30cm四方)を遣り方に合わせて設置し、コンクリートを施工します。コンクリートは自分でこねてつくってもいいし、地元の石材屋さんがミキサー車で0.5立方メートルから搬送してくれます。コンクリートを流し込んだところで基礎金具をセットしておきます。コンクリートは4週間養生させてから型枠をはずします。 基礎レベル水位計を用いて基礎のレベルを計測して、丸太刻みの図面に現寸法を書き込み、丸太の長さを算出して、その長さを図面に書き写します。 |
|
太 刻 み ▼ |
丸太で軸組を造り、次に屋根を施工し、壁はケンタ材を張っていく方法です。丸太は地元の杉を使います。末口で18cm程度で長さ4mの丸太を使います。これを図面通りにカッティングします。丸太は事前に皮を剥いて3ケ月以上は乾燥させておく必要があります。クレーン車を必要とせずに組み上げるため、丸太重量を軽減させなければならないためです。乾燥させることにより、丸太の重量は半分以下になります。 |
|
上 げ ▼ |
 丸太を組み上げる場合には、まず柱を立ち上げ、支えとなるものを用いて固定します。 丸太を組み上げる場合には、まず柱を立ち上げ、支えとなるものを用いて固定します。具体的には、立ち上げる丸太の桁行方向と張間方向に木杭を打っておき、丸太柱とそれぞれの杭とを支えとする角材で打ち付けて固定します。 次には大引きにあたる丸太を柱間に刻んだ切り込みにはめ込みます。 この状態で丸太の柱はかなりしっかりとします。この大引きの上に仮の床をつくって、この床を足場にして屋根下になる棟木の丸太を組み込みます。大引きも棟木も立ち上げた柱より寸法をとって、その都度加工をします。丸太はそれぞれ太さも異なり、また曲がり具合も違うため、原寸合わせとします。これを順番に行っていくことにより、最後の棟上げを迎えることが出来ます。 屋根野地にはケンタ材を使います。ケンタ材の材厚が大きいため垂木には材厚が大きい角材を使用します。この上にコンパネを張り、防水シートを施工し、屋根は洋瓦を施工します。 |
|
▼ |
壁材にはケンタ材を用いて、これを外壁および内壁として張り合わせていくのですが、この間には鉄板(コイル)を入れて施工します。ケンタ材が乾燥収縮して隙間が開いてくるのですが、この鉄板で隙間を塞ぐ仕掛けとなっています。 また、隙間が気になるようであれば、コーキングを施工することとなりますが、私も自分の手づくりログハウスでの週末生活が4年になりますが、ほとんど気になりませんし、毎年冬にも来ていての体験から問題ないと思っています。 |
|
の 他 |
床はフローリングで、内装などは好みに応じて楽しみながら作ればいいと思います。 冬の暖房は薪ストーブが趣があってお洒落です。レンガ積みなどを取り入れる場合は、最初から計画した方が施工しやすいのですが、後付けもできます。私の場合はトイレは簡易水洗トイレを付けています。 |
週末田舎暮らし情報館へのお問い合わせはこちらまで・・
▼
〒370-0521 群馬県邑楽郡大泉町住吉13-6
電話・ファックス:0276-63-3468
久保田 伯一
Copyright (c) Syuumatsu-inakagurashi-jyohokan All Right Reserved