| ▼炭焼き窯 | ||
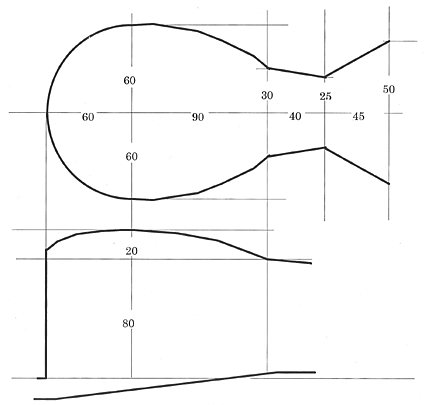
1. 窯の大きさを決める
型板を用いて、窯の位置ぎめを行う。窯の仕上がりの大きさよりも30cmほど広く、深さは30〜40cmに掘り下げる奥中央に排煙口を定める
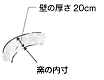

排水溝の工事として、中央に幅40cm深さ40cmの溝を掘る。
2つに割った竹の節を抜いて樋をつくり、溝に敷き詰める。
煙道の根元の部分を掘り下げ、短い竹筒を詰め、その竹筒の上部が窯底よりも3〜8cm下がるように施行する その後、その排水溝全体に握りこぶし大の石、砂利(レンガの破片)を敷き詰める
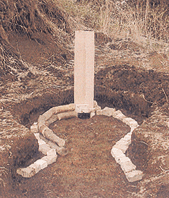
底にたまったガスが抜けやすいように、窯底は水平もしくは幾分奥下がりに仕上げる
5. 土を積み上げて窯壁を築く
窯壁づくりは、内側と外側に土留めをつくり、その中に粘土をいれて付き固めていく(順次、上に積み上げる)。
高さ80cm〜90cmになったら、土留めを取り払って窯壁の表面を削り、板や手ヘラなどで粘土の表面をしっかり打ち固めて仕上げる。
その後、その粘土層20cmの外側に約50cmの土壌層を設け、その外側を木の柵などで取り囲む。
6. 窯壁と平行して、排煙口をつくる
ベニヤ板で煙道の型をつくって、窯壁に埋め込み、周囲をレンガで固めていく。
排煙口の底部は窯底より3〜8cmほど掘り下げ、前方には緩やかな傾斜をつける。
排煙口の大きさは、高さ6〜7cm、奥行き30cmに、耐火レンガで作り込む。

窯口は小さいほどよく、幅60cm、高さ80cmくらいが目安。
窯口の両側に石を積み上げ、その隙間を粘土で塗り固めていく。
窯の顔となる部分であるため、特徴をだす。
8. 胴焼きをする
煙道が出来上がったら、窯を長持ちさせるために、排煙口の近くで焚き火をして、煙道全体をよく乾燥させるとともに、燃焼室内でも焚き火をして、窯壁や窯底を乾燥させる
9. 炭材を詰める
煙道、窯底を掃除し、煙道口に蓋をする。炭化室の窯底全体に、小枝・粗朶などを敷き並べる次に、窯壁の高さと同じサイズに切り揃えた太さ10cmほど(太ければ割る)の炭材を、窯の奥から太い方を上にして立てて、密に詰め込んでいく。窯口の近くは燃えて灰になり易いため、太い材や粗悪な材をおく。次に、天井をつくるために、型木や切り子をのせて、形を整えていく
10. 天井をつくる
天井の形に盛った切り子の上に、幾分湿ったゴザ、もしくは新聞紙やダンボールなどを敷き詰め、ガムテープで止めていく。その上に積み上げる粘土は、周囲が30cmで上にいくに従って薄くしていき、頂部が15cmとなるように積む 粘土をのせ終わっら、木槌などで打ち固め、表面が平らになったら、手へらで入念に仕上げる。根気よく叩き続けていくと、土の表面から水分がしみだしていき土の水分が抜ける
11. 天井を乾燥させる
天井に水分が残ったまま炭を焼くと、天井が割れてしまうため、そこで、煙の出口を塞ぎ、窯口で焚き火をして、天井を乾燥させる。乾燥が進むに従い、割れ目が出来てきたら、手へらでしっかり打ち固めておく


天井ができたら、雨から守るために小屋をかける
13. 木酢液採取装置の取り付け
14. 障壁・焚き口をつくり、火を入れる
焚き口の奥に耐火レンガなどを横に積み上げて障壁を築くことにより、焚き口の近くの炭材が灰になるのをある程度防ぐことができる。障壁は下の方に通風口を開けておく。焚き口と障壁の間の空間が燃焼室となる。障壁付近までぎっしり炭材を詰めたら、火入れのための焚き口をつくる。焚き口は石や耐火レンガを積み上げて、間に粘土を詰めて窯口を塞いでいく。下に高さ10cm幅20cmの通風口をつくる。上には高さ30cm幅30cmの燃料投入口を設けておく。窯口の上部に中の様子を覗くための小さな穴を開ける(普段は閉じておく)

1.火入れ
燃焼室に燃えやすい小枝などを入れておき、別の場所でおこした火を投入する中での燃焼が確認できたら、薪を次々と投入していく。この時点で、投入口を石、レンガなどで狭める。
2.炭化の始まり
窯の中が一定温度になれば、炭材が熱分解して炭化が始まる。煙突口から白い煙が勢いよく立ち昇る。
3.炭化の進行
窯内では、天井の方から窯底へと炭化が進行していく。炭化の速度は、煙突口(煙道口)の開口面積で調整する。最初はほとんど塞いでしまうが、炭化が進むにつれ徐々に開いていく。
4.煙突口と通風口の調整方法
口焚きを続けると、炭化が始まり煙突口から白い煙がもくもくと出る。この時に煙突口を狭める。さらに口焚きを続けると、炭化による熱分解が活発になり焦げ臭い煙(70〜75℃)が勢いよく立ち昇る。この時に薪の投入口を塞ぐ。次に、煙突口をしばらく開いていき、中の熱分解が安定して行われるのを待。煙突口を開けたら、この時に通風口を狭めていく。この辺から木酢液の採取を開始する。しばらくしてから、安定したかどうかの様子を見ながら、煙突口を徐々に狭めていく。炭化が進むに連れて、煙の温度が上昇して(90〜150℃)褐色を帯びてくる。木酢液の採取はこの辺で中止する。しだいに、木酢臭が強くなり、煙の量は少なくなっていくこの時期は、ゆっくり炭化させることが必要なので煙突口をさらに狭める。しばらくすると、タールの多い白い煙(200℃)になり、さらに青色(230〜300℃)に変わってくる。

煙が青色に変わり、温度が230〜300℃になったら、煙突口と通風口を再び開けて、精練(炭のガス分を抜く操作)に入り、青い煙がきれたところで窯止めする(煙突口および通風口を閉塞する)。精練により、皮の堅い良質の炭が焼きあがる。
6.冷却と炭出し
徐々に温度を下げていく(3日〜5日)ことが良質の炭をつくる条件。窯内の温度を100℃以下にまで下げる。煙突口を閉じたままで、窯口を少し開けてみる。この時に炭に火が入らない事を確認してから、外気を入れて窯内を冷却する。焼きたての炭は、外気にふれて、空気と水分を吸って安定するため、一晩かけて冷ます。万が一、火がまだ残っていると、空気に触れて燃え出すことがあるため、要注意