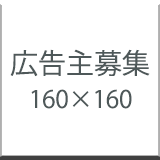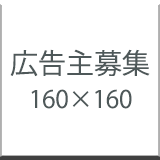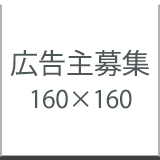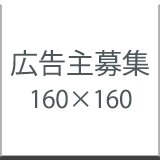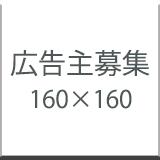ボランティア リンクサイト【助け合う心】
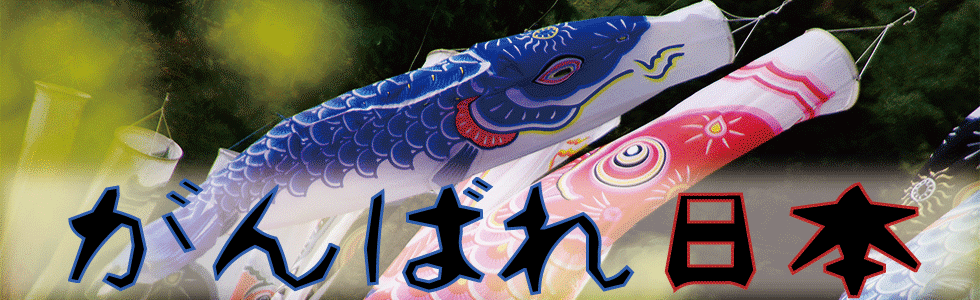
■ 災害時におけるボランティア支援マニュアル ■
ボランティアとは何か?
ボランティア活動はあくまでも自発的(自発性)な活動であり、義務でも強制でもありません。個人個人の自由な意志により、考え、発想し、行動するものです。ただ個人の意志により行動するといえども、自己の利益を目的とするものではなく、利他性が求められ、その活動や目的が社会に開かれたものである必要があります。さらに「無償性」「継続性」といった要件も求められます。1..ボランティアは自発的行為
「VOLUNTEER」という言葉は日本語では、“篤志家”や“志願兵”と訳されています。この言葉の語源は、ラテン語の「VOLO(ヴォロ)」であり、英語では「WILL」すなわち「自分で○○する」という意味です。ですから、ボランティア活動というのは、あくまでも自発的(自発性)な活動を示すものであり、義務でも誰かに強制されるものでもありません。
それにもかかわらず、従来は「VOLUNTEER」という言葉は「奉仕」と訳されることが多く、“滅私奉公”的なイメージでもって訳されたため、活動の範囲を制限されたり、自発的な行動に規制を加えたりすることもあり、特定の人だけが行う行動のようにも理解されてきました。
しかし近年、さまざな領域や分野でボランティアの活発な動きがはじまり、その意義は、社会的な課題解決の可能性を秘めた活動であることと理解されるようになってきました。このような理解が一般化する中で、改めて“ボランティア”という言葉が持つ本来の意味やその意義の理解が広まりつつあります。
2.ボランティアの多様性と先駆性
ボランティア活動は、あくまで、個人の自由な意志により、考え、発想し、行動するという自発的な行為、つまり“自発性”により支えられているものです。そして、自発的であるがために、個々の取り組みに違いがあり、そのため多様な活動ができ、既成概念に捕らわれずに、自由で先駆的な取り組みが展開できるのです。まさに“自発性(主体性)”こそがボランティア活動の最も大切な要件であるといっても過言ではありません。
もっとも、個人の意志により行動するといっても、自己の利益を目的とするものであってはなりません。常に“利他性”が求められ、その活動や目的が社会に開かれたものである必要があります。
したがって、ボランティア活動とは、「正しさ」や「公平さ」が求められる活動というよりも「多様性」と「先駆性」が求められる活動であると理解する必要があります。
3.ボランティアの無償性と継続性
次に、二次的な要件として「無償性」「継続性」もあげられます。個人がボランティア活動を展開する場合、あくまで無償が基本です。もっとも最近は、活動にかかる交通費の補助やお弁当程度の食事代を支給するケースもありますが、これはあくまでも、ボランティアを“受ける側”や活動を主催する側の“気持ち”的なもので、ボランティア自身が求めるものでは決してありません。
また、日常的な活動の場面において継続的な活動が必要とされている場合や、継続することが何らかの効果につながることが期待できる場合には“継続性”が求められます。しかし、イベント的な活動や突発的な災害救援など、一時的な活動で重要なものもあり、継続することが重要であるとは一概にいえない場合もあります。したがって活動の内容や効果などを、ボランティア活動を“する側”とそれを“受ける側”とが、常に点検し、碓認しながら進めていくことが大切です。
■ 災害時におけるボランティア支援マニュアル ■
ボランティア活動の目的とその意義(意味)
ボランティア活動は、個人個人の自発的な行為であるために、その目的も多様であり、単なる“労力”提供でもなければ滅私奉公でもありません。ボランティア活動とは、「何らかの助けを求める人に手をさしのべないではいられない」という共感と、受け手側の受容による「協働の企て」として行われるものです。1.機動性と活動内容の多様性
ボランティア活動を始めるきっかけは、一人一人違います。しかし、多くの場合“何かの救いを求める人に、何かできることがないか”という、“受ける側”の悲しみや怒り等の思いに共感し、行動することが多いのです。たとえば、阪神・淡路大震災や重油流出災害の時も、報道で現地の状況が伝えられることにより、現地で生活する人々に共感し、何万人、何十万人ものボランティアが駆けつけ、さまざまな活動を展開したのです。
ボランティア活動の目的は、個々の活動の内容によって異なりますが、広義の意味においては、自分自身の生活する社会において起こる社会問題や課題の解決に対して、単に行政や他者に求めるだけではなく、自分自身が自発的・主体的にその問題を解決していこうというものです。
したがって、ボランティア活動は政府や自治体がプログラムした活動だけを行うのではなく、自発的な活動であるがため、その範囲、方法、手段、規模等すべてが多様です。
この多様さこそが、従来にない新たな活動を展開する“先駆性”を生み出し、“受ける側”の個々の二一ズに対応できる“個別性”を実現するのです。そして、緊急時等に俊敏に対応できる“機動性”も得られるのです。公平さを求められるがため、多様性に対応できない行政とは違った活動を展開することが可能なのです。全体を把握した上での公平原理による行政の思考とは、まったく逆の思考によって進んでいると言っていいでしょう。
2.コミュニケーションが共感を生む
ボランティアを単なる“労力”として捉えることは、多様性のある社会形成に支障をきたすことになりかねません。個々の意志にもとづいて展開するボランティア活動こそが、援肋を必要とする人にとっては欠かせない重要な要素になるのです。とはいえ、ボランティアが完璧なものであるとはいえません。なぜなら、多様性を重んじるがゆえに、個と個の対立が少なからず起こり、トラブルも発生しやすくなるのです、個々の自発的な考えを尊重するがゆえに合議制をとることも多く、必ずしも効率的でないこともありますし、数々の課題や問題が発生しやすくもなってきます。そこに適切なコミュニケーションの必要性があります。ボランティアを“する側”と“受ける側”のコミュニケーションを大切にすることが新たな展開へのヒントになったり、双方の理解につながり、共感を生み、本当に必要な活動の姿を見出すことができるようになるのです。
■ 災害時におけるボランティア支援マニュアル ■
災害時のボランティアの心構え
1 自分自身の自立
被災地ではボランティア自身の飲料水や食品等の調達や、宿泊場所の確保が困難であることが想定されます。事前に現地の状況把握をした上で、必需品を確認・調達し、一般的に、水、飲料水、宿泊用テントや寝袋、活動に必要な機材(懐中電灯、ラジオ、携帯電話等)は自分で確保し、自活できるように準備していくことが大切です。
2 状況を知る
活動を始めるにあたっては、現地の活動団体等に参加し、オリエンテーションを受けることが大切です。そのことが、詳しい現地の状況を知ることにも、自分の活動内容や役割を確認することにもなります。
3 意思の疎通
被災地では、被害を受けた人が「被災者」という名のもとに、一括されることに抵抗を感じる人もいます。どんな状況であれ、相手の気持ちを大切にし、尊重する気持ちをもって意思の疎通を図るように心がけましょう。
4 意思の尊重
災害時のボランティアは、被災者の生活を支援することを目的に活動します。活動は、「~してあげる」といった押しつけがましいものでなく、被災者の意思を尊重し活動することが大切です。
5 考えた行動
ボランティアとしてできること、できないこと、してはいけないことを考えて無理のない活動をすることが必要です。活動自体が被災者の自立を阻害したり、自らが危険に陥ったりしないよう心がけることが大切です。
6 健康管理
ケガや病気、事故に充分注意し、また、過労や睡眠不足にならないように健康管理に注意することが大切です。(二次災害が起こらないようにするのもボランティアの努めです。)
7 保険の加入
事故に備えてボランティア活動保険に加入しておきましょう。
【ボランティア(英 volunteer)とは、ボランティア活動に携わる人のことである。ボランティア活動は、古典的な定義では自発(自主)性、無償(無給)性、利他(社会、公共、公益)性に基づく活動とされるが、今日ではこれらに 先駆(先見、創造、開拓)性を加えた4つをボランティア活動の柱とする場合が一般的となっている。】
Wikipediaはこちら→
ページTOPに戻る
ホーム
スポンサード リンク