ここで,もう一度方法論的な話に戻して,アメリカの精神医学者,ハリー・スタック・サリヴァン(1892〜1949)のパーソナリティ理論を紹
介しましょう。
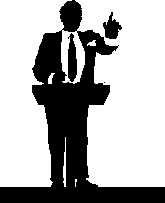 サリヴァンは次のように言っています。「<自己(self)>とは,われわれが<私(I)>ということばを発する時,このことばに
サリヴァンは次のように言っています。「<自己(self)>とは,われわれが<私(I)>ということばを発する時,このことばに
よって指すところのものである」が,パーソナリティはその<自己>だけから成るものではなく,抑制・抑圧・解離という<自己>の機能に
よって意識の枠外に追いやられた諸体験,すなわち<非自己>も<自己>とともにパーソナリティを構成する一部分なのである。「ここ
でいう<自己>とは一個の固定的実体ではなく,対人的過程が集合してつくる一つの図形(かたち)である。」 サリヴァンは,<自己>
の力動的な局面を強調しようとするとき,その<自己>を<自己態勢(self dynamism)>と呼びます。また,<自己>の統合化されて
いる局面を強調しようとするとき,その<自己>を<自己組織(self system)>と呼びます。 「重要人物からの承認は非常に価値の高
いものであり,逆に,不承認は満足を奪い不安を誘発する。<自己>がきわめて重要となってくるのはここである。子どもの<自己>は
,承認不承認の原因となる言動に対して非常に鋭く焦点を絞る。」この焦点を絞るという「特性は,不安と強く結びついて,それ以後,生
涯にわたって持続する。」 つまり,重要人物による承認不承認に関係する体験だけが<自己>の中に組み込まれ,それ以外の人格部
分にあたる衝動・欲望・欲求は<自己>との結合を絶たれ,意識の枠外に解離される(to be dissociated)のです。
「<自己>とは,いわば,自己維持系的なものであって幼小児期に与えられた方向づけと特性を忠実に守ってゆこうとする傾向が強い
。」 そのような方向安定作用が何によるものであるかといえば,それは,「過去の体験が<自己>の構造すなわち<自己態勢(self
dynamism)>の構造の中に一旦組み込まれたならば,きわめて異質な体験,すなわち過去の体験を修正する力を持つ新奇な体験を閉
め出して,<自己>の中にはいって来ないようにするからである。<自己>が成長の方向を一定に保つのは,当人の意識の幅に対する
<自己>の規制力もさることながら,自分が主にとっている構えとは全く異質なものが意識にのぼりそうになると不安がたちまち起こる
ために,体験に限界線が引かれるためでもある。」 <自己態勢>の中に「構造的に組み込まれ得なかった体験は,最後には,まさに
構造的に組み込まれ得なかったがために,複数の領域にわたる<解離>状態に置かれる。すなわち,その当人の社会的環境をも含め
て外的現実との関係という領域だけでなく,その人の個人的現実という領域においても<解離>される。」
「自らの体験によってか,あるいは発達途上の諸段階における重要人物からの影響によってか,いずれにせよその意識から強力で永
続的な<動機付け機構(motivational systems)>を相当数解離するようにと求められるならば,その人は将来精神障害になる危険が
かなりある。その人が発達途上で必ず通過しなければならない対人的な場のどれかにおいて必ず不適応を起こすだろう。なぜ必ず不適
応を起こすかといえば,その人の活動が二つに分裂しているため,すなわち意識の枠内にある活動と枠外にある活動とに分かれてしま
ったためである。」 「対人的な関わり合いをもとうとする心理的諸傾向より成る一つの系統(system)が<自己>から解離できないほど
の多量のエネルギーを含み,しかも葛藤や不安が続くならば,<自己態勢>は,<再象徴化(象徴づけのやり直し・resymbolizaition)
>という過程によっておおよその安全を得るという手に出ることがある。」それは,「昇華の方向への問題の立て直し」であり,安全を確
保していこうとする一つの現れなのである。
そして,何らかの体験により,<自己>の外に解離した系統を<自己>の中に受容することを余儀なくされるならば,それは「結局,
人格に大幅の変化を生じることであり,それは今後自分が存在の拠り所とする対人的な場の種類も大きく変わることを意味する。」
以上,サリヴァンのパーソナリティ理論の概要を紹介してみましたが,これから,この理論に沿って,パウロの翻身の体験を理解して
いこうと思います。