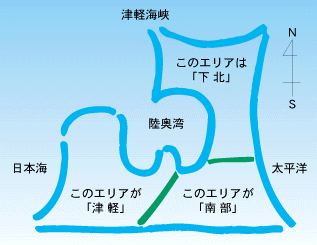
「下北」は厳密に言うと「南部」なんですが、歴史的背景などから言葉も習慣も「南部」とは趣を異にしています。
そこでここでは「津軽」「南部」「下北」の三地域に分けてみました。
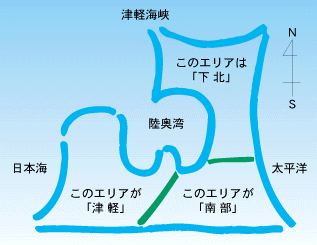
16 それは決して言っちゃダメ 2003/6/18
唐突ですが、お嬢さんをお持ちのお父さん、息子さんをお持ちのお母さん、お子さんと一緒にお風呂に入っていたのは、お子さんが何歳の時まででしたか?
私が生まれて4歳になるまでは、むつ市内で父方の祖母や叔父夫婦と同居でした。物心ついた時には私は「おばあちゃんの係」だったので、お風呂はずっと祖母と一緒でした。父や母とお風呂に入った記憶がありません。
4歳の時に、父の仕事の都合で青森市内の六畳二間のアパートに引っ越したんですが、ここは内風呂が無く、それから5年半ほどは近くの銭湯(でも子どもの足には遠かった)に通うことになりました。
ここで私は初めて、「父と一緒に男湯に入る」ことを経験しました。もっとも普段は「母や妹と一緒に女湯」だったわけですが、当時でも比較的若い時期に子どもを持った父は娘二人を自慢したかったのと、弟が生まれてからは愛する女房が赤ん坊の世話で大変なため、その手助けのために私や妹を連れて、時々男湯に行ったわけです。
当時は私も幼くて、お風呂で男の人に自分の裸を見られて恥ずかしいとか、男の裸を見ることができて嬉しい恥ずかしいとかといったことはまったく感じませんでした。
ただ、なんとなく男湯の方が女湯に比べてお湯の温度が高いような気がしたのと、なんとなく男湯の方が女湯に比べてお湯をうめにくいなと感じたのとで、
「できれば女湯の方に入りたいなあ」
とは思っていました。でも実際は、お湯の温度は男湯も女湯もそう変わらないでしょうし、
「熱い?それくらい我慢しなさい。みんなが入るお風呂なんだから」
と言う母と違って、
「熱い?よし!バンバンうめろ!!」
と言う父と入る方が、よっぽど入りやすかった、ということもありました。
まあ、そんなこんなで私は父と一緒にお風呂に入ること自体には、そんなに嫌悪感も抱かずに育ったわけです。
そうこうしているうちに小学校に入学すると、男湯で同じクラスの男子に会うようになりまして、さすがにこれは
「ちょっと困ったなあ」
と、父自身が思うようになったようです。その頃になると弟もそれなりにお風呂で私達と遊べるようになり、私達きょうだい3人は母と一緒に女湯に入る、ということが何年か続きました。
小学校4年の夏休みに父の転勤に伴って南部地方に引っ越しまして、社宅に入りました。この社宅は青森のアパートに比べて一部屋増えたのと、水洗トイレだったのと、なんと内風呂がついていたのとで、子ども心におったまげた憶えがあります。冬の寒い日でも、風呂上がりにアノラック(防寒着の一種。今もあるかどうかは謎)を着込んで帽子を被ってマフラーを巻いて長靴を履いて手袋をはめて延々歩いて帰ることも無い、というのは、やっぱりいいもんですわ。
で、お風呂なんですが、戦中育ちの倹約家の母の教えで、「なるべく一緒に続けてさっさと入る」ことが我が家のルールでした。さほど広くもない浴室でしたが、親が入る時に子も一緒に入って、時間と、冷めたお湯の追いだきを極力抑えることで灯油代と、浴室の照明の電気代を節約したんですね。寒い冬場などは、特にその傾向がありました。
それで私は何年かぶりに父と一緒にお風呂に入る機会ができたわけですが、さすがに小学校4年生くらいになると、男親と一緒にお風呂に入るのはあまり気の進まないことでした。でも「嫌」と言ってしまえば角が立つし、親子の間でそんなことを言うのは親不孝だという思いもあったし、母の言う「倹約」もそれなりに理解できたので、小さい頃から「いい子」だった私は、ただの一度も「お父さんと入るのは嫌だ」などとは言わずに自分の羞恥心をぐっとこらえ、
「父と一緒に入るのは、親孝行な、いいことなんだ。恥ずかしいと思うのは、そう思う自分の心が貧しいから恥ずかしいんだ」
と自分に言い聞かせつつ、時には父と一緒にお風呂に入っておりました。なんて健気な子だったんでしょうか、私は。
そんな健気な私が、いつから父と一緒にお風呂に入らなくなったのか。それは小学校も終わり頃のある日のことでしたが、私はその時のことを今でも鮮明に憶えています。
その日、いつものように「お湯が冷めちゃったら灯油代がもったいないから、お父さんと一緒に入ろう」と、羞恥心を抑え何でもない顔で、父や妹と一緒にお風呂に入っていました。先に身体を洗った父が私や妹と交代で浴槽に浸かり、私と妹が洗い場で身体を洗い始めた時のことです。
私達が身体を洗っている様子を見ていた父が、何気なく言った言葉。
「おっ、おめもだんだん、毛が生えできたな♪」
「父とはもう一緒には入れない」と思った瞬間でした。事実、それからは一度も一緒に入っていません。親にしてみれば娘の成長を喜ぶ言葉だったのだろうとは思いますが、思春期を間近に控えた少女が受け止めるには、いささか荷が重い言葉でした。この一言さえ無かったら、私はまだしばらくは、父と一緒に入っていただろうに、と思います。
全国のお嬢さんをお持ちのお父さん、いずれどこの馬の骨とも知らぬ男のもとに嫁いでいく大事な娘と、今は一回でも多くお風呂に入っていたいと思うなら、間違ってもこの一言だけは言ってはいけません。
私は自分自身のこういう経験があるものですから、現在小学校5年生のムスコにも、
「チンチチンが立派になってきたね〜♪」
などとは言いません。なので、今でもムスコと一緒に、お風呂に入ってます♪
15 宴たけなわ 2001/3/17
今年はまた3月に入ってもやたらと寒い日があったり、このあたりではめずらしく雪が降ったりしてますが、さすがにこの季節ともなると、あちらこちらで花粉症のくしゃみやら鼻水やら涙やらで、実にかまびすしいことでございますな。実は私も御多分に漏れずアレルギー体質でして、小さい時からそれはそれは「かちゃくちゃない(訳:とにもかくにも面倒でやっていられない)」思いをしてきました。
私はもともと蕁麻疹がありまして、と申しましても食べ物で出たことはなく、「機械的蕁麻疹」とでもいうのでしょうか、よくパンツのゴムのあとが痒くなって掻いていると、他のなんともなかったところもどんどん痒くなって、気がつくと全身掻きむしって真っ赤になり、血がにじむどころかモロに出血しているという子どもでして、大きくなってからは二の腕をわざと爪で引っ掻いてみみず腫れをつくり、それで腕に模様を作って友達にウケるということなど、朝飯前でした(←昔から身を削ってでも笑いを取りたかったヤツ)。一度だけタンスに長い間入れていた服を着た時に呼吸困難になるほどの蕁麻疹が出たことがありまして、医者の話ではタンスに入れていた防虫剤のせいかもしれないということでしたが、薬品が原因か?と疑われる蕁麻疹は、今までの人生の中で、ただその1回だけです。
4歳の時にむつ市から青森市に引っ越したんですが、引っ越したころから喘息になり、さらに9歳の頃にアトピー性皮膚炎が発症しまして、以来、この病気とも長い付き合いになりますな。
思い起こせば当時は「アレルゲン(アレルギーの原因)」といえば、誰でもまっ先にあげるのが「卵」と「鯖」で、次にちょっと知ってる人などは「ブタクサ」「セイダカアワダチソウ」「キク」「ユリ」などの花粉をあげるといった頃でした。ところが私は何度検査をしても、そのどれにも引っ掛からなかったんですね。私が喘息の発作を起こす時は、どういうわけか低気圧が通過するころだったり、夏から秋にかけて台風がやってくるころだったり、晩秋になってシベリア寒気団が降りてくるころだったりと、天気に関係していました。母の話ですと、夜中、ぐっすり眠っている時に屋根に雨が「ぽつ」とあたると発作を起こしていたりもしたようでして、雨音が聞こえてもいないのに不思議なものだと思ったそうです。
実はムスコも私に似たのか2歳の頃から喘息がありまして、いちおう卵の白身やハウスダストにアレルギー反応は出たんですが、やはりどちらかというと天気と大きな関係があるようです。一度台風情報もないのに天気のいい日に強い発作が出たことがありまして首をひねっていたんですが、翌日の天気予報で「実は昨日は言わなかったんですが、南の海上で、昨日台風が発生しておりまして‥‥。」と言ったことがあり、「まるで台風レーダーのようなヤツ‥‥‥。」と思ったこともありました。
それでも今はいい薬が出来たものだなぁと、ムスコを見ていて思いますね。だってちゃんと発作に効くんですから。私が小さい時はアレルギーに関しては解っていないことが多すぎて、薬は効かないし、医師達でさえどうすればいいか解らずにオロオロするといったことも少なくありませんでした。まして喘息が気象と大きな関係があることに経験から気付いていたのは一部の医者と患者達くらいなもので、医者ですらそうなんですから世間での認知度はさらに低く、「喘息で死ぬヤツはいない。」とか、「気持ちが弱いからそんな病気になるんだ。」とか、「マラソンで鍛えれば治る。」とか、まるで根拠のない乱暴な意見を振り回す人がたくさんいて、発作が起きていて苦しいのに無理矢理マラソンをさせられたり、横になるとますます発作がひどくなるのに「寝てれば治る。」と無理に布団に寝かされたりといった、今では「発作中は御法度なこと」をさせられたことが、よくありました。
はっきりと申しましょう。喘息は下手をすると死ぬ病気です。だいたい気持ちの弱い子に、あんな苦しい発作に耐えることなど出来ません。発作を起こしているのにマラソンをさせるなんて、脚を骨折した人に「鍛え方が足りないからだ。」と松葉杖をついたまま走らせるのと同じ行為です。もちろんちょっとくらいの環境の変化にもびくともしない、強い体を作るのは大事なことです。でもそれはあくまで医師の指導のもとに、発作のない時にゆっくりと始めるのが大切で、なんでもかんでもただやみくもに「鍛えりゃ治る」と考えている「脳みそも筋肉」な人たちが言うほど、単純なものではないんです。さすがに最近はそういう「脳みそも筋肉」な人たちも減ったかな?と思ってみていますが。
かように私はアレルギーでかちゃくちゃない思いをしてきましたが、面白いことに、今のところ花粉症はないんですよ。不思議ですよね。季節の変わり目の今くらいの時期は喘息にちょっと気をつけることはありますが、花粉症の方は平気のへいざ、「へのカッパ」です。ここ十数年で花粉症の患者が爆発的に増え、以前はアレルギー患者に暴言を吐きまくった「鍛えりゃ治る教」の「脳みそも筋肉信者」達の中にも、大変な思いをしている人も多いと思います。そういう人たちを見てるといい気味でいい気味で思わず笑みがこぼれ‥‥‥ああ、いやいや、気の毒で気の毒で思わず目頭が熱くなってしまいますな、ホントに。「明日は我が身」、私だっていつ花粉症になるか分からないのですから、今は花粉症の患者さんに向かって「鍛え方が足りないんじゃないの?」とか「気にしてるからますますひどくなるんじゃないの?」などとは、決して言いますまい。心で思ってたとしても、ほほほほほ♪(←いい性格)。
ところで先ほども書いたように、私は9歳からアトピー性皮膚炎でも「ゆるぐない(訳:大変な)」思いをしてきたんですが、なんと去年の10月、発症から実に28年目にして、実はアトピーじゃなくて「脂漏性皮膚炎」だったことが判りました。症状も使う薬もよく似てはいますが、全く別の病気だと言うんですね。それまで自分のアレルギー体質の遺伝のせいでムスコにも辛い思いをさせていて、今はまだ大丈夫だけど、いつムスコやムスメにもアトピーが出るか分からない、出たらどうしよう、と思っていた私には、この診断はまさに「天の加護」とも言うべきものでした。
アレルギーやアトピーで辛い思いをしている皆さん、こういうこともあるんですから、絶対に気持ちを腐らせちゃダメですよ〜〜ん。
いや〜、皆さん、今年の冬はなんだか寒いですねぇ(←と毎年言ってるような気が)。実家方面でも「今年は寒いし雪多いし、まんずゆるぐねじゃ(訳:本当に大変よ)!!」なんて言ってます。青森県というと12月から翌年3月まで県内全域で毎日ドカ雪が降っていると思われがちですが、実際のところは津軽や下北に比べたら南部なんてほとんど雪は降らないし(←でも寒い)、皆さんが思い描くいわゆる「青森の冬」の寒さと雪は、2月がピークになります。そりゃ11月も12月も1月も3月も雪は降るし寒いですし、4月の入学式の頃にもどうかすると雪が降ったりするし、一昨年だか一昨々年みたいに春分の日に一晩で70センチも降るなんてこともたまにはありますが。
雪が多くて困るのは、何と言っても女排泄、いえ、除排雪関係です。車道は除雪車がやってくれるとしても、そのままでは玄関の前に車道の雪がうずたかく積まれたままになってしまうので、玄関から道路に出るために通路を作らなきゃいけないわけです。しかも都市ガスじゃなくてプロパンガスなので、ガスボンベの交換や地震や火事といった非常時の避難路の確保のために、家の周りの雪かきが必要なのです。特に私の実家などは、2年程前に玄関先までやっと道路がついたので今はすぐ前まで除雪車が入ってくれるようになりましたが、その道路がつく前は畑の中の一軒家だったために、道路に出るまでの約150メートル程の農道をとにかく人が通れるようにするのに、一日に何度でも積もったら雪をかき、積もったらまた雪をかきの繰り返しでした。子どもでも登校前や下校後に、せっせと雪かきをするんですよ。あとで親が仕上げの雪かきをすることも多いですが(←ちぇ)。
もうひとつ、雪かきと並んで大事な作業があります。「屋根の雪下ろし」ですね。これは道路の雪かきと比べると、必ずやらなければいけないものってワケではないようですね。雪の少ない年なんかは、一度もしなくていいこともありますし。しかも最近は雪国の建築方もだいぶ変わってきてるようでして、これまでは屋根に傾斜をつけて自然に屋根雪が落ちるようなシステム(?)が主流だったのですが、十数年前くらいから、ちょっと見にはまるでビルの屋上のような、平べったい感じの屋根になってきています。「あんな形の屋根だったら雪が自然に落ちなくて雪下ろしも大変だろうに、どうして最近新しく建つ家は、ああいう平べったい屋根ばっかりなんだろう?しかもいつ見てもあまり雪が無いし。」と常々疑問に思っておりましたが、去年、とある方のおかげでその疑問が一気に氷解いたしました。
あの屋根の造りは「無落雪構造」というものだそうで、下から見たら平べったく見える屋根は、実は中心に向かって漏斗のように傾斜しているんだそうです。で、家自体の熱と雪の重みで発生する熱によって、雪は自然に溶けてしまうんだそうですよ。かなりの量の屋根雪でも嘘のように溶けてしまうそうでして、溶けた水は屋根の中心の樋から地面や側溝に流れ落ちるしくみになってるんですね。時に漏斗の傾斜角度によっては雪が溶けにくいこともあるらしいですが、大工さんの話では下手に雪下ろしをしてはかえってよくないということだそうで、まぁ、こんなふうにして、雪国の生活も徐々に変わっていくということなのでしょうね。
いいですよね、「無落雪構造」。これなら屋根の雪下ろしをしなくてもいいし、氷の巨塊と化した屋根雪がいきなり落ちてきて怪我をしたり死んだりすることも無いし、第一隣の敷地に自分ちの屋根雪が落ちて隣の家の窓ガラスを割ったり(←本当)、あるいはその反対に隣の屋根雪が自分ちの敷地に落ちてきて家の外壁を傷めたりしてご近所と不仲になったりすることも防げるわけですもんね(←これも本当)。
いえ、大袈裟な話じゃないんですよ。どんなに仲の良いお隣どうしでも、お互いの家の屋根雪の落ち方一つ、雪かきした時の雪の捨て方や捨て場所一つで、あっという間に犬猿の仲になってしまうことも少なくないんです。極端な例では春から秋までは仲良く近所付き合いをするのに、冬場は顔を合わせても挨拶すら交わさなくなるなんてこともあるらしいです。いえ、聞いた話ですよ。実家ではそういう事態になったことはありませんでしたし。いえ、ホントですって!(←なぜ強調?)さっきも書いたように、実家は「畑の中の一軒家」なので、お隣との間に比較的余裕があるわけです。ですから庭続きのお隣の家の二階の屋根雪がまず一階の屋根に落ちて、その勢いで物置きの屋根に落ちて、物置きの屋根の傾斜のせいで二階と一階と物置きの屋根雪が庭の塀をダイレクトに越えて(ほぼ)全部うちの庭に落ちてきても、うちのプロパンガスのボンベを直撃することもないですし、せっかく雪かきしたばかりの玄関先がまた隣の屋根雪に埋もれてしまうといったこともありませんでしたから。ちょうど隣の屋根雪が(ほぼ)全部落ちてくるところに植えていた庭木の枝が、雪囲いをしていたにもかかわらず冬中の屋根雪の落下のせいでボキボキに折れてしまっても、別に家族が怪我をするわけでもないですしね。ですからお隣と不仲になったことはないんですよ、ええ(←妙に強調)。
そんなわけで実家の庭は隣の屋根雪が(ほぼ)全部落ちてくるので、それはそれはものすごい雪の山ができるんですね。あたりまえといえばあたりまえですが、それが春になるとしっかり溶けるんですから、自然の魔法ってすごいと思ったりします。
春、あんなに積もっていた雪が消えていくのを見る喜びと感動は、神様が雪国の人にだけ許した特別なものかもしれません。雪が消えていくにつれ雪に隠れていた空き缶や空き瓶やプラスチック容器などのゴミが出てきたり、道が泥んこになってしまって車とすれ違うたびにヒヤヒヤしたりしますが、あれだけ長かった冬としばらくおさらば出来るんですから、まぁ、良しとしましょう。
あ、雪が溶けてその下から出てきたもので、今まで一番驚いたものの話を一つ。さっきも書いたように実家の庭にはお隣の屋根雪が(ほぼ)全部落ちてくるんですが、その屋根雪が溶けた下から布団が一枚出てきたことがあったんですね。うちの布団じゃないですよ。お隣のです。ある秋の日、天気がいいので物置きの屋根に布団を出して干していたんでしょう。取り込むのを忘れたか(←そうなのか?)、それとも取り込む暇もない程にあっという間に雪が積もったものか(←いや、それはいくらなんでもちょっと‥‥‥)、とにかく物置きの屋根に出されたままだった布団の上に雪が積もり、屋根雪と一緒にうちの庭に落ちてきたというわけです。布団が無くなったのに気付かないお隣もすごいですが、こちらも布団が落ちてきたのに全く気がつかないでいましたからね。いかにお隣の屋根雪の量が半端でないかがおわかりでしょう。あ、そのひと冬雪に埋もれてグショグショになった布団は、春、お隣が引き取っていきました、はい。
お隣、お布団じゃなくて、一万円札を干さないかなぁ(←おいおい)。
それも屋根いーーーっぱい!!!(←‥‥‥)
「青森県出身」だと言うと、「じゃあ、スキー得意でしょ!」っていうのと同じくらいの頻度で言われることがあるんですじゃ。「青森って寒いんだよね!?」っていうのがそれですね。大概の人は青森県っていうと「寒い」しか感じないらしいんですよ。夏でも「寒い」って思ってるらしいし。どうかすれば北海道よりも寒いんじゃないかって思われてるらしいんで、笑っちゃうんですが。
あのさ、冬の青森は「暑い」よ!いや、ホントだって!!関東地方や関西地方の人達の想像をはるかに越えて、めちゃめちゃ暑いんだってば!!
あのね、昔ならいざ知らず、冬に寒い地方ってのは、家の中だけは暖かくしようと思うもんなのよ!!でないと家の中で遭難しちゃうでしょ!!(←あのな‥‥‥)暖を取るのはこたつだけなんて関東や関西に比べたら、どれだけ暑いか。エアコン暖房なんかよりもうんと火力の強い石油ストーブや石炭ストーブや薪ストーブを、ごんごん焚くわけよ。しかも今時なんかは床暖房も一緒に使うから、家の中、特に居間の暑さといったら、ハンパじゃないんですぞ。
かくいう私の実家も寒がりの父のせいで石油ストーブ&床暖房なので、冬場の居間の暑さといったら、座っていて立ち上がると、立ちくらみ以上に暑さでボーーーッ、クラクラクラ‥‥‥とするくらい暑いんですな。
あんまり暑くてクラクラするんで、寒さにも暑さにも弱いお嬢様な私が、とうとう「サーキュレーターつけようよ。」と言い出して、つけたことがあったんでよ。あ、サーキュレーターっていうのは、部屋の空気を撹拌して、天井近くと床上の温度差を無くす装置だと思ってもらえばいいですな、はい。
いや〜、快適快適。暖かいながらも常に部屋の中を空気が動いていて、「適当に暖かく適当に涼しい」のが身体に合っているお姫様な私には、実にいい環境が出来ました。
ところが。サーキュレーターの風が「寒い」と言う父の為に、せっかく取り付けたサーキュレーターをほどなく使わなくなってしまったんですね。へう〜〜〜〜〜〜〜〜〜。
でもここでガックリきてはいけません。実はクソ暑い中にもそれなりに楽しみというのがあるんですよ。外は零下20度近くにもなって、ビーフシチューも鍋の中で凍ってしまうような厳寒の夜、居間のごんごん燃えさかるストーブの前でホカホカの床暖房の上に座り、顔を暑さで真っ赤にしながら食べるアイスクリームの旨いこと旨いこと。これがやめられないんですよ、ホントに。夏に食べるよりも美味しいんじゃないかって思うくらいです。
ポイントは「座る位置」。一口に「石油ストーブの前」と言っても、ストーブの場所によって熱がガンガンくるところとそうでもないところがあるわけです。なもんでアイスクリームを一番美味しい状態で食べたい女王様な私は、ストーブの一番熱い面に対して座って、アイスクリームを食べるわけですね。いえ、実は他の家族もちゃんと熱い面に向かえるくらい、大きなストーブだってだけの話なんですが。
「青森は一年中寒い」としか考えられない人には、想像も出来ない楽しみでございますな。
東京時代、山口県出身の友達に「山口県って、雪降るの?」と聞いて、笑われたことがありましたっけ。な〜〜〜んだ、私も「青森は寒い」ってしか考えてない人と、似たようなもんだなぁ。
12 実家の年越し 2000/12/28
さて皆さん、今年もいよいよ押し迫って参りました。クリスマスが終わるとまるで競争でもしているかのようにお正月準備のための品物が街に並び、「洗脳でもしてくれるのか?」という勢いで正月関係の曲がリフレインされますね。ところで「師走」の「師」とは「学校の先生」のことではなくて「お坊さん」のことだとご存知でしたか?お坊さんというのは心身の修行を積んでいるので普段は慌てて走ったりしないものらしいのですが、そのお坊さんでも走らずにはいられないほど忙しい、というのが
「師走」の意味だそうです。はい、ためになりましたね。
実は我が家では、お正月は一年おきに宝塚市とむつ市の実家で過ごすことにしておりまして、今度のお正月は実家の番だったのですが、義父が亡くなったためにそうもいかなくなりました。いえ、私が「お正月にも実家に帰りたい。」とダンナにダダをこねたわけじゃありませんよ。むしろ「毎年田名部祭りに帰してもらえるだけでもありがたい」と、結婚してからムスコが生まれて一歳半になるまでの五年間はお正月には里帰りしたことはありませんでしたし、ただの一度も「冬にも帰して。」と言ったことはなかったんですから。では、どうして「一年おきの正月帰省」が実現することになったのでしょうか。
ムスコが一歳過ぎになったある秋の日、ダンナがぽつりと言いました。「ムスコにも冬の青森を見せてやりたいなぁ。雪に触らせてやりたいなぁ。」たしかにそうでした。何しろ遠くて足代がかかるために滅多に里帰りできず、実家の両親や祖父母(三年前に亡くなった母方の祖父や一昨年亡くなった父方の祖母も、当時はまだ元気でした)にはなかなかムスコの顔を見せてやれずに、心苦しく思っていたのです。そんなわけで「冬の帰省はこれが最初で最後かも」と思いつつ、ダンナが冬休みに入るのを待って、親子三人で実家に行きました。
ところで青森県のように冬が長くて雪も深く、昔は今ほど冬場の娯楽なんか無かったろうというところは、客をもてなすというととにかくお酒やご馳走を並べて「やれ食え、それ食え」となったものらしいです。他のお宅のやり方はどうなのか知りませんが、実家では年越しの夜から母方の実家から借りてきた時代劇で見るような朱塗りのお膳に年越し用のご馳走を並べて、大皿にくだものやお菓子を盛った「くちとり」と呼ばれるものが出されるわけですね。「くちとり」の内容ですが、盛る品数で「三つ盛り、五つ盛り、七つ盛り」などと呼ばれまして、家族の好きなものなら基本的に何でもいいんでしょうが、たとえば「りんご」「みかん」「駄菓子」の三種類で「三つ盛り」、それに「クッキー」と「おせんべい」を足して「五つ盛り」、そこに「バナナ」と「チョコレート」を足せば「七つ盛り」などと、一つ一つをとってみれば豪華でも何でもないものなのですが、「年越しそば」同様、大晦日の晩にはとても重要な役所を演じるメニューの一つなわけです。昔は「くちとり」に使われるお菓子といえば落雁やお饅頭やお団子の類いが多かったようでうちでもそうだったのですが、私が中学生の頃からあまりこだわらなくなって、子どもの好きなケーキやシュークリームやドーナツになったりしました。
朱塗りのお膳の方にしても、「これにあとお雑煮と茶わん蒸しと焼いたサケが入れば、すっかり元旦のお膳」と言っていいくらいのご馳走が並ぶわけですから、それまで「年越しのメニューと言えば年越しそば」しか知らなかったダンナは、それはそれは驚いたものらしいです。しかもうどんの方が美味しい関西地方に比べるとそば自体が美味しい上に、小さめの器に少しずつ入れたそばの上にとろろと七味とネギをかけて何度も何度もおかわりをするという、それまで全く経験したことのなかった食べ方に、ダンナはもうすっかりメロメロになってしまったのでした。そのメロメロがまだ覚めやらぬ翌日の正月一日、朝からやはり朱塗りのお膳(重箱じゃないのがポイントです)に山海の珍味や郷土料理が並ぶわけですから、もうダンナは完璧にKOされてしまったのでした。そして‥‥‥。
「ママ、宝塚と田名部(たなぶ)と、正月は一年おきにしよか。」
「えーーーーー!?いいよ、なんも。そったにぢぇんこ(お金)無べさ。」
「いや!そうしよ!ムスコにもそうするのがいいに決まってるやろ。」
「へても田名部祭りさ帰るのだげは譲れねよ!」(←なんといってもこれが一番大事!!)
「それはええねん。とにかくあの料理とそばを食いたいねん!!」(←ここで語るに落ちる)
「‥‥‥‥‥‥帰省積み立て、まんだUPしねばねのー(しなきゃいけないねー)。」
これが一年おきに正月帰省ができるようになった理由です。その分足代がかかるようになりましたが、ムスコもムスメもまだ本格的な降りではないとはいえイトコ達と雪遊びが出来ますし、特に32年ぶりの女児誕生となったムスメは、90歳のひいおばあちゃんの生きる力となっているわけです。子どもが大きくなってくれば部活だ補習だとますます帰れなくなるでしょうから、今のうちは多少無理をしてでも帰省することにしましょう。うしっ!!
唐突な出だしで大変申し訳ありませんが、皆さんは子どもの頃、替え歌を歌いませんでしたか?それも「怪しい替え歌」を。童謡や文部省唱歌、はてはCMソングまで、大人が聞いたら顔をしかめるか苦笑するかというような替え歌を、男の子と一緒になって大きな声で歌っていました。出所は分かりません。誰かが歌っていたのを聴いて、面白くって真似して歌っていたんですね。
覚えている中で一番古いのは、幼稚園時代に歌っていた「うれしいひなまつり」(サトーハチロー作詞 河村光陽作曲)の替え歌で、「かなしいひなまつり」という歌です。
♪あかりをつけたら消えちゃった
お花をあげたら枯れちゃった
五人囃子は死んじゃった
今日はかなしいひなまつり♪
なんて他愛のない、可愛らしい歌なんでしょうか。実に無邪気です。しかも驚いたことに、ムスコも学校でこの替え歌を習って(?)きて、「ママァ、こんな変な歌、知ってるぅ?」とさも嬉しそうに歌うんですね。細かい部分に多少の違いはありますが、まさしくこの歌なんですよ。これって全国の小学生の間で、代々歌い継がれているものなんですか?(←おしまこ?)
もう一つ、幼稚園時代に歌っていた替え歌に、こんなのもありました。「きらきら星」(武鹿悦子作詞 フランス民謡)のメロディで歌う「ABCのうた」がありますが、その替え歌です。
♪ABCの海岸で カニにキンタマ挟まれた
「いでいではなせ」「はなすもんかソーセージ」
赤チン塗っても治らない 黒チン塗ったら毛が生えた♪
なんとのびのびとおおらかな歌なのでしょうか。男の子にとってここを挟まれる以上の苦痛があろうか?(いや、無い!)という場面においてさえ、カニとの心楽しげな触れ合いをはかっています。しかも「毛が生えた」と、思春期の心と身体に大きな変化と動揺をもたらす第二次性徴を、さらりと表現しているではありませんか。まさに「性教育替え歌」とも言うべきものですね。「きらきら星変奏曲」を作曲したモーツァルトも、草葉の陰で感涙していることでしょう(←言い切った)。当時私は父親とお風呂に入りながら、「パパも黒チン塗ったんだ。」と思ったものでした。
他にもありますよ。例えば小学生時代に歌っていた替え歌で、こういう歌がありました。
♪朝は四時半 空弁当下げて
会社に出かける お父ちゃんの姿
シャツはボロボロ パンツはクソだらけ
ああかわいそう 給料は30円♪
後に高石ともやとナタ−シャセブンが歌っていた『朝の四時ごろ』というタイトルの歌らしいこと、しかも私達が歌っていたのはかなり歌詞が違ってしまっていたらしいことなどが判ったのですが、いくら20年以上前のことだと言っても、お給料が30円というのはいかにも涙を誘う、もののあはれを見事に歌い切った替え歌ではありませんか。もちろんこれは、「♪山は白銀 朝日を浴びて」の歌い出しで誰もが知っている、「スキー」(時雨音羽作詞 平井康三郎作曲)という歌の替え歌ですね。この替え歌を、ムスコが学校で「習う日」がはたして来るのか!?非常に興味深いところではあります。
さて、普通こういう他愛もない替え歌を中学生になっても歌っている子はまずいないものですが、妹の友達でかなりなつわものが一人いました。中学生だったある日、妹が「友達が作った替え歌だ」と言いながら歌って聞かせてくれたのは、北は北海道から南は沖縄まで、知らない人はただの一人もいないだろうと思われる、あの曲の替え歌でした。
♪ボクの名前は「キン坊」、ボクの名前は「タマ坊」
二人合わせて「キンタマ」だ、キミとボクとで「キンタマ」だ
大きなものから小さなものまで
サイズもいろいろ男の世界♪
語感の面白さからゲラゲラ大笑いしたものですが、私はこの歌で「大きなものから小さなものまでいろいろあるらしい」と知ったのです。それまでは父と弟のしか見たことがなかったので、「大きなものと小さなものがある」という認識しかありませんでしたから。実に奥の深い、男性のアイデンティティーにさえ関わるような、まさに「哲学」といった感のある替え歌ですね。
さて、いくつか替え歌を紹介してきましたが、小学生時代に歌っていた替え歌で、どうしても途中から思い出せなくて焦れったい思いをしている歌があります。皆さんはテレビのヒーロー番組で、「愛の戦士レインボーマン」というのがあったのを覚えていらっしゃるでしょうか?この「レインボーマン」のオープニング「行けレインボーマン」(川内康範作詞 北原じゅん作曲)の歌い出しは「♪インドの山奥で修行して “ダイバダッタ”の魂宿し」というのですが、一番頭の「♪インドの山奥で」のメロディだけを繰り返しながら言葉をどんどん数珠のようにつなげていった替え歌があります。
♪インドの山奥でっ歯のハゲアタマんじゅう食いたい菜っ葉の干し菜汁‥‥‥‥‥
私が覚えているのはここまでです。「干し菜汁」の次にはいったいどんな言葉が来るのでしょうか?当時のクラスメートで「類家(るいけ)君」という子がいたのですが、どうしても「るいけ」という言葉が出てきてしまい、記憶をたぐることができません。ああっ!奥歯にものが挟まっているような、ノドの奥に小骨が刺さっているような、焦れったいこの感じ!!この歌の続きをご存知の方は、ぜひとも教えてくだされませ。
情報、お待ちしております。