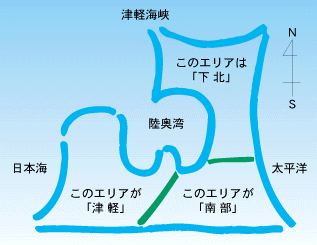
「下北」は厳密に言うと「南部」なんですが、歴史的背景などから言葉も習慣も「南部」とは趣を異にしています。
そこでここでは「津軽」「南部」「下北」の三地域に分けてみました。
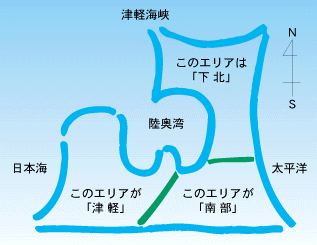
と言っても青森県に動物園は無かったように思うんですよ。浅虫温泉(あさむしおんせん、当時は浅虫)に水族館はあったんですが。
私が小さい頃には下北半島の付け根に「むつ観光牧場」だったか「下北観光牧場」だったかいう、タイワンザルやらラクダやら何やら広い敷地内に放し飼いになってるという、まぁちょっとしたサファリパークのようなところがあったんですがほどなく潰れてしまいまして、今は名残りの錆びたフェンスだけが強風吹きすさぶ原野にぐにゃりと立ってるんですな。
小さい時から人間以外の動物が好きで好きで、親にさえ「お前は神様が間違って人の姿にしちゃったのかもねぇ。」と言われるほど、朝から晩まで動物の本を夢中になって読んでいました。いえ、狭い意味の動物でなくて植物に対しての動物ですから、鳥も魚も虫も爬虫類も両生類も好きでした。それなのに動物園が無い!!辛かったっすよ、ええ。
ところが中学2年だか3年だかに気づいたんですが、「移動動物園」って言うんですか?ああいうのが「むつ松木屋」(デパートの名前)の屋上に来るっていうじゃないですか!!行きましたよ、すぐに。いや〜、いるいる、それなりに。さすがにキリンやゾウの類いはいなかったと思うんですが、サルとかライオンとかトラとかポニーとかワラビーとか鳥類とか、そのあたりの動物が小さな檻に入れられてちょこんと展示されていました。
で、なんとな〜く気になったサルがいまして、なんだったかな、チンパンジーだったかニホンザルだったかタイワンザルだったかちょっとよく覚えていないんですがまだ子ザルでして、檻の向こう側の壁にぴったりくっついてふるえていたんですね。で、なんとな〜く檻の前に右手の甲を出してみたんですよ。そしたらその子ザルが奥から出てきて、なんとまぁ、私の手の甲の毛づくろいを始めたじゃありませんか。自分で差し出したとはいえ、さすがに驚きましたね。だって毛づくろいですよ、毛づくろい。劣位のサルから優位のサルへのおべっかであるとか、互いの親愛の情の表現であるとかいろいろなことが言われていますが、そんなことはどうでもいいくらい嬉しかったですね。またその子ザルの手つきの優しいこと。ちょっとひんやりした、ちゃんと力加減した手つき。思わず「ごめんね〜、毛が少なくて。」と口に出してしまいました。
考えてみたら子ザルの檻の前に柵がなかったからできたことかもしれませんね。普通は手を出したら引っ掻かれるか噛みつかれるかどっちかだろうと思うんですが(実際3、4歳の時に、子ザルに顔を引っ掻かれたことがあります)、あの子ザルにとって私はそんなに親しみの持てる顔だったのでしょうか?いや、顔じゃないかもしれませんね。もしかしたら母親のような匂いを感じ取ったのかもしれません。14、5歳の娘に母親の匂いを感じるというのはちょっと無理があるかもしれませんが、なんと言っても相手はサルですから、我々ホモ・サピエンスの想像を遥かに超えたことを考えたり感じたりしていたのかもしれません。とても嬉しくて、ちょっぴり人間の自信を無くした出来事でした。
ところでこれを読んだ良い子の皆さん、皆さんは私のマネをして動物の檻の前に手を出したりしてはいけませんよ。サルにぎっちり指をつかまれたら下手したら骨が砕けますし、そのまま噛みつかれでもしたら指なんか簡単に噛みちぎられてしまいます。絶対に手を出してはいけません。解りましたね!!(←自分は出したクセに)
前回は夏になると聞こえてくるイカの売り声をご紹介をしましたが、実はもう一つ、夏場に聞こえてくる声があるんですな。それは、
「シイガ〜〜〜シイガ〜〜〜、びょうぶさんのシイガにメロンはいかがでしか?甘い甘いびょうぶさんのシイガにメロンはいかがでしか?。」
これがいっぱつで解ったあなた、かなり青森ナイズドされてきましたね。では解らなかった方の為にご説明いたしましょう。
これはやはり軽トラでやってくる、「スイカ売り」の声なんですよ。青森県は西津軽郡にあるスイカとメロンの名産地「屏風山(びょうぶさん)」でとれた「スイカ(訛って”シイガ”)とメロンはいかがですか?」と言っているわけですね。
ところで私は子どもの頃から「屏風山って、津軽のどの辺にある山なんだろう?」という疑問を抱いて生きてきました(←ちょっと大袈裟)。だって津軽地方の山といえば、「津軽富士」の愛称で親しまれる「岩木山(いわきさん)」しか知りませんでしたから。あとはひたすら拡がる、お米とりんごの「津軽平野」ですもんね。というわけで、とある方にアドバイスをいただいて、その辺りに詳しい方にお聞きしてみました。すると、
「屏風山というのは実は山ではないんです。辺り一帯砂砂砂だった広大な土地に、砂が風で飛ばされるのを防ぐために松を植えました。その松の防風林の様子がまるで屏風のようなので、”屏風山”と呼ばれるようになりました。砂地ということで、スイカやメロンの栽培に適しているようです。」
という、実に分かりやすい、親切な答えをいただきました(教えて下さった方のWEBサイトはこちら)。
なるほどそうだったのかー。子どもの頃から慣れ親しんだ売り声の意味が、青森を出て18年も経った今、ようやくはっきり解りましたぞ。あああ、実家の皆に自慢したい!!!(←こいつは)
さてこのスイカ、ではじめの頃は1個2000円だったりするんですが、季節になると1個1000円前後になったと思います。この頃になると甘くてシャクシャクで、たまらなく美味しいわけですね。お盆には仏壇に屏風山のスイカをでんと供えたりもして、その存在感のありように思わず仏壇でなくてスイカの方に手を合わせるなんて事も、子どもの頃はありました(←バチあたり)。
ところがこの美味しい美味しい屏風山のスイカが、売れなくなる事があります。
下北地方は太平洋側にあるため、「ヤマセ」と呼ばれる冷たい風が吹く事があるんですね。夏でも「ヤマセ」が吹くと、半袖ではいられなくなるほど気温が下がったりします。さらに「冷夏」(”れいか”。ヤマセや海水温などの影響で、夏でも気温が上がらず寒い)の年なんかは、1個500円でも売れなくなります。そんな年は当然お米や他の作物の出来も悪いわけで、いわゆる「凶作」という、なんともせつなくやるせない年になるんですね。
去年はスイカが飛ぶように売れたのではないかと思うほど、とにかく暑い夏でした。今年もスイカがそれなりに売れるくらい暑い夏になるといいなぁと思っています。
さて、私のふるさとはむつ市田名部(たなぶ)地区でございます。ここには生まれてから4歳までと、14歳から18歳まで住んでいたわけですが、ここで「夏になると聞こえてくる声」というのがあるんですな。それは、
「ガ〜〜〜〜〜イガ〜イガイガイガイガイガイガイガイガイガ〜〜〜〜〜〜、ズッパイでせんえんだ〜〜〜〜〜〜〜。」
朝もはよからこんな何かの呪文みたいな、しかもお世辞にも「朗らか」とか「爽やか」とはちょっと言えない声が、遠くからだんだんこっちに向かってやってくるんですよ。これ、なんのことか解りますか?解りませんね?はい、ご説明いたしましょう。
これは、軽トラでやってくる、「イカ売り」の声なんですよ。訛って「イガ」となり、さらに最初の「イ」がどっかに飛んじゃって「ガ」から始まるように聞こえるんですね。イカは「1匹、2匹」ではなくて「1パイ、2ハイ」と数えます。「10パイ」が訛って「ズッパイ」となり、それが「千円だ」と言っているわけですね。これで解りましたか?解りましたね?はい、良かった良かった。
むつ市の隣にはイカの水揚げ港の大畑(おおはた)や下風呂(しもふろ)などがあって、その関係で新鮮なイカが豊富なんですな。
ここでいう「イカ」は地元で言うところの「真イカ」(マイカ)なんですが、あれは「スルメイカ」ですか?(←よく分かってない)新鮮なイカというのは皮が黒くて身が透き通ってるんですね。だから上京して初めてイカを見た時、「何だこれは?」と思ったもんです。だって皮も身も白いんですよ(←腐る寸前)。仕方がないとはいえ、あまりのショックに、その年はたしか帰省するまでイカは食べませんでした。
ところで「ズッパイで千円」の時というのは、ハッキリ言ってあまり買う気になれません。まぁ、イカの大きさにもよりますが、もうちょっと時期を待って、「ニズッパイで千円」になるのを狙います。
夏の早朝、この売り声が遠くから聞こえてくると、「どれ、イガ刺し(イカの刺身の事をこう呼びます)するが。」と鍋を持って買いに行き(たぶん今ならビニール袋に入れてくれると思いますが)、ちゃっちゃとさばいて細長いイカ刺しにし、あつあつご飯に大根おろしとしょうゆをつけたイカ刺しをのせて食べるというのが、「よくある朝ご飯の風景」でした。
余談ですが、細長い刺身にするといっても「イカそうめん」ではありません。これはあくまで「イカ刺し」です。「イカそうめん」なんて言葉は、私は上京してから知りました。たぶん東京辺りの新鮮なイカを知らない人が、下北や函館なんかの新鮮なイカ刺しを見て「すごい!こんなに細く切ってあって、まるでそうめんみたいだ!!」とでも言ったのが始まりなんではないかと思ってるんですよ(事実、母方の親戚に”この透き通ってるの、ところてん!?”と聞いた東京人がいたとか)。それを地元の人達が「なんだか新鮮な響きだ」などと、観光客用に採用しちゃったんではないかとみているんですが、本当のところはどうなんでしょうね?どなたかご存知ないですか?
今年初めて田名部で暮らし出した方、これでこの声が遠くから聞こえてきても、びびらなくてすみますね。
えー、私は4歳から10歳まで青森市奥野(おくの)――当時は青森市浦町奥野(うらまちおくの)といいました――に住んでいたんですが、その頃に覚えたもので夏の風物詩とも言えるものがあります。
♪チンチンチンチッカチンチンチンチンチッカチンチンチン♪の音と共に70歳がらみのおじいさんがリヤカーにアイスを載せて引いてくる、あれです。そう、私達はそれを「チンチンアイス」(←そのまんま)と呼んで、この音が聞こえてくるのを心待ちにしていたものでした。
うちはおおっぴらに買い食いすることを親が許さなかったので、この音が遠くから聞こえてくると急いで「ママ!買ってもいい!?」と確認し(”ダメ”と言われることは殆ど無かった)、お許しが出ると小銭を握りしめて妹や友達と買いに走ったものでした。
この「チンチンアイス」、どんなのかといいますと、アイスクリームと言うよりはシャーベットに近いかもしれませんね。基本は白1色ですが、イチゴのピンク、メロンの緑、レモン(?)の黄色、チョコの茶色、ソーダのブルー等、何色かのバリエーションがありまして、それをおじいさんがヘラで掻き取って、コーンカップの上にまるで薔薇のつぼみのように盛り上げるわけですね。
「おじちゃん、ひとっつちょうだい。」
「おっきいのが?ちいせぇのが?」
ここで「ちいさいの」と言ってしまうと、小さい上に白1色という、なんとも味気ないものになってしまうので、たとえ倍の値段になろうとも、ここは「おっきいの!」と言うわけですね。
「色、なんぼ入れるば?」
「全部!!」
などというやりとりがあって手にしたチンチンアイスは、綺麗で甘くて口の中でほろほろと溶けて、なんとも幸せな気持ちになったものです。
ところでこの手のアイスは青森独特のものなんでしょうか?ダンナの従妹に一度恐山でご馳走したら(そんな大袈裟なものでもないけれど)、「初めて食べたー。なんかジェラートみたいで美味しい。」って言ってたんですよ。そういえば同じ青森県内でも津軽や下北ではよく見かけたんですが、南部の方ではあまり見ませんでしたね。う〜〜〜ん、どの辺からどの辺までが「チンチンアイス」のテリトリーなんでしょうか?
ところでこの「チンチンアイス」を引いていたおじいさんですが、今思えばトイレなんかはいったいどうしていたんでしょうか?当時の事ですもんね、そこはやっぱり道端で・・・・・。そういえばリヤカーの引き手にはいつも、煮しまったような手拭いやタオルが結び付けられていましたっけ・・・・・。今だったら「不衛生です!!」とかなんとかPTAから即苦情が出そうですね。
この「チンチンアイス」、おじいさんがリヤカーで売り歩かなくなってから、もう大分長い年月が経ちました。今は行楽地やイベント会場、道端などで、ヤマンバなお姉ちゃん達が2、3人で売ってることが多いようです。コーンカップにアイスを盛り上げる手つきがあんまり危なっかしいので、「もしかしたら私の方が上手く盛れるんじゃないか?」などと考えつつ、次回は「夏になると聞こえてきた声」について書いてみましょう(いいのか!?予告なんかして!!??)。
そう、比叡山、高野山と並び、「日本三大霊場」と称される山なのよ。まぁ、歴史がどうとか見どころはどことかいうのは観光案内にどかんと書いてあるからここでははしょっちゃいましょ。いや、なんでいきなり恐山の話をここで始めたかと言うとさ。
だいたい小学校の高学年から中学高校にかけて、「ミステリー」や「オカルト」に興味を持ち出す子って結構いるでしょ。私もそうでね。で、お約束で「○○の怖い話」とか「本当にあった○○な話」とかいう本を、夢中になって読んでた時期があったわけだ。
そんな本の中に「恐山」は必ずと言っていい程出てくるんだよね。書かれ方もだいたい同じで、
「くねくねと曲がりくねった道を車で登っていく。道の両側は木が鬱蒼と茂っていて、昼間でもあまり陽が差し込まず薄暗い。人通りがほとんど無いのも無気味だ。そろそろ着くかという頃、なにやら異様な雰囲気が漂ってきた。山門をくぐるとところどころ蒸気が吹き上げ、熱く煮えたぎった湯がごぼごぼと湧いて、この世のものとも思えぬ風景だ。」
まぁ、こんな感じだよね。
あのさ、
「くねくねと曲がりくねった道」山だもの、あだりめだべさ。へても舗装ささっちぇあべ!?
「道の両側は木が鬱蒼と茂って」だして山だんだってば。木ぃ無ばおがしいべさ!
「昼間でもあまり陽が差し込まず薄暗い」天気悪ぃ日に行ったべ。晴れでればだっきゃやだら明るくてご陽気だ山だんだして。
「人通りがほとんど無い」車で30〜40分かがるよんた山道、今時だぁ歩いで行ぐってな!?そのかわり車やバイクだの自転車だののツーリングの皆さんが、がんがん通っちぇあべさ。
「異様な雰囲気が漂って」硫黄の臭いだば漂って来るたって。へたて温泉湧いでらもの、あだりめだべ???
「蒸気が吹き上げ、熱く煮えたぎった湯がごぼごぼと湧いて」死火山化してきているとはいえ、やせでもかれでも温泉あるもの。有名な温泉地はたいがいそうだべさ。
「この世のものとも思えぬ風景」へばおめ死んでらのが!!??
(共通語訳省略)
たしかに「あの世とこの世をつなぐ場所」なんだろうから、そういうイメージを求めて恐山に行く人がいてもいいよ。でもそういうのが苦手な人にはね。
景色がきれい。むき出しの岩肌やごろごろ転がる石ころがきれい。青空を行く雲がきれい。咲いてる花が陽炎に揺れてきれい。カルデラだから霊場のぐるりを囲む山が湖に写ってきれい。山にかかるお日さまがきれい。湖の透明度が高くて白砂の水辺できれい。黒く見える程濃い緑の木がきれい。
それから「これを履いて上がって来さまい。」とでも言いたげな、湖を背にして揃えてあるわらじがちょっぴり哀しい。
そんな恐山がもうすぐ冬の眠りから覚めるよ。
私の実家があるむつ市小川町は、「恐山街道」の登り口にあるんだよ。つまり私は、恐山のふもとでおがったのさぁ。
失礼な。夏はそれなりに暑いわよっ。どう暑いかと言うと、例えば、
暑さのせいで線路が弛んじゃって列車がストップしちゃったとか、アスファルトが柔らかくなってタイヤや靴のかかとや山車の車がめり込んじゃったとか。どう、暑いでしょ。
特に今年は暑かった。だってさー、県内でも特にむつ市はさー、それも実家のある小川町はさー、昼間どんなに暑くても夜になればス〜〜〜ッと涼しくなるのが常だったのよね。昼間「暑い暑い」と言ってても、夜には「フロ入ろうか」て感じ。
なのに今年は「シャワーでいい」だったのよ。約4週間いたんだけど、一度もおフロに入らなかったもんね。
だって寝る時間になっても30度を下らないんだよ。宝塚市ではごく普通の事だけど、むつ市では特別な事なのさ。
それで困ったのはさ、宝塚市みたいに暑いところだと冷房は(ある程度)標準装備じゃない?ところがうちの実家みたいに「夜は涼しいから気持ちよく眠れる」ところは無いんだよ、冷房が。
で、今年みたいに暑くても来年も暑くなるとは誰も思わないから、今年ちょっとくらい暑いからといって「エアコンを買おう」なんて思わないんだよね。特にうちの実家の親みたいなタイプはさ。
でさ、子どもってよく「アセモ」を出すでしょ。いつもは「むつのおじいちゃんのとこに行けば、アセモ治るからねー。」って言ってたんだけど、今年はね。宝塚市で作ったアセモは一旦治りましたよ。でもその後新しいアセモができちゃった。それもそれまでのよりでかいやつ。いや、参ったね。これも「温暖化」のせい?
でもさ、これで毎年暑くなってくかっていうとそうでもないあたりがくせ者なんだよね。たぶん来年あたりは「冷夏」になるんじゃないかなー。今まで「2年続けて暑かった」年って、まず無いもんなー。それよりは「やいや、去年あったに暑かったのに、今年ぁこったに寒くてどうしたもんだべ。」ってパターンの方が多かったもんなー。
う〜〜〜ん、来年が心配ですなー。今から冷夏対策しとかないとダメですかなー。
いや、ほんとに地震はダメなんですよ。震度1でも「揺れてる」と脳より早く体が判断すれば、脈拍は早まり、血圧と体温は上昇し、血中のアドレナリン濃度はおそらく天井知らず。体中の神経が皮膚に集まるし、膝は笑うし、でもチーターよりも俊敏になってる、たぶん。最初からこうだったワケじゃないんですよ。ちっちゃいときに、それはあったんです。
私が幼稚園の年中組で、誕生日前だったから4歳の時の事。すでにむつ市から青森市に引っ越していたんだけど、その時は何かの事情でむつ市にいたワケです。風邪を引いたかぜんそくだったかで、恐山街道の入り口近くにあった佐々木小児科に、母と一つ下の妹と行ってたんだけどね。
聴診器をあててもらっている時に、佐々木先生と母が「ずんぶ長げな。」「ホントですね。」てな会話をしてたのよ。後から聞いたらそれは「初期微動(地震の本格的な揺れの前にある、小さな揺れ)が長いな。」ってことだったんだけど、そのときはまだ何も解ってなくてね。で、注射をしてもらうのにパンツ一丁という格好になって、看護婦さんのところに行ったそのとき。
注射の薬剤アンプルを入れる棚が、いきなり倒れてきたんだよ、物凄い音で。それにびっくりしてたら、今度は窓ガラスやガラスの欄間(って言うのかなあ?)が割れて、がしゃがしゃ降ってきたんだよね。何がなんなのか解らなくてただ立ちすくんでいたら、母が私と妹を両脇に抱え、私達の服とバッグをわしづかみにして外に飛び出したんだよ。その母の荒々しい感じが恐くて、妹と一緒に泣き出してしまってね。頭上から降ってくるガラスを避けながら外に出て地面に下ろされた時、世界中が揺れているのに気付いたんだよ。
病院前の車が1、2台停められるくらいのスペースで、母が大急ぎで私と妹に服を着せてくれた。見回すと他の患者さん達も、親にそうされていたよ。ゆっくりと揺れがおさまっていったけど、4歳の子どもの頭と体に「地震とはどういうものか」なんてことが焼き付いてしまった。服を着せられてる最中、地面の中から聞いた事もない音がしてくるのに気付いたよ。よくある「ゴゴゴゴ・・・・」っていうような地鳴りじゃなくて、「ド―――――ン!!!!」っていう、大砲みたいな音だった。あの音は、あれから30年以上たった今も忘れられない。余震がひどくて、しばらくは服を着たまま寝てた。余震がある度に飛び起きて、父の首根っこにしがみついてた・・・。
1968(昭和43)年、5月16日、午前9時45分、震度5、マグニチュード7、8。これが私が体験した「十勝沖地震」です。「十勝」って北海道の地名がついてるけど、実際に大きな被害が出たのは、青森県の南部(下北含む)地方だったと記憶してます(もし考え違いだったらごめんなさい)。時間が時間だったので、学校の裏山が崩れて校舎ごと生き埋めになり、犠牲になった児童生徒がたくさんいました。道路、鉄道、ライフラインもずたずたに寸断されました。南部地方では、「防災の日」は、この5月16日なんです。大規模な避難訓練や防災訓練が行われます。マグニチュードは関東大震災に匹敵するものです。たまたま海洋性の地震だった事、北国特有の建築様式のおかげで耐震性が高かったこと、大きな火災が起きなかった事、そしておそらく人口密度の低さで関東大震災、阪神大震災のような何千人、何万人という被害者を出さずにすんだのだと思います。
宝塚市に来てあの阪神大震災にあうわけですが、阪神大震災とくらべても、十勝沖地震が震度5というのはあまりに低い数値だと思えてならないんですよ。震度は人の体感と建物の倒壊率なんかで決まるそうなんですが、それなら十勝沖地震だって震度6以上の地震だったと、私は思っています。建物の倒壊率は低かったかもしれないけど、体感的なこととか、道路や鉄道の被害とか考えるとね。
この十勝沖地震からだよ、私が地震を怖がるようになったのは・・・。
日本には名前を言っただけで、「ああ、あれ!!」とすぐに思い浮かぶメジャーな煎餅がある。
「草加煎餅」「瓦煎餅」なんかは、たいがいの人が知ってるよね。
さて、青森県。「煎餅」と言ったら「南部煎餅」を指す。「せんべ、食うが。」と言って出てくるのは、まず間違いなくこの「南部煎餅」だ。
南部煎餅のお店、「八戸屋(はちのへや)」さんによれば、
「建徳の昔、長慶天皇御遷幸の時、日が暮れても夕食の用意も出来ずお困りになった。その時一行中に赤松某が兵の兜を鍋として、そば粉を練って火にかけ胡麻を掃りかけて奉った処其の風味を非常にお歓びになり其の後も時折赤松に命じてその独特の風味を愛されました。」とのこと(煎餅の袋に書いてある「南部煎餅の由来」から)。
今はそば粉ではなく、小麦粉がメインになっている。胡麻をまぜ込んだ「胡麻煎餅」、ピーナッツをまぜ込んだ「豆煎餅」、胡麻煎餅を油で揚げた「揚げ煎餅」、水飴を二枚の胡麻煎餅でサンドした「飴煎餅」、バターたっぷりの「バター煎餅」などなど、種類もいっぱい。ちっちぇわらし(訳、小さい子ども)から歯の無いジ様バ様まで、この煎餅を食べる(しゃぶってふやけたら飲み込むの、年寄りは)。
さて、南部地方には「煎餅汁」というのがある。正しい発音は「せんべ汁」(”じ”にアクセント)となる。胡麻やピーナッツなどの「具」が何も入っていない「白煎餅(しろせんべい)」を手でぱきぱき割って、とり肉、ごぼう、人参、大根、糸こんにゃく、長ねぎなどが入った醤油仕立ての鍋に入れて食べる。
小学4年生の時津軽から南部に引っ越した私は数々のカルチャーショックを受けたが、この「せんべ汁」もその一つだった。「お煎餅を鍋に入れるぅ〜!?」、どんな味がするのか恐かった。しかも南部では、キャンプだの炊事遠足だの人が集まるイベントがあるとこれを作る。山形の芋煮みたいに。そしてとうとう私もそれを食べる日がやってきた。
「うまい!!!」
びっくりした。入れたての煎餅のじなじな硬い感じ、時間が経ってちょっとふやけた煎餅のふにゃふにゃした感じ、どれも「め!(訳、美味しい)」。」そして私は「せんべ汁」の虜になった。
青森県の南部地方に行かれる方。「何食べてえすか?」と聞かれたら、迷わず「煎餅汁」と言おう。これからの寒い季節、やみつきになるよ、これは。
青森県出身だというと、「スキー得意でしょ!」とよく決めつけられちゃうんだよ〜。
「それが、できないんだよねー。」というと、「ええ〜?ホントに青森県民なの〜?」って目で見られる事がある。
じゃあ何か?沖縄の人はみんな泳げて、京都の人はみんな舞妓さんで、大阪の人はみんな漫才師で、北海道の人はみんなムツゴロウだとでも言うのか?
私が雪深い青森市に住んでいたのは4歳から10歳まで。その頃は「ミニスキー」ってモンで遊んでいた。「ミニスキー」とはその名のとおり長さ30〜40センチメートルくらいのプラスチックのスキー。長靴を履いた上からぺら〜としたベルトで留めて履くようになってて、色は赤いの、青いの、緑の、ピンクの、これくらいはあったかな?
ミニスキーの滑り方や滑る姿は、どっちかというとスケートを滑るのに似てる。スキーみたいにストックつかったりしないし(たまに使ってるやつもいた)。スケートと違うトコといえば、スピンができないことくらいかな?普通の道路をミニスキーで滑って広場まで行って、広場で遊んだ後はまたミニスキーで帰る。3時間も4時間もミニスキーを履きっぱなしで遊んでた・・・。
ミニスキーはね、折れやすいのが欠点だった。物によっては、おろしたてなのに折れる事もあったし。ミニスキー、今はあんまり見ないんだよね。売ってないのかな?
ひとくちに「青森県」と言っても、津軽(つがる)と南部(なんぶ)に別れ、南部もさらに上北(かみきた)を含む県南部と下北(しもきた)に別れるのだ。津軽と南部は明治時代に入って廃藩置県になるまでは全く別の国であり、治める殿様も違った(はずだ)。
しかも下北地方にいたっては、県南の人たちからは「え、南部のつもりだのすか!?ちょっと厚かましいんでね〜のすか?」的なとられかたをしてきたわけさ。
そんなわけで、津軽、南部、下北の3つの地域で成り立ってると思ってもらえればいいんだよね(たぶん)。
なんでこんな話を最初にするかと言うと、この三地域、方言から天気から習慣からまるで違うんだよね。方言は使う単語やイントネーションが全く違うし、「青森は雪国」と思ってるそこのあなた、県南部はちょっとしか降らないし、降ってもあんまり積もらない、ってな具合。
この三地域の生活を全て体験しましたぞ。つっても子どもの時ね。チチが転勤族だったから。いや、もう、それはそれは思い出に溢れておりますよ〜〜〜〜〜。
ああ、今日も津軽から南部、下北から津軽へと引っ越ししてる家族がいるんじゃありますまいか。がんばれー、がんばれー。