
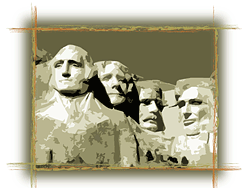

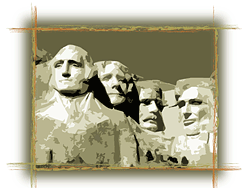
![]() ←ここをクリックする
←ここをクリックする
「本(もと)を務(つと)む、木立ちて道(みち)生ず。」
「論語」の中にある名言である。
人間はその毎日の生活において、さまざまな問題に当面するが、その解決のためには、そのことにかかわる根本問題を把握することに努力することが大切である。
根本となるもの、ものごとの本質さえ確かに把握することができれば、あとは自然に、解決のための方法が分かるということである。この場合の「道」とは方法ということである。
1.この名言に照らして日本の教育の本質を見極めたい。学校には、教授の客体的であり学習の主体である個々の子供が集団として存在し、個々の子供の内的な意欲とその能力に支えられた「教授・学習活動」があるが、それが、教育の場所としての学校における教育の本質であることを忘れてはならない。そのことを念頭において、各学校がそれぞれに編成する教育課程において不易な内容とされる次のことを大切にすることが、特に肝要である。
○自ら学ぶ意欲・態度・能力を育てること。(自己教育力)
○社会の変化に主体的に対応できる能力を育てること。
○基礎的・基本な内容を重視しその内容を見極め確かに身に付けるようにすること。
○個性を生かす教育を充実するすること。
○心豊かな児童・生徒を育てること。
2.教育実践は、具体的には、各教科、道徳、特別活動の授業であるがその授業は、教師のはたらきかけのもとに、子供を中心にして、教師と子供が一体となり、教材を媒体に相互に働きかけながら、その授業の目標達成を図る共同作業でありチームワークであることを認識したい。
3.どの子供も自己課題を持って意欲的に学ぶような授業は、要するに、一人ひとりの子供が、それぞれに考え、主体的にかつ協力的に学習問題を追究して、必要な知識・技能を理解し見方考え方を身につけることのできる授業である。


