



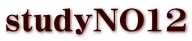 ←ここをクリックするとNO7へ
←ここをクリックするとNO7へ 「言うべき時を知る人は、また黙すべき時を知る
ギリシャの名高い数学者、物理学者・アルキメデスの残したことばである。
人はただ黙っているのがよいのではない。言うべきときはどんなときであるか、
進んで言わなければならないときはどんなときであるかをわきまえて、そのときには、はっきり述べなければならない。
しかし、また、どんなときが黙すべきときであるかをわきまえて、そのときには、一言も言わない態度をべきである。それが、真の知恵者の道であるというように、このことばを受け止めたい。
アルキメデスとほぼ同時代に、東洋において、老子が、「知る者が言わず、言う者は知らず」のことばを残している。それは、知る者は、ことば少なく要点を簡潔に表現するが、知恵の少ない者は、一般にことばの多いわりに要点が明確でないという意味である。
これらの名言を伝える意味を現代的に考察すると「礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動ができるようになる」ということである。
学校における教育は、具体的には、各教科等領域の授業あるが、その授業の過程には授業効果をあげるために以前からグループ学習での「話し合い活動」という学習活動が取り上げられてきた。しかし、途中で学習の効果が上がらないということから教師対児童・生徒の一斉授業が風靡した。
しかし、近年になって、「学ぶ共同体」としてグループでの「学習活動」が取り上げられ、授業の目標達成の効果的な方法の一つとして盛んに授業研究されるようになってきている。ただ、大切なことは、「どの子も学習に積極的に参加し、数多くの主体的な意見を出し、その全てがクラスのみんなによって尊重されるようなされるような、学級の雰囲気になっていることが必要である」
そのような雰囲気になるためには、個々の子供の考え方等を深く見極めることが必要である。具体的には数多くの個々の子どもたちの意見を分析分類し、整理することによって、そして、その整理された多様な意見について、それぞれの意見の根拠とともに吟味検討して、その中から、よりすぐれた意見を見つけ出すことであり、つくり出すことが大切である。


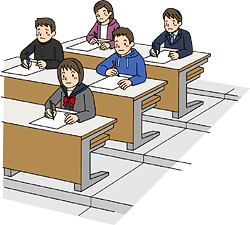
このようにして進める学習活動の過程においては、子どもは、人の意見に対して、それを注意しながら集中して聞き、それによって自分の考えを確かめたり、また、臆せず進んで自分の考えを発表したり、質問したりすることを通して自分の考えを自己評価したりする判断力が身につくことができる。
要するに、それは、「学ぶ共同体」(グループや全体)学習の中で積極的に自分をためしてみようとする子どもの主体的な学習態度が、より向上するようになると言える。