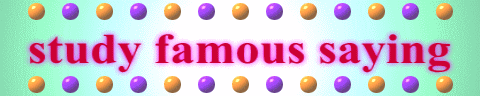

「勝は、己(おねれ)に勝より大なるはなし。」
大哲学者プラトン(ギリシャ)の言葉である。自分の中に起こる欲望や邪念などを抑えるための、自分との闘いに勝つことは、ほかの人との議論や争いに勝つことなど、いろいろな勝利の中で最大のものであるという意味としてとらえることのできるものである。
このことばの持つ現代意味は「人間として正しく生きるためには人間のもつ弱さの克服に努めること、正しいと考えることを、勇気をもってねばり強くやり通すことが大切である」と受け止められる。要するに、このプラトンのことばは、「人間が一面においてもつ弱さ醜さを克服することがたいへんむずかしく困難なことで、その闘いに勝つことは、その人にとって色々な勝利の中で最大のものである」としてそのことのもつ、人間の生き方における意味を、大きく取り上げて、価値づけている。人間は、おそらく、誰もが、自分のもつ人間としての弱さや醜さを指摘されたり、そのことを認めなければならないような立場に立たされること、好まないだろう。
そのためには、何よりも、自分を、自分で支配する力、コントロールできる力、すなわち、自己統御の力を強くすることである
その自己統御の力を育てるためには、人間にとって最も大切な「主体的な立場」の確立を図ることが大切であるが、そのためにはその「主体的な立場」を支える、原理・法則を、質的に高める努力を続けることが肝要となる。
人が、謙虚に他人に意見を求めたりするのは、主体的な立場を確立するためであり、そのことによって、自己を支配できる、自己統御の力を強くするためのものである。
自己統御に関連するものとして、哲学者カント(ドイツ)はその道徳的自由論の中で「人間の真の自由ついて、それは理性に基づく道徳法則に自発的に従って、感覚的欲望にうち勝つことによって確立できるものである」としている。
要するに、カントの自由は、理性に基づく自律性であるから、外的な拘束から解放されるというような消極的な自由ではない。それは主体的な立場において行おうとするものを完遂しようとする積極的な自由といえるものである。
この「自由」に関連して、主体的な生き方にかかわる大事な事柄に、「規律」の問題がある。「規律」には、人の行為の基準とか、あるいは一定の秩序、きまりといった意味があるが、それは、人間にとって社会生活をスムーズに営むために、なくてはならない重要な働きをするものである。学校規律に関する指導においては、学校にある規則について、その必要性の理解を深めることに重点をおいて進めることが大切である。
「何のために、そのきまりがあるのか」について十分に納得することができれば、おそらく子供は、その規則を守ろうとする態度で実践への努力をするであろうし、そのことに対する教師の指導に対しても、率直に応ずるにちがいない。