過渡応答(矩形波)
過渡応答とは、例えば、ゼロから急に1になるような状態の変化なのですが、アンプの場合、1kHzの矩形波を入力しておいて、出力される波形でその応答性能を論ずる事が多いと思います。NFBをかけたパワーアンプの場合、負荷抵抗として、8Ωの抵抗をつないで、矩形波を加え、負荷抵抗に並列にコンデンサを入れて、矩形波の立ち上がり部分の変化をみて、リンギングが生じなければ、安定度の高いアンプとして、合格であり、大きなリンギングが生じたり、ひどい時には、寄生振動を起こして、AMラジオに妨害電波を出してしまう失敗アンプとしたりという判定に利用します。
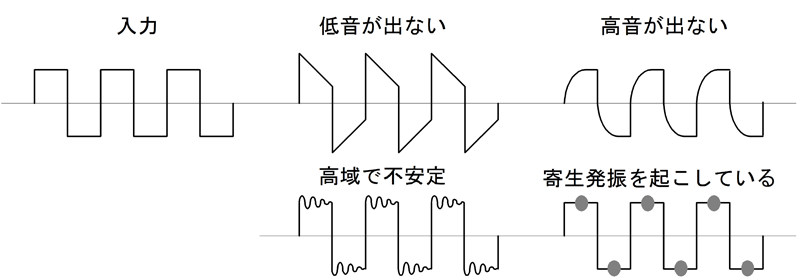
アナログ時代の過渡応答は、これが全てであったのが、デジタル時代では少し様子が変わりました。コンピュータや、CDからの矩形波は、上図の高域で不安定という波形と良く似た波形になります。違いは、無限大のサンプリング周波数が使えず、CDの44.1kHzのように制限されて、本来、真四角であるべき波形が、発振を起こしたような波形になってしまいます。こうした音源を使用して波形による過渡応答診断を行うと、どこがリンギングで、どこが正常部分なのか判別できず不都合です。
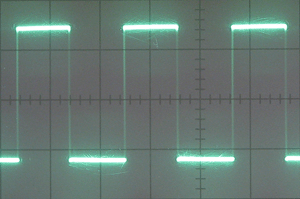 従来のアナログ発振器による矩形波
従来のアナログ発振器による矩形波 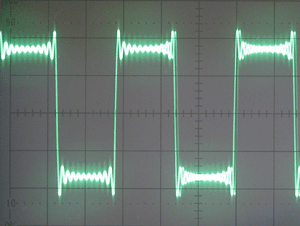 CDなどのデジタル音源による矩形波
CDなどのデジタル音源による矩形波そこで、スピーカーとアンプの関係を調べるのに、直流的な1とゼロの応答ではなく、交流的な1とゼロの応答を調べるという観点で、正弦波を途中で止めるトーンバースト波に注目してみました。
過渡応答(トーンバースト波)
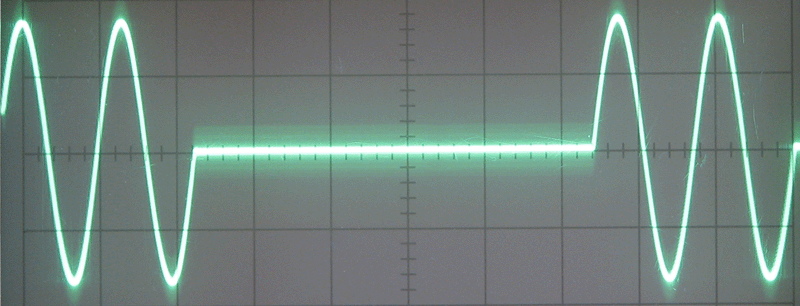 トーンバースト波
トーンバースト波上の写真は、1kHzON周期2、OFF周期4というトーンバースト波です。1kHzの正弦波が2波続いた後で、一旦ゼロになり、再び1kHzが出力されるという過渡現象が含まれます。正弦波だけを一定時間流しておいて測定する高調波歪率は、アンプの性能の尺度としてよく利用されますが、低歪=高音質でないのは、周知の事実です。アンプに単純に純抵抗をつなぎ、1kHz以外の成分の発生具合を%で表すのですが、無帰還のアンプなら、そこそこに歪率の個性が出てきますが、OPアンプ主体の音響機器であれば、この歪みは、SN測定と同義になるほど、ノイズに依存した数値となり、性能比較用途には何の意味も持ちません。しかし、ノイズに依存した歪率となるのは、負荷が純抵抗の場合だけであり、スピーカーのように、磁石とコイルを持ったものは、逆起電力が発生するので、単純でなくなります。
スピーカーを負荷とした場合のアンプの出力
本来アンプは、出力端と入力を比較して、入力に相似な波形を出力しようとします。理想的にはそうであっても、アンプからスピーカーへは、ケーブルの抵抗が僅かに加わり、アンプ内部でもNFBループ外にあるミューティングリレーの接点抵抗、内部配線抵抗が加わります。普通この抵抗値は、1Ω以下と小さいので、抵抗を無視して考えられています。ところが、抵抗値がゼロに近いだけで、抵抗値は有限値をとります。それと、アンプ側NFBループ端で、完全に入力と同一であっても、スピーカーには、磁石とコイルが有り、それが発電機となりますので、スピーカーの端子には、アンプからの出力以外にスピーカーで発電した電力が加わり、アンプの入力波形とは異なった電圧が発生します。この電力は、アンプの内部抵抗により、アンプで消費されて、スピーカー端子に表れないのが、理論ではありますが、実際には、程度の差があっても、スピーカー端子に表れてしまいます。以下では、理想に近い状態を直列抵抗無しとし、現実よりも、少し辛めな結果が出るように、スピーカーインピーダンスと同じぐらいの8Ωという直流抵抗を入れて波形の比較を行いました。直列抵抗の存在により、スピーカーで発電される電力波形がよく見えるようになります。
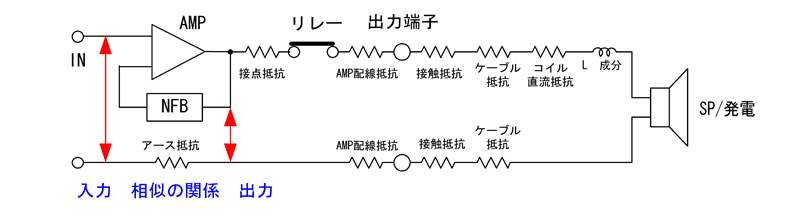
以下の検証で使う、8Ωという直流抵抗値は、この4S6を200m以上使用しなければならないような数値ですが、極端にしておいた方が現象が観測しやすいので、この抵抗値をアンプとスピーカーの間に入れて差を比べると以下のようになります。
下はDEONのAVアンプ AVC1620から4kHzトーンバースト波をスピーカーに加えた時のスピーカー端子電圧で、振幅が大きい方がアンプ直結、小さい方が8Ωが直列に入った場合で、抵抗がある場合、正弦波部分が終わってゼロになるべき部分で、ツノのように、逆起電力大きく表れています。右は実験に使用したスピーカーで、 DAITO VOICE PN-15 8Ω 直流抵抗 6.33Ω 口径16cm ダブルコーン型 です。
先にも述べたとおり直列抵抗が入ると、聴感でも余計なジー音が増えて、肝心の4kHzの音が小さくなります。
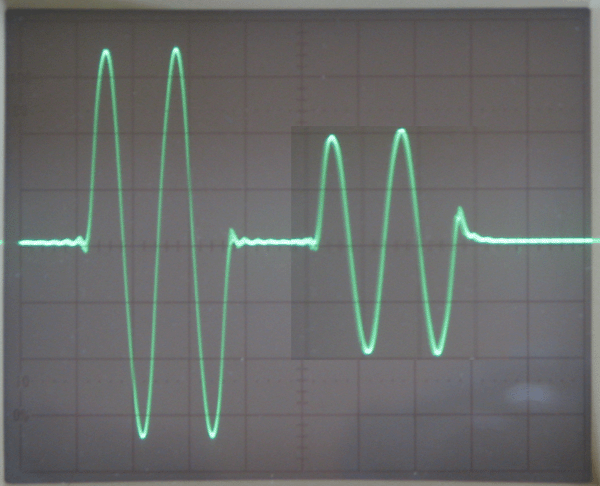

このスピーカーのマグネットは一般設備用スピーカーですので、音響用より小さく弱いと思いますが、いわゆる普通のスピーカーです。上記の物が、建築物実装時は、スプリングにパネルを引っかけて天井裏に置かれています。実験では、写真のようにマグネットを床に置いた状態で、スピーカーの入力端子に発生する電圧を見ています。
下は、100Hzの場合ですが、右側は、直流抵抗ゼロですが、コーン紙の振動が収まらず、まだ動こうとするのを半波ぐらいで抑え込んでいるのが、よくわかります。右側は8Ωの直流抵抗が入った状態ですが、2周期ぐらいふらついているのが判ります。又、次の100Hzの1波目の電圧のかかり具合も小さくなっています。
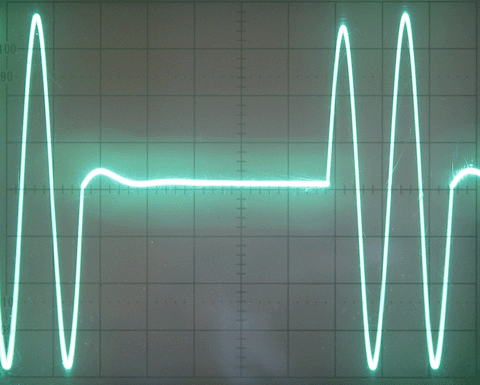
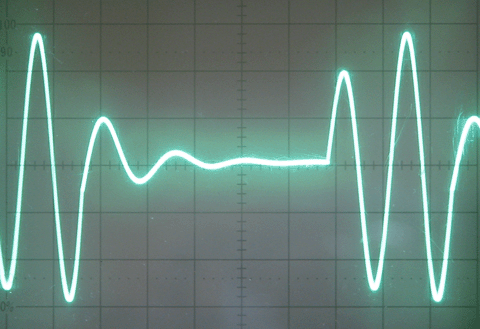
スピーカー直結のマルチアンプ駆動では、制動がしっかり効いているし、ネットワーク経由では、ぼわっとした低音になるのは、この波形からも判ります。ところが、スピーカーの代わりに、純抵抗をつなぐと、直列抵抗が有っても波形変化せず、純粋なトーンバースト波となります。波形写真は、まったくきれいなトーンバースト波ですので、省略します。同様にコンデンサをつないでも何も起きませんし、コイルでも同じです。すなわち、抵抗、コンデンサ、コイルとい受動素子がアンプの負荷となった場合、途中の抵抗が0〜8Ωほど有っても波形の乱れは生じず、アンプ本来の役割である筈の、肝心の電磁スピーカーを接続した途端、アンプから加わる波形が乱れるという事です。コンデンサスピーカーでは、そのような現象は起きません。
結論 スピーカーは、能動素子(アクティブ素子)なので、自身で発電を行い、勝手に音を出します。
実験 SPケーブルのインダクタンスは無視できるのか 実験結果:100Hzでは無視できるが、9kHzでは影響がある
以下の回路にて、実験を行いました。
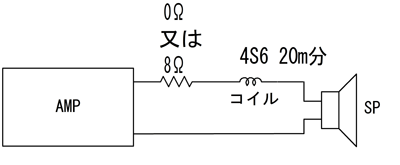 4S6 20m分の直流抵抗は片線で0.31Ω、往復で、0.61Ω有り、インダクタンスは、8の字巻きして、片線時15μH/mです。
4S6 20m分の直流抵抗は片線で0.31Ω、往復で、0.61Ω有り、インダクタンスは、8の字巻きして、片線時15μH/mです。直列に8Ωの抵抗がある場合 100Hz
SPケーブル4S6を20m使用し、ケーブルが途中に入った時の変化ですが、左が片線だけ使用して0.3mHぐらいのインダクタンスが有る場合で、右側がケーブルを往復で使用して、インダクタンスをキャンセルした状態の波形です。


100Hz波形はほとんど同じで、20m程度のスピーカーケーブルのインダクタンス分が、波形に及ぼす影響は有りませんでした。
アンプ直結(抵抗なし) 100Hz
下の左側は直列抵抗は無し直結し、同じく途中に4S6 20mで片線使用して、0.3mHぐらいのインダクタンスが有る場合で、右側が、ケーブル往復使用して、インダクタンスキャンセルした状態です。
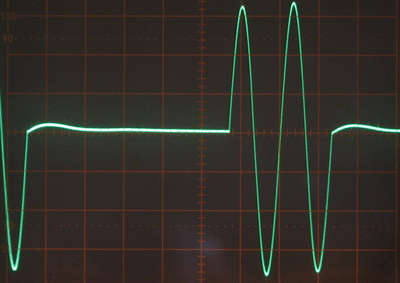

100Hzでの結論:アンプまで、抵抗が有っても、無くても、インダクタンス分の影響は有りませんでした。
次は同じ条件で、周波数を9kHzに上げてみます。
直列抵抗8Ωがある場合 9kHz
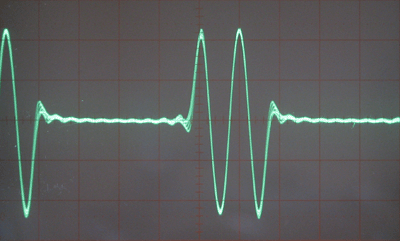
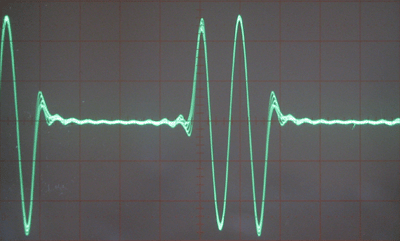
SPケーブル片線分のインダクタンスが入ると逆起電力のツノが小さくなりますが、9kHzの振幅も小さくなり、音量低下します。右側、SPケーブル往復でインダクタンスがキャンセルされた場合は、逆起電力が大きくなりますが、9kHzの振幅も大きくなっています。
アンプ直結(抵抗なし) 9kHz
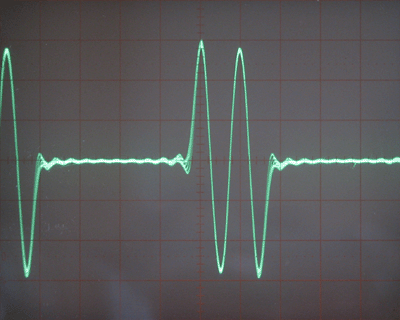
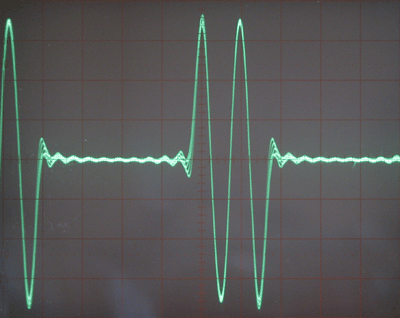
SPケーブル片線分のインダクタンスが入った場合、上記の4ケース中では、逆起電力が最小です。しかし、9kHzの振幅はインダクタンスが無い場合より小さくなっています。右側インダクタンスキャンセルした場合では、逆起電力は少し大きくなりますが、9kHzの振幅は上記4ケース中最大です。9kHzのような高い周波数の場合は、スピーカー自身のインダクタンスと、電線のインダクタンスが打ち消し方向に働き、逆起電力を軽減するようです。しかし、ケーブルインダクタンスにより電圧が分圧されて、音量が小さくなります。
ケーブルインダクタンスは、直流抵抗とは違い、スピーカーの逆起電力に作用しないが、高域でインピーダンスが上昇するので、ボリュームが効いたように分圧され、入力電力そのものが高域で低下します。
低音域のふらついている部分はどういった周波数なのか
波形観測により、ほぼ76Hzと推定しました。左が76Hzで、右がその2倍の152Hzです。正弦波が倍の周波数になっても、ふらつき部分の周波数変化は無いようです。
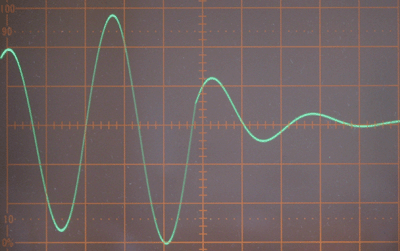 76Hz
76Hz 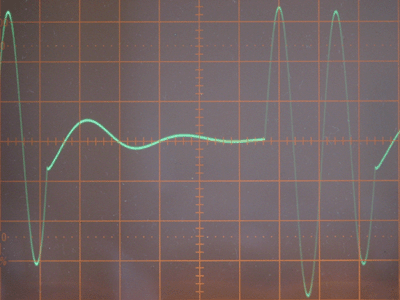 152Hz
152Hz下は、この実験で使用した DAITO VOICE PN-15 8Ωのボイスコイルインピーダンス特性で、最低共振周波数は、81.8Hzです。76Hzは、この最低共振周波数より低いのですが、極めて近い周波数です。
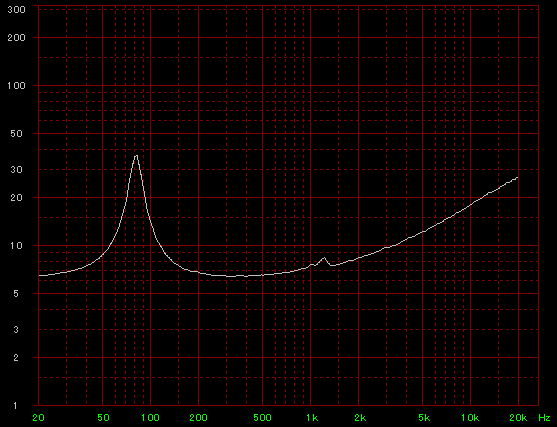
こちらは、有名なBOSEのユニットで、直流抵抗1.33Ω 公称インピーダンス1.6Ω 最低共振周波数150Hzの特性で、左が150Hz、右が300Hzの場合で、PN-15と同じ傾向となります。
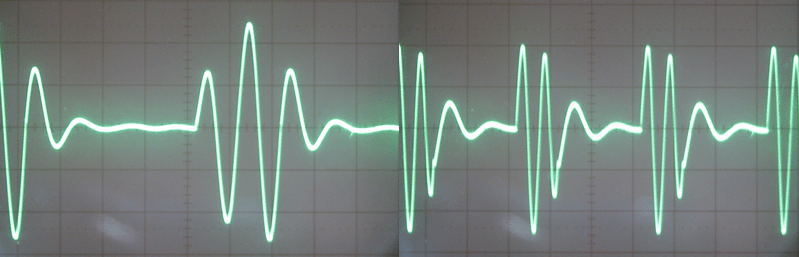
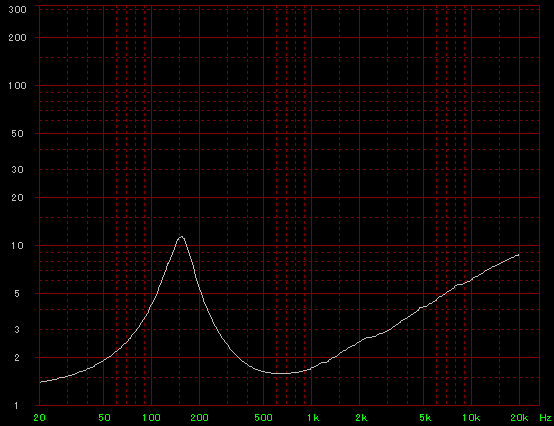

どうやらこれが、しまりの無い低音の正体かも知れません。入力を取り去っても、最低共振周波数付近で振動が継続し、ぼわっとした低音で、しかも、箱鳴りのように同じような周波数で鳴り、ベースの音階がはっきりしなくなるようです。一方、高音域は、すっきりしない音で、雑音混じりに聞こえるはずです。アンプ直結で鳴らした場合、これらの雑音は著しく軽減されますので、測定器で測るような歪み数値に関係しない、別の次元の高品質の音が再生されます。
アンプ直結と、直列抵抗が大きい場合の周波数ごとの比較
マイクで収音した波形も所々で掲載しておきました。SP端子電圧と実際の音波がほとんど同じであることがこれで解ります。
31.5Hz 以下左側 アンプ直結 右側 8Ω直列抵抗有り
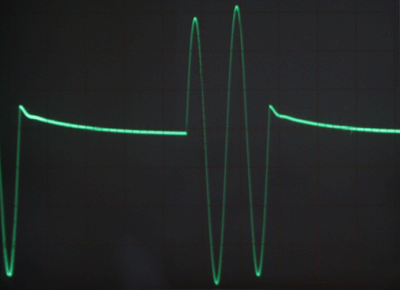
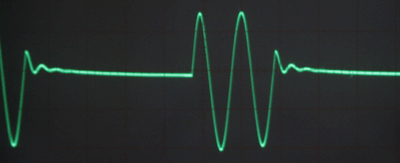
40Hz
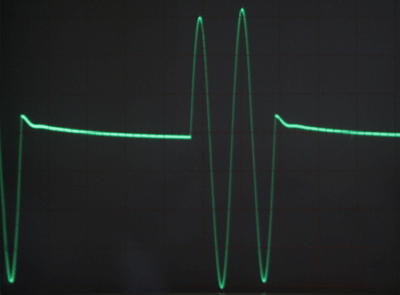
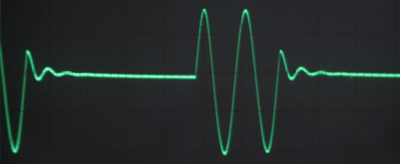
63Hz
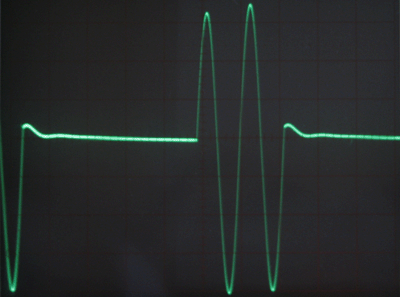
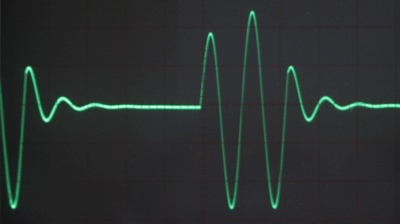
63Hzでのマイクによる収音波形 スピーカー端子電圧波形とよく一致しています。
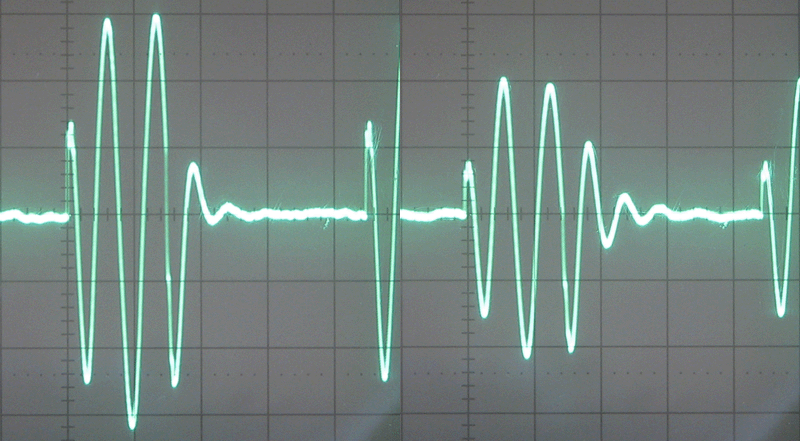
80Hz 最低共振周波数付近ですが、直列抵抗があってもインピーダンス上昇で電圧が高くなり、低音のピークができるようです。
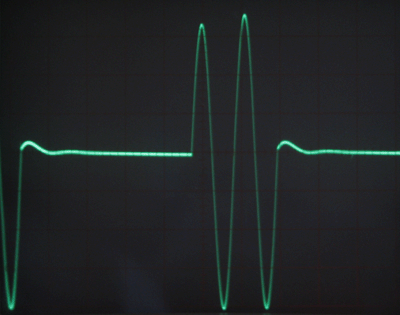
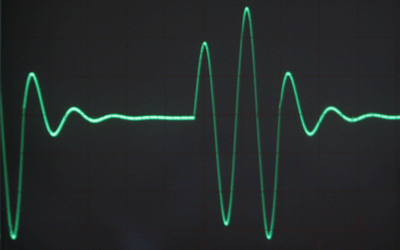
80Hz マイク収音波形 63Hzと同じような傾向です。
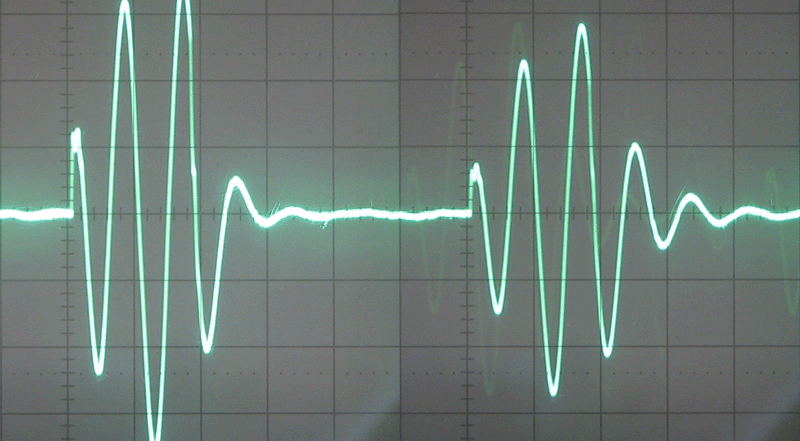
125Hz
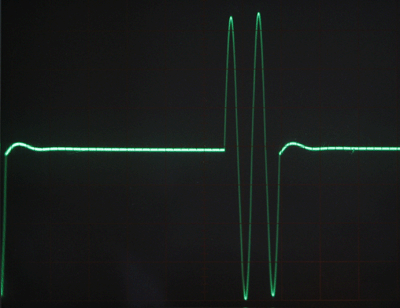

125Hz マイク収音波形 右側直列抵抗有りでは、主音より、余計な付属音がはっきりと判ります。
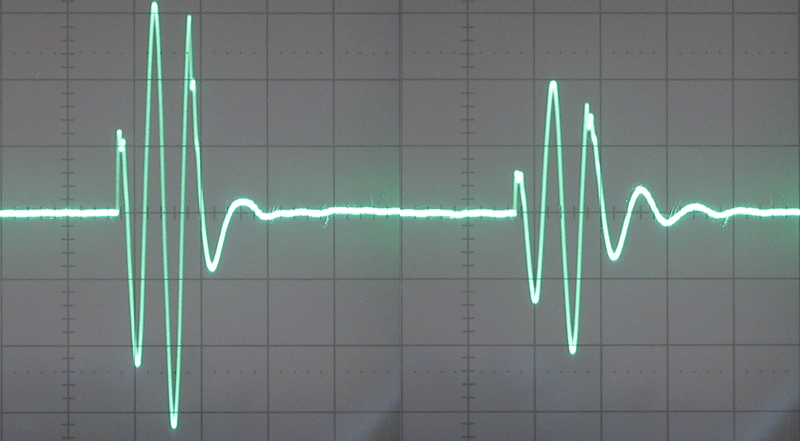
250Hz
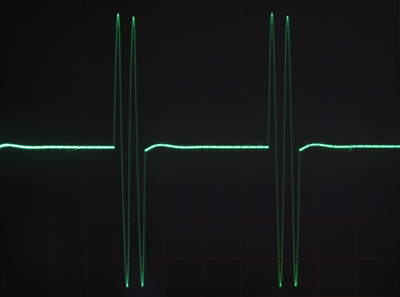
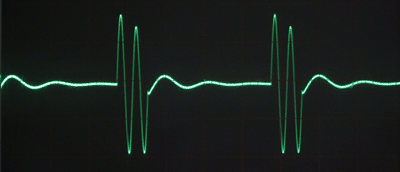
250Hz マイク収音波形 直列抵抗が有る場合は、主音だけが小さくなり、付属音だけが、同じレベルというように見えます。
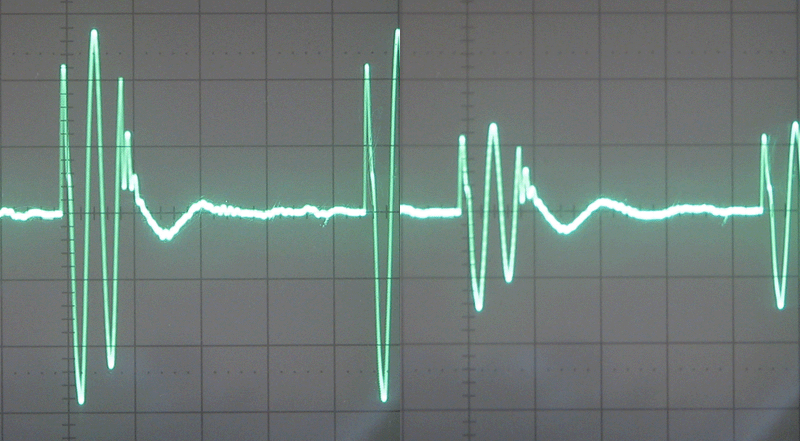
500Hz 右側直列抵抗8Ωがある場合の、逆起電力によるツノが見え始めます。
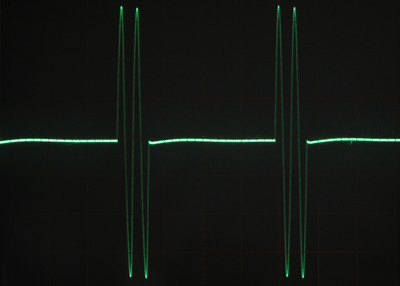
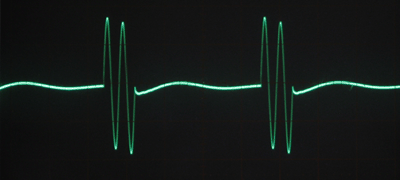
500Hz マイク収音波形 直列抵抗が有ると、250Hzと同様に主音だけレベルが下がり、付属音だけそのままのレベルです。
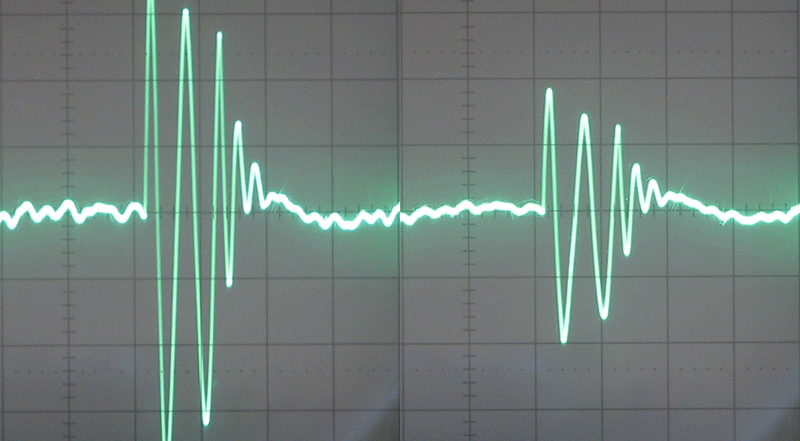
1kHz
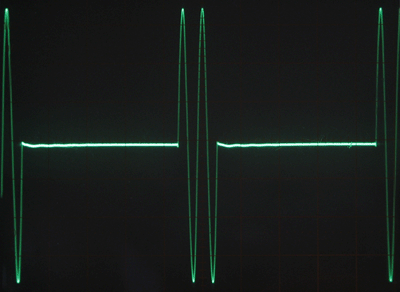

1kHz マイク収音波形 直列抵抗有りでは、レベル低下は相変わらず有りますが、付属音の割合はそれほど悪くは見えません。
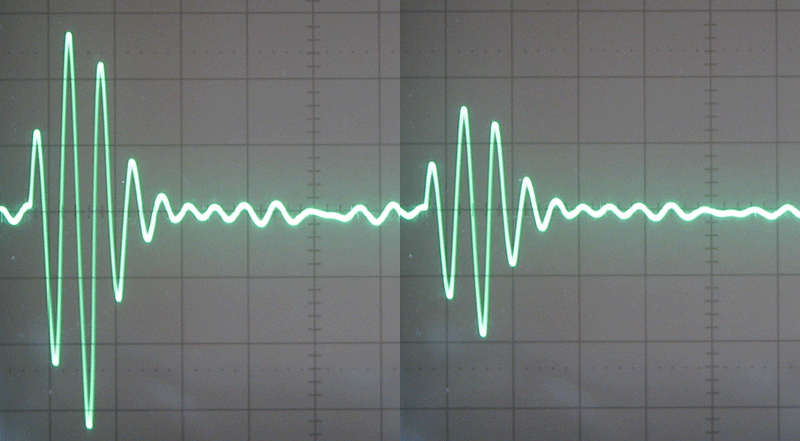
5kHz 逆起電力によるツノはかなりはっきりしてきます。それと、ボイスコイルインピーダンス上昇にともなって、直列抵抗があっても、分圧される電圧が高くなり、逆起電力も大きくなっています。

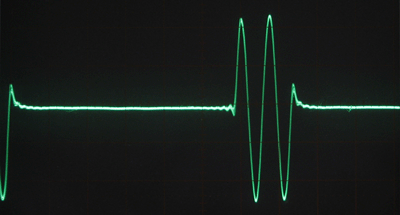
5kHz マイク収音波形 付属音のジーという音は、波形でははっきりしませんが聴感では、直列抵抗有りの右側の方が大きく感じられます。又、波形の立ち上がりにも差がでています。
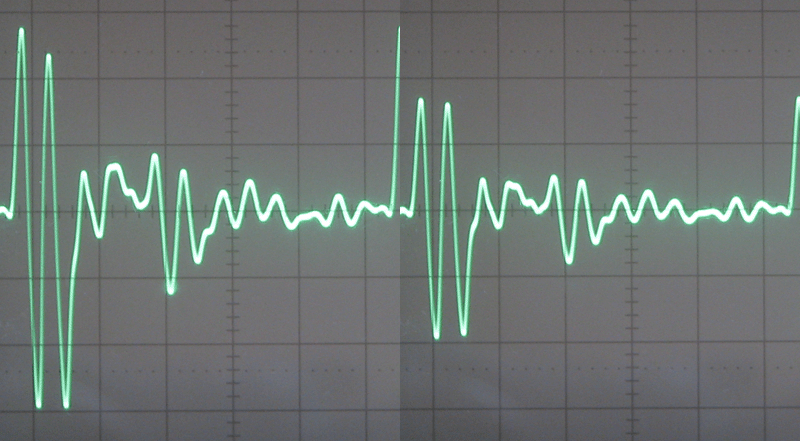
9kHz
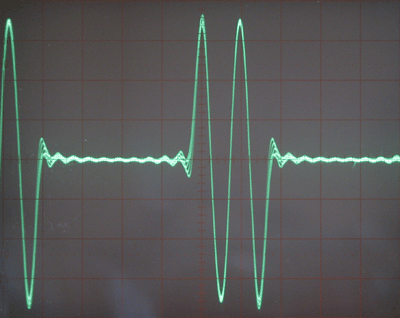
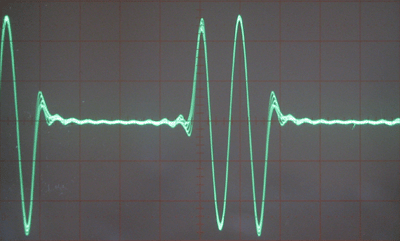
9kHz マイク収音波形 5kHzと同じような傾向ですが、左側アンプ直結の方が立ち上がりが良くなっています。
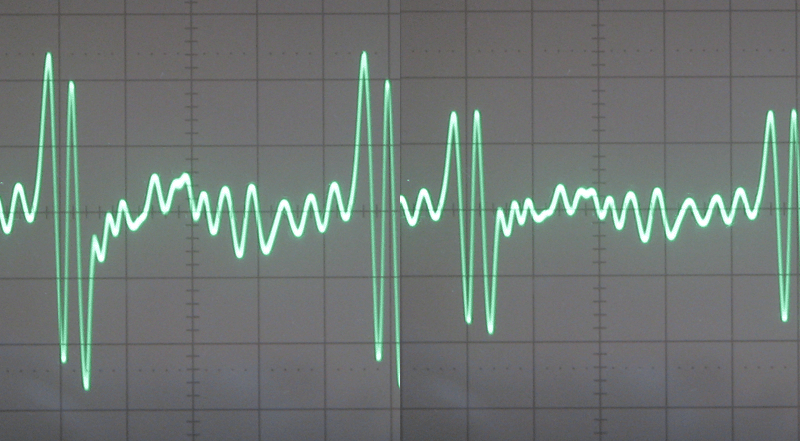
ヘッドホンの場合は?
ヘッドホンも構造的には、スピーカーと同じで、コイルと磁石ですので、同じ現象が起きます。
SONY MDR−CD900ST 周波数−インピーダンス特性
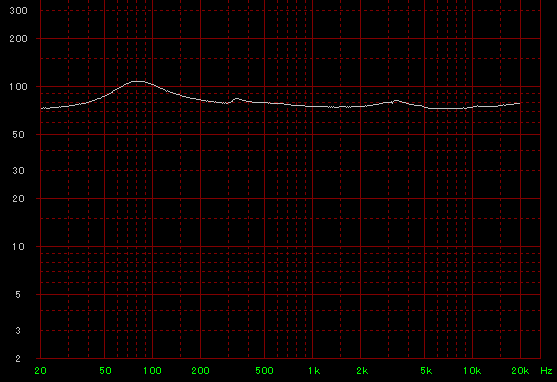

インピーダンスは、1kHzでは75Ωです。これは、平均的なスピーカーの10倍ですので、直列抵抗の影響は、1/10に下がります。USBインターフェースUA-5のヘッドホン端子では、逆起電力の影響は非常に少ないものとなっています。又、直結と8Ωの比較では、ほとんど変わりがありませんでした。ただし、100Ωの直列抵抗をつなげるとスピーカーと同様に逆起電力が表れてきます。ステレオアンプの場合330Ωぐらいが出力電力減少用として入っていますので、もっと悪くなります。ということは、直列抵抗を介さず、微少出力アンプで、定電圧駆動すると逆起電力が全て吸収されますので、音質向上が期待できます。こういった製品として、ヘッドホンアンプが有りますが、ICによるボルテージフォロアにトランジスタバッファ出力段を加えて出力しています。CDプレーヤーにおまけのように付いているヘッドホン端子でも、場合によっては、高級ステレオアンプよりも良い音でヘッドホンを鳴らすことができる可能性があります。
以上のトーンバースト波のように急激に音が無くなる音楽はないものの、磁石とコイルで構成するスピーカーから低音域では、しまりの無い低音や、ジー音で汚染された高音が発生する可能性を証明しています。マルチ駆動スピーカと、LCネットワークスピーカーの音の違いは、ホール音響の場合特に顕著で、判別しやすいものです。オーディオマニアでは、この違いに接する機会が無いとはいえ、アンプまでできるだけ低い抵抗で接続する重要性がこれで理解できると思います。
戻る