ここでは、ホーンスピーカーの特性にふれてみることにします。冒頭で紹介した伊藤毅著「音響工学原論」7.4.3動電型ホーンスピーカーについて、お読みになる方は少なそうですので、要約すると以下の図のようになります。
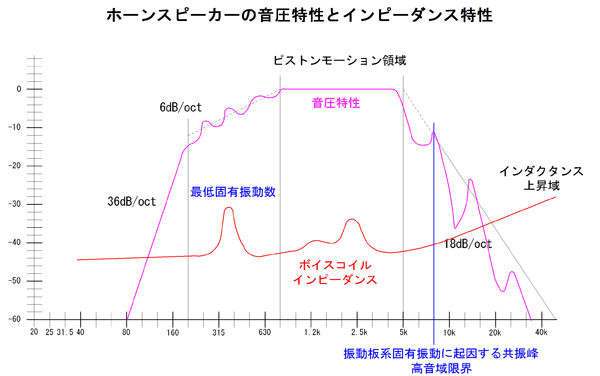
低域側 6dB/octで音圧が変動しているのが、ホーンが十分に長くない事によって、開口端で反射を起こしホーン内で共振を起こした場合に生じる部分だそうです。
TOA 380SE 定指向性 MIDホーン 高域でのインダクタンス上昇が7kHz付近からと、他機種より早めに起きています。
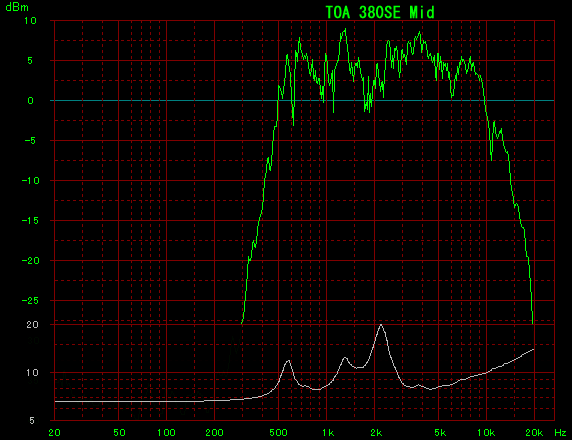
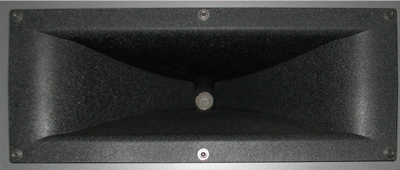
クリプシュ ドライバ K-53-K ホーン K-701 古い 3WAYスピーカーのミッドで使用されていた、割と小柄なホーンスピーカーです。260(W)x112(H)x280(D)でありながらカットオフ周波数 600Hzです。
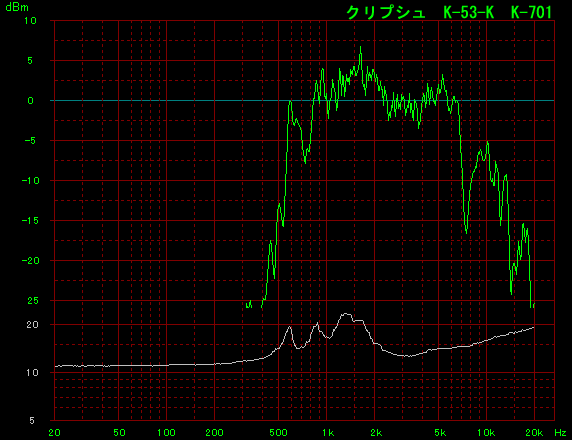
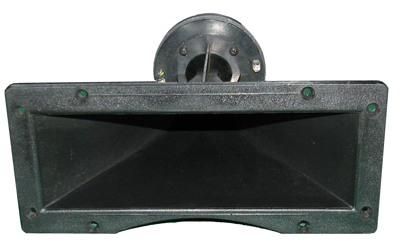
ONKYO HM-450A 拡散ホーン カットオフ周波数と比較して小型のホーンなので、低音側の6dB/oct変動があります。高域の共振峰もはっきりしています。国産品らしく平坦域がたいへん広いのが特徴です。
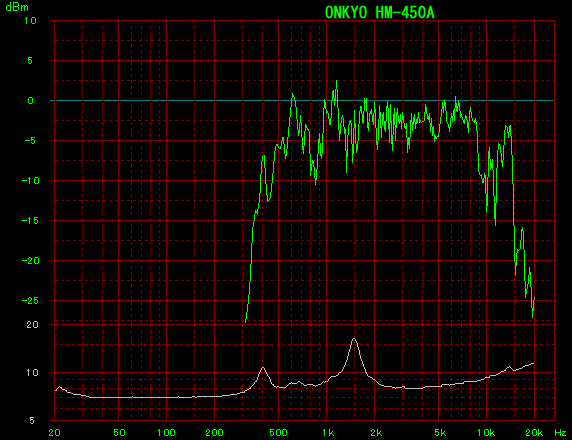
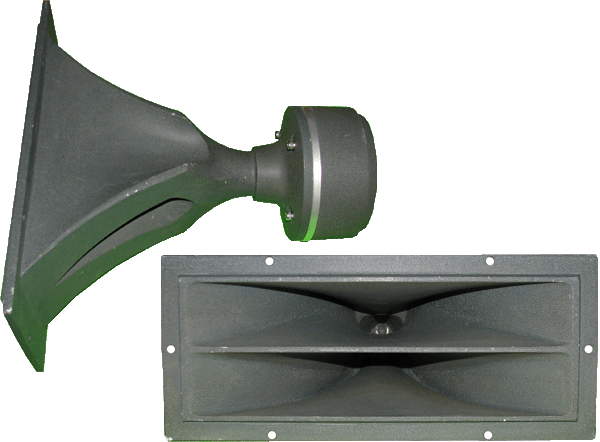
JBL 2425J と 2370A(500Hz用) の組み合わせ 奥行きの短いのが特徴です。CD(定指向性)ホーン特有のダラ下がり特性がはっきりしています。
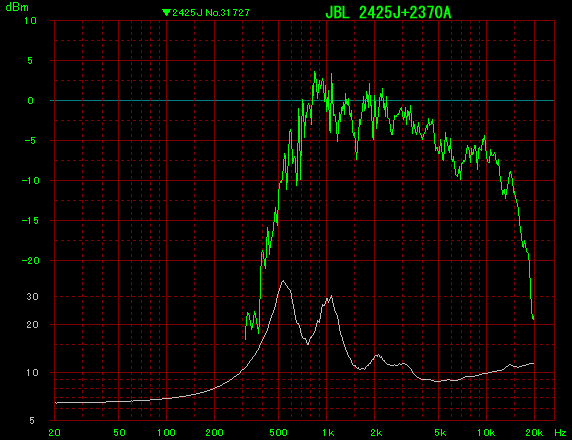
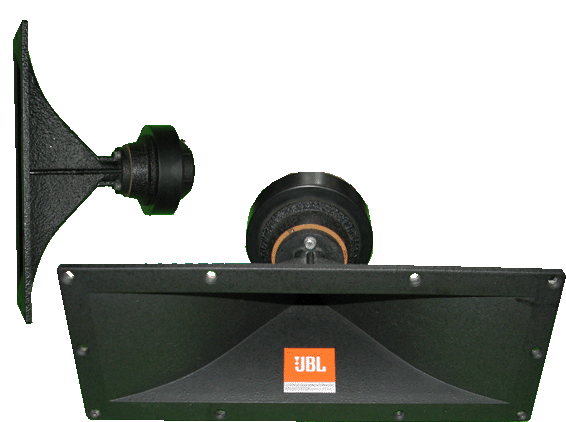
高域でダラ下がりとなるCDホーンの特性を補正できるようにチャンネルデバイダーで、高域をブーストできるCX3400の特性を参考までに掲載しておきます。
CDホーンSWがついたCX3400の特性
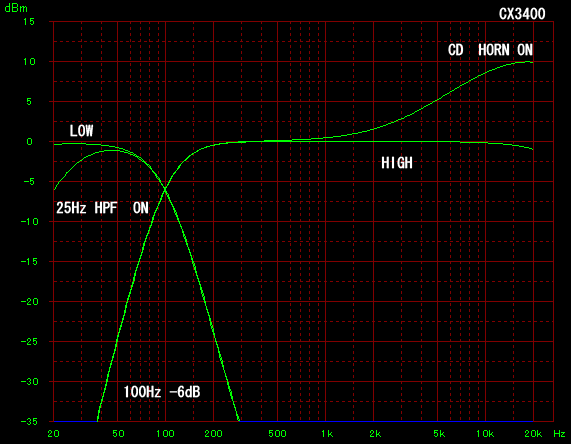
CX3400を100Hzでクロスした場合の特性で、リンクウィッツなので、クロスポイントは、-6dB、ウーハ保護用HPFは、25Hzで-3dBです。JBL 2425J+2370Aのように(右のグラフ)、高音域にかけてダラ下がりとなるCDホーン補正SWもついています。
CX3400は、クロス周波数設定に連続可変ボリュームを使用していますので、設定した周波数値がわかりにくいのですが、リンクウィッツライリーフィルターですので、クロス周波数での電圧値は-6dBです。-6dBは、半分の値なので、デシベル表示できないデジタルマルチメーターでも、周波数が調べられます。例えば、上のような場合で、平坦域、1kHz、0dBの場合0.775Vなのですが、0.775V÷2=0.3875Vという電圧値になった時、周波数カウンタレンジでクロス周波数を知ることができます。もちろん、1Vと0.5Vというように読みやすい関係の値を使用しても良いでしょう。低周波発振器などが無くても、発振器ソフトの周波数設定を変更していけば、クロス周波数は簡単に探せます。
LF SUM 機能について。
5.1サラウンドのように、サブウーハーを1個だけ使用する場合を想定している機能で、LRの信号の低音成分だけを、1ch側のLOWから出力されます。それぞれのチャンネルのフィルター周波数で機能しますので、L側100Hzで、R側400Hzなどの誤ったセッティングの場合、R側からは、設定した周波数に応じた低域成分が、LOW SUMに出力されますので注意します。又、High側の出力は、2ch独立使用でも、SUM使用でも、低域がカットされた出力となっています。小口径スピーカーなどで、低音側をカットしないで、フラットで出したいと思っても、そのような使い方には対応していません。
ヤフオクで入手したCX3400が、時々音が悪くなるので、HF側の出力波形を見て、びっくり仰天、正弦波が、崩れていました。原因は、OPアンプのハンダ付け不良で、倍率の高いルーペで、探し出し、ハンダ付けを行い、解決しました。
JBL 2445Jと 2380A(400Hz用)の組み合わせ
左からクリプシシュ ONKYO 一番右が、JBL2445J+2380Aです。2インチスロートホーンの大きさがはっきりわかります。600Hz〜5kHzぐらいが適正使用範囲でしょう。全帯域で、非常に歪みが少ないのが特徴です。400Hz〜600Hzまでがホーンが短いことによる-6dB/octの落ち込みですが、ピーク、ディップが少なく、開口端反射はよく制御されているようです。
ホーン中心部のスリットのサイズは、2380Aでは、19.8x100で、2370Aは、19x44.8であり、縦の長さは、推奨ドライバーのダイヤフラムの直径と同じです。この長さの違いは、2インチスロートホーンが、音が良いと評価される原因ではないかと推測しています。
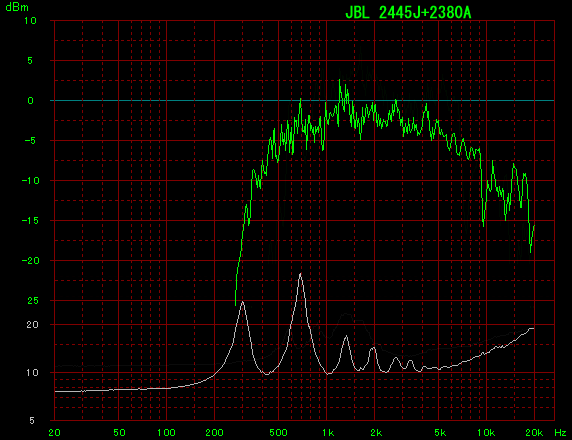
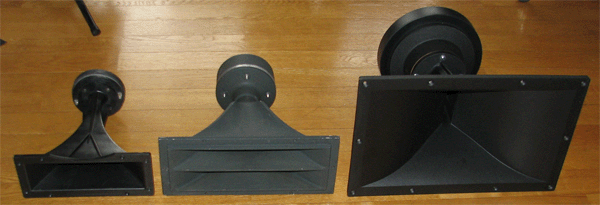
JBL2445Jのダイヤフラムを確認する為に、3本のプラスねじを外し、カバーを開けてみました。
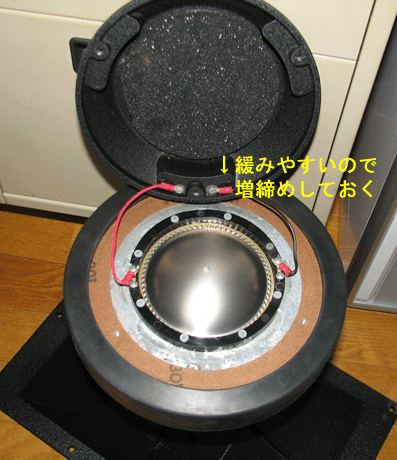
JBLドライバーのプッシュターミナルは構造上、内側のねじが緩みやすいので、裏蓋を開けたら増締めしておきますが、そと歯ワッシャーM3 を挟んで取付け直すと良いでしょう。
JBLで使用しているインチねじについて
入手したドライバーが古く、ユニクロメッキがほとんど腐食して変色していたので、ステンレス製と交換する事にし、一通り規格を勉強して、適合する物が入手できました。
ホーン接合部 W 1/4 首下長さ 25mm 平ワッシャー及びスプリングワッシャー W 1/4用 スパナサイズ10mm
裏側ケース部 #8-32 長さ 1/2 カーマで入手したUNCステンなべ小ねじでは、頭の径が8.3mmと大きく、6.7mmにまで小さくしないと使用できません。ステンレスなので、かなりきつい作業です。
代わりに六角穴のねじならば、6.74mmで径の問題はありませんが、六角レンチが、9/64という特殊サイズとなり、インチ用セットでは、組み合わされていません。単品をネット通販で、送料、代引き手数料込みで¥1,386で購入しました。
ダイヤフラム取付ねじは、#6-32 長さ 5/8です。注文先の商品構成では、六角穴のトラスねじでしたが、こちらは、普通のインチ用六角レンチセットが使えました。1kHz〜2kHzの音を出しながら1本づつ交換すると良いでしょう。
もしも、イコライザのギャップ確認などで、ダイヤフラムを外した場合は、音を出しながら、3本を最初に締めて、ビリ付きが無いことを確認して、他のねじを順次締めると良いです。
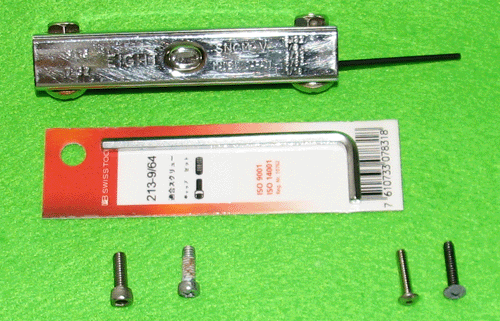
 ホームセンターの W1/4 取付ねじ(\100)
ホームセンターの W1/4 取付ねじ(\100)一般に入手可能な六角レンチ インチサイズセット 3/16、7/32、5/32、1/8、3/32、5/64、1/16という7本組と、スイスツールズ 9/64 六角レンチです。
ねじは、購入した#8のキャップと、オリジナルのなべねじ及び、#6のトラスねじと、メッキが飛んでしまっている、オリジナルのユニクロメッキ仕様ダイヤフラム取付ねじです。
RAMSA WU-S911/16 大型ラジアルホーンスピーカーの特性です。国産品(OEM)らしく、600Hz〜4.5kHzまでフラットな特性です。ダイヤフラムは、樹脂製です。右側は、ギャップ内の磁性流体が固化して障害が発生している時の特性です。磁性流体トラブルの原因は、過大入力によって、ボイスコイルが発熱し、磁性流体が沸騰した為です。ギャップ内の清掃を行い固形物を取り除いたら、インピーダンス特性は、正常品とは異なりますが、正常な音が出るようになりました。
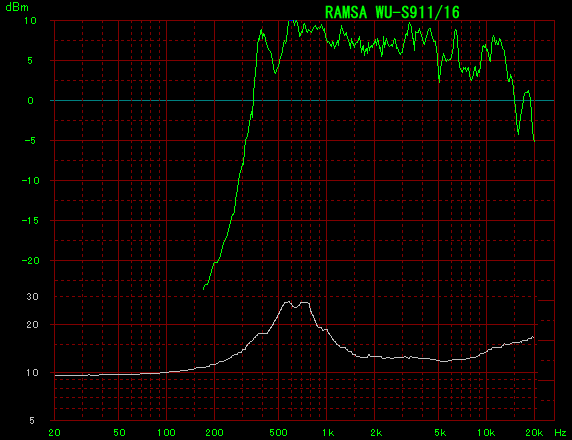
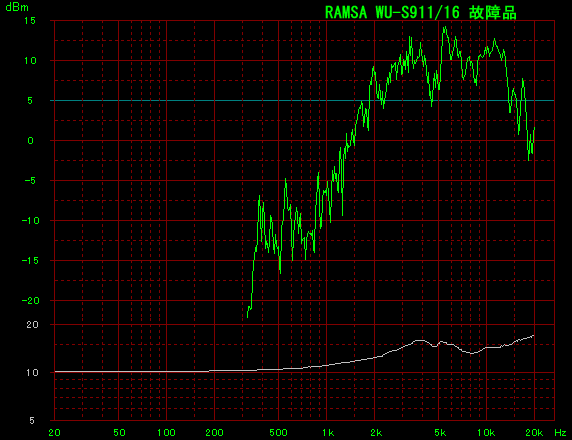
TOA 380SE High HT-371B-8 高域限界が結構早めで、15kHzまでの範囲のようです。帯域内でインダクタンス上昇が始まっています。JBL2405を少し小ぶりにしたような形状のホーンです。
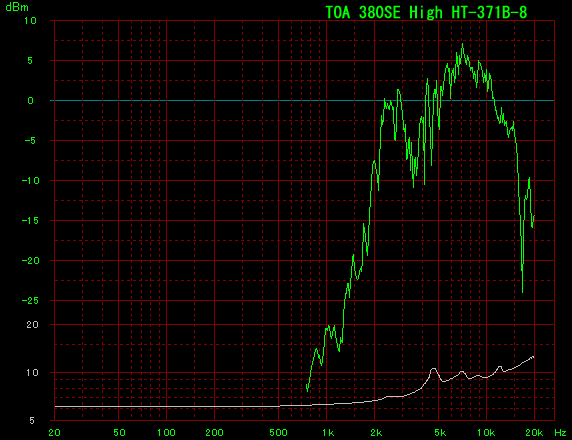


Beyma CP22 コンプレッションツイーター 40°コニカルホーン 上と同じく8kHzに特徴的な盛り上がりがあります。JBL 075と酷似したホーンです。上のHT-371B同様、7〜8kHzにピークが来る特性は、JBLと同等の音質を狙った結果、特性が酷似したのではないかと推測しています。インピーダンス特性は、非常に滑らかですが、ホーン自体の加工は、荒削りで、ダイキャストの鋳型の跡が残っていたりします。接続ターミナルは、スピーカーのフランジ部に向いており、隙間が13mmと狭く、一般的な平型ファストン端子は使用できません。旗型ファストン端子も試しましたがうまく接続できませんでしたので、直接ハンダ付けが良いと思います。
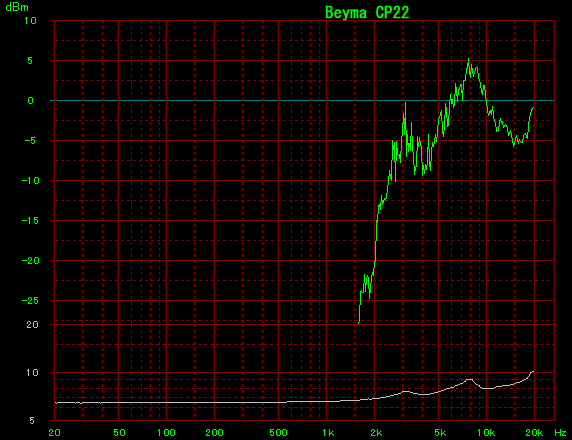

FOSTEX T90A リングダイヤフラムによるスーパーツイータらしく、20kHzまで平坦です。10kHzの落ち込みはこの機種の特徴です。上の2機種と違い、周波数特性は滑らかです。
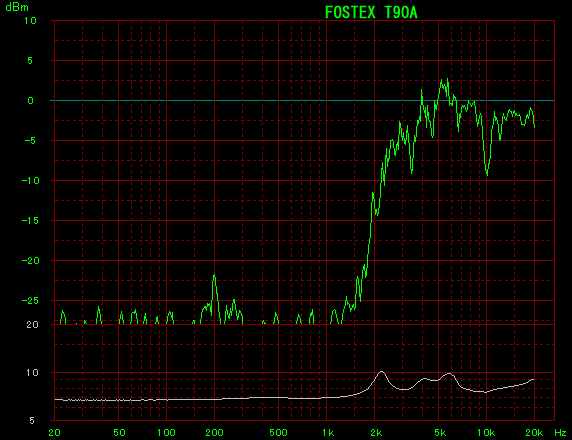
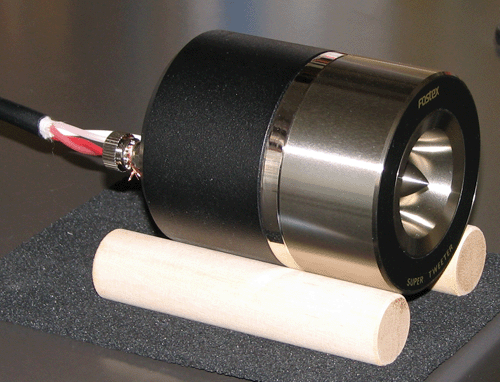
TANNOY System12 1991年頃
同軸2WAYスピーカーユニットで有名なTANNOYの1991年頃の製品ですが、モニタースピーカーとして開発されたシリーズで30cmウーハーを使用したモデルです。周波数特性 44Hz〜25kHz 出力音圧レベル96dB/W 8Ω クロスオーバー1500Hzです。念願がかなって、入手できましたので、早速、分析をしてみました。LFユニットには、直列にコイル、HFユニットには直列にコンデンサが入っており、KEFと同じく英国製スピーカーとして一般的な構成となっています。HFユニットには、レベル補正用の抵抗が入っており、+1.5dB、0dB、-1.5dBと可変可能です。LFユニットの最低共振周波数は、実測で20Hzと、さすがに、PA用大口径とは違い、モニター用らしく低い値となっています。特筆すべき点は、全帯域において、歪みが非常に少なく、100Hz以下の超低域でも、歪みが1%を越える事が無く、80Hz以上では、0.2%以下と、アンプの測定と間違うような低歪みでした。定格値として、高調波歪率0.5%と表示されていますが、TANNOYの自信の表れでしょう。
インピーダンス特性
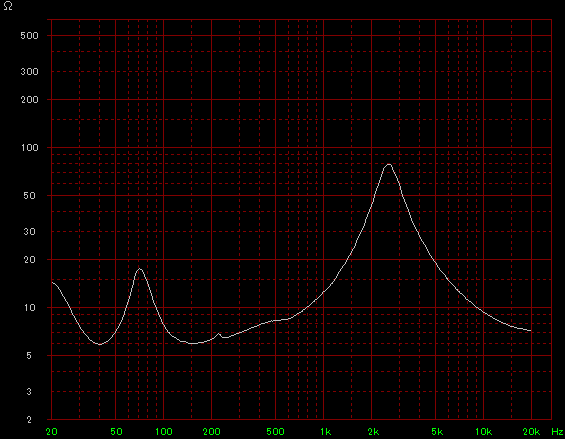
 2014/12/11
2014/12/11スピーカーの定格インピーダンスは、この測定からは、6Ωが正しい事が判ります。2kHzから3kHzにかけて80Ωと高い値ですので、真空管アンプで鳴らすと、かなり派手な高音になりそうです。
LFユニット と、HFユニットを、入力端子から独立して測定
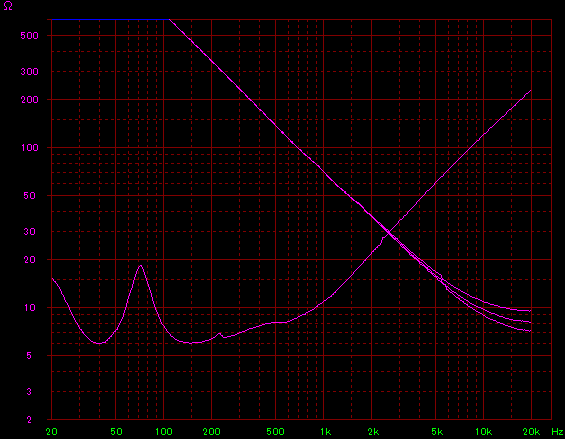
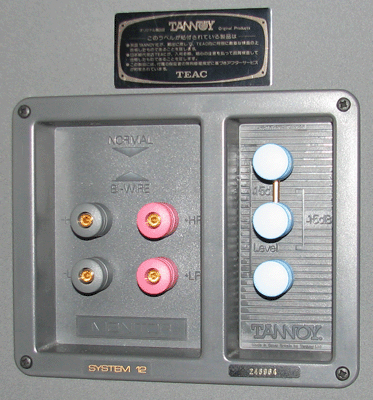
それぞれのスピーカー端子から直接に測定したインピーダンスで、上がLF、下がHFで、LFユニットのエッジが硬化しており、良品よりも山が右にずれています(No,142030)。エッジの硬化は、外部からのインピーダンス測定で、推測できると言えます。この事は、音響設備保守点検に重要であり、竣工時に、保守用の基準測定を行っておくと、経年劣化が推定できるようになります。通常の保守点検で行われる、ピンクノイズによる音圧特性だけでは、このような劣化を測定できません。元来NFBをかけて安定した回路性能が保証されているのが、電気機器で、これらのデータ取りに大半を費やす点検よりも、それ以外の接続盤やコネクタ類の実動作による、接点部分のリフレッシュや、要となるスピーカーの動作に、重きがあると思います。スピーカーユニットは、天井などの高所にある、エンクロージャーに取り付けられており、容易に現物を点検できませんが、このような手法により、エッジの劣化、ダンパーの破損、磁性流体の固化、ファストンコネクタの接触不良、ボイスコイル接合部の接触不良などの様々なスピーカートラブルの発見ができると証明できます。
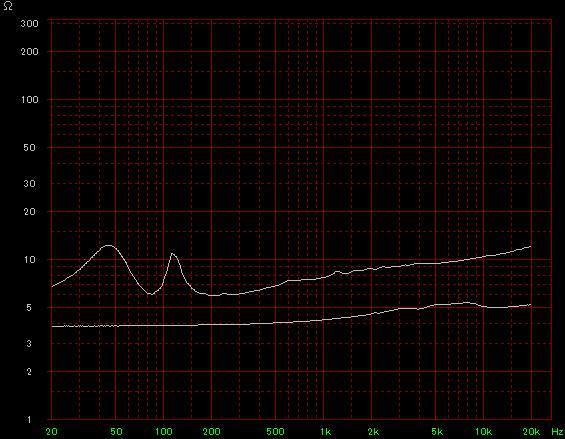
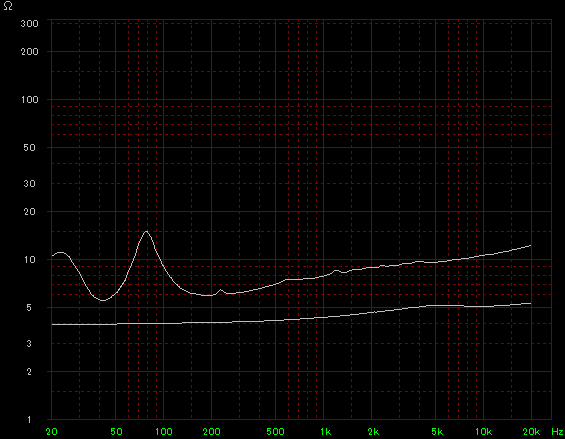 2015/010/01
2015/010/01LFユニットのインピーダンスは、6Ω、HFは、5Ωという測定結果です。右は、同じ物ですが、ウーアーのニトリルラバーエッジの裏表を清掃して、ポリメイトを塗布した物で、正常品にだいぶ近づきました。HFも芯出しを慎重にやった後で、インピーダンス変化が滑らかになりました。
インピーダンスから求めたLFユニットの直列コイルは、1.9mHで、HFユニットの直列コンデンサは、2.3μFで、HF用アッテネーターの値により、20kHzのインピーダンス値が、7Ω、8Ω、9.5Ωと異なった値を示します。
下は、実際の内部写真ですが、2mHの空芯コイル(内部抵抗41.8.2mΩ)と高域用コンデンサ2.2μF/160V等が主要な定数で、LF側が12dB/oct(2次)、HF側が6dB/oct(1次)フィルターとなっています。プリント基板を使わず、部品は接着により、基板に固定されています。
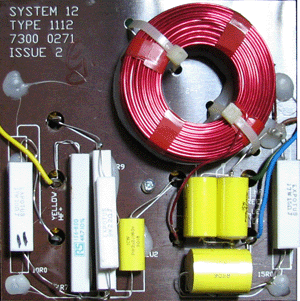
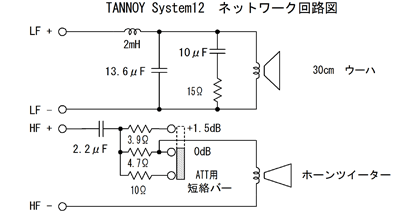
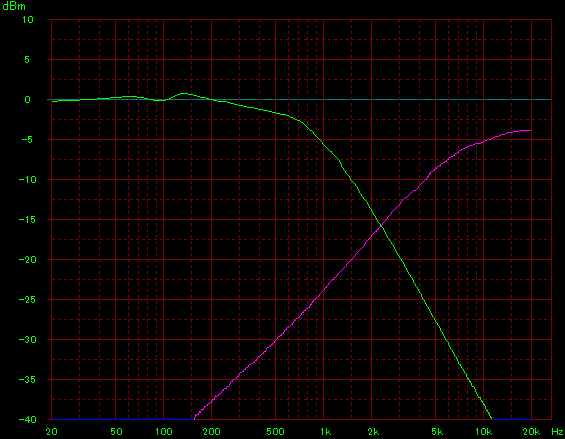
上のネットワークを経由してスピーカーに供給される電圧で、緑色がLF、マゼンタがHFで、HFのATTは、+1.5dBです。カットオフ周波数を-3dBポイントとすれば、LFが750Hzで12dB/octフィルターで、HFが6.6kHzで6dB/octフィルターとなります。メーカーの定格クロスオーバー周波数が1.5kHzとなっていますが、1.5kHzでは、LFが、-10.2dB HFが-15.9dBと、フィルターの理論とは、かけはなれた値です。パワーアンプは、SANSUI AU-α607NRAを使用しましたが、LF側が100Hz前後で、盛り上がったところがあります。完全にフラットなアンプで駆動しても、このような入力電圧となりますので、アンプによってスピーカーの音が変わる原因の一つとなります。この凸凹ができる、犯人は、空芯コイルの内部抵抗(418.2mΩ)と、スピーカーケーブルの直流抵抗です。真空管アンプでは、これらの抵抗に、高い内部抵抗が加わりますので、もっと極端に電圧の凸凹が出てきます。
周波数特性 LFとHFを同時に鳴らした場合と、独立して鳴らした場合で、音圧的なクロスオーバー周波数は、1.2kHz前後と読み取れます。スピーカーは、フロアにベタ置きしています。
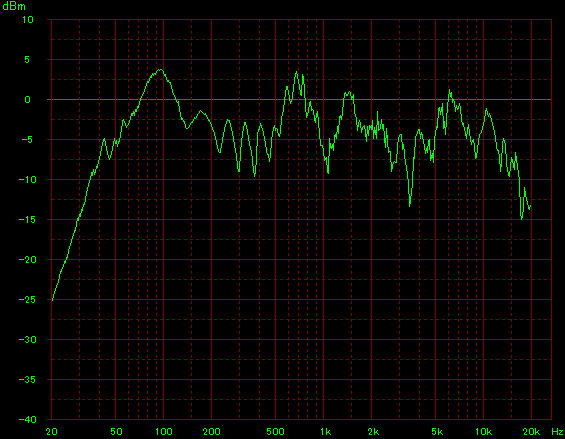
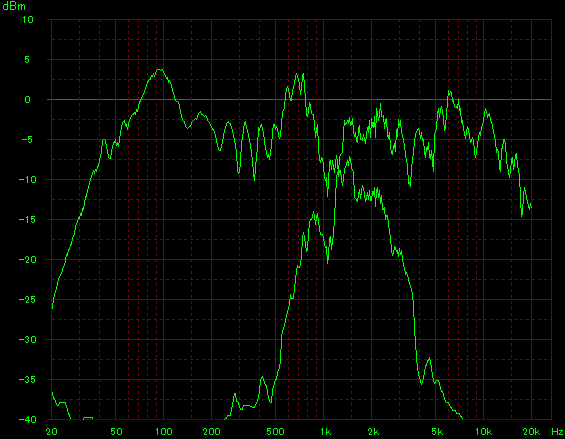
1波トーンバースト 1kHz 2.5kHz 5kHz 通常接続
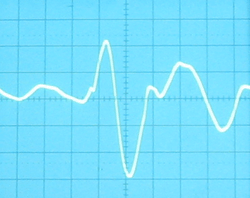
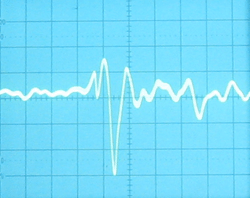
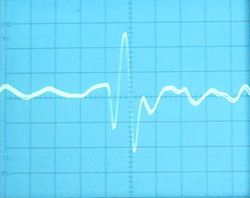 2015/01/06
2015/01/06HF ATT +1.5dBで、バイアンプ接続 遅延 LF 34mm
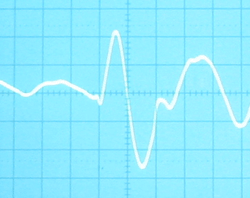
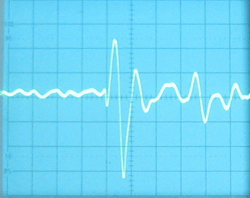
 2015/01/06
2015/01/06本格的なマルチアンプ駆動 バタワース18dB/oct クロスオーバー周波数2.51kHz 遅延 LF 44mm レベル LF -0.3dB HF -3.3dB
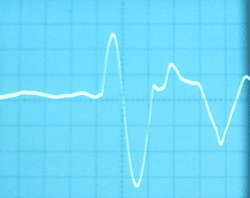
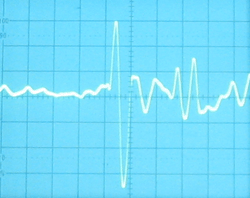
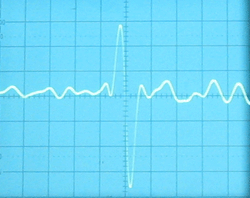 2015/01/06
2015/01/06一番上は、通常接続と表記しましたが、バイアンプ接続で遅延無しで、1アンプで、シングルワイヤー接続でも同じ波形となります。中段は、LFに34mmの遅延を掛けた波形で、2.5kHzは、形の良くなった正弦波ですが、5kHzでは、遅延無しと同じ結果です。これは、ウーハーからの音が5kHzのトーンバースト波に全く影響していない事を表しています。一方、マルチアンプとして、バタワースフィルター18dB/oct、遅延 LF 44mmとした波形は、1kHz 2.5kHz 5kHz全てで、良く整った波形となります。
LFに設定した遅延時間により、周波数特性が変化する関係をグラフにしてみました。床面から135mm浮かして、1オクターブ幅のFM変調波による測定です。(ピンクノイズでは、揺らぎが大きくこのような測定に向きません)10mm=29マイクロ秒相当
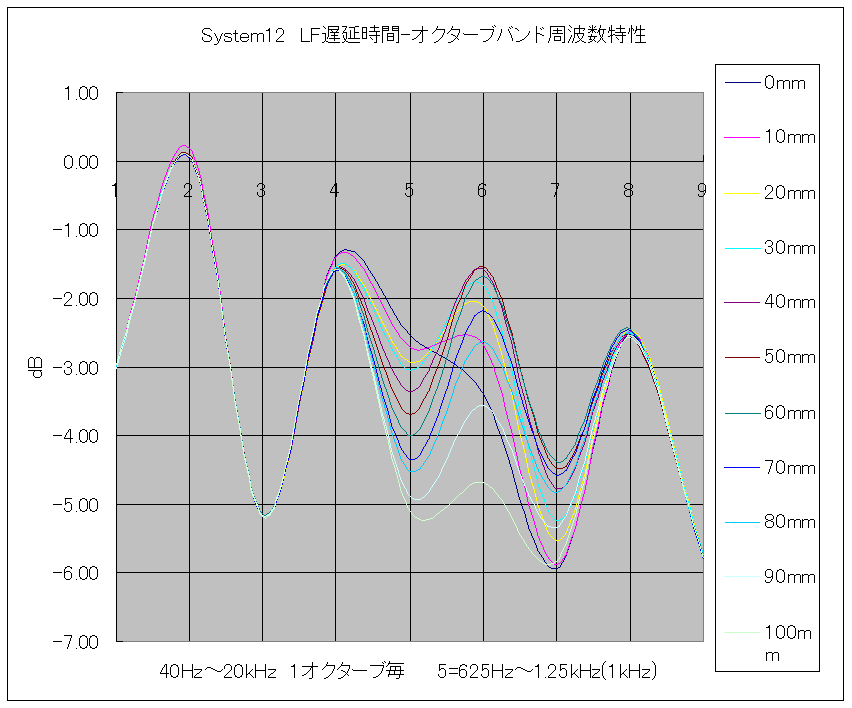 フィルター無しバイアンプ接続
フィルター無しバイアンプ接続遅延時間0mmのオリジナル接続では、1kHzが全体の最大で、2.5kHz〜5kHzが最小となり、音質的には、中音部分のくすみとして感じられると思います。遅延時間を増やすと、1kHzは低下しますが、その上の帯域が上昇します。30mmの線が見やすいと思いますが、1kHzがそれほど低下せずに、その上の周波数帯全てで改善されます。波形的には、36mmが良さそうですが、LFのコーンが、HFのホーンとして動作する奥行きの深い形状なので、遅延時間の最適値が、ある値に収束せず、正解が複数になります。これが、TANNOYの特徴の一つで、セッティングの妙が味わえます。床から135mm浮かしたのは、フロアにベタ置きでは、低域が持ち上がりすぎ、胴間声になってしまいましたので、その対策です。System12は、巷の噂では、ClassicだけでなくJAZZも聴けるとなっていますが、少し癖を取り去るだけで、かなり守備範囲が広がります。
このような遅延時間だけを設定する際は、チャンネルデバイダーのフィルターをOFFにして下さい。変なフィルターを設定すると、まとまりがつかなくなります。6dB/octのバタワースを1.5kHzでテストしてみましたが、内蔵のネットワークの影響で、HFを逆相にする方が良い結果となり、スピーカーと、チャンデバ双方で6dB/octなので、TOTALで、12dB/octのバタワースフィルターとして、振る舞います。AVアンプによる、バイアンプ接続では、LFだけに遅延時間を設定することができませんので、ディレイ機能のある、機器が必要となります。ここで、TANNOYのXO5000という古いチャンデバが、100μsec(長さでは、34mm15℃)という遅延ポジションを持っていたのは、改めて、自社製品を知り尽くしたうえでの事だったと気が付きます。
磁性流体トラブル
磁性流体は、ダイヤフラムの放熱と、センタリングが解決するということで、この頃から、現在までも、磁気回路のギャップに注入されておりますが、トラブル事例が報告される事が少ないので、まだ一般には、その微妙さが浸透していないと思いますが、磁性粉+界面活性剤+油という成分が、固化したり、減量したりで、音質に与える影響は有ると思います。すなわち、車で、オイル交換が必要なのと同じように、スピーカーも、数10年も経過したら、磁性流体のメンテナンスが必要と考えます。これに対して、古典的なエアーギャップのスピーカーは、ダイヤフラムの金属疲労だけが劣化要因で、ほぼメンテナンスフリーです。TANNOYのみならず、JBLでも、状況は同じで、左右で高音のレベル差が目立つようになったら、磁性流体のメンテナンスが必要になると考えましょう。(左右の特性が揃って、状態が良い場合は、歪み増加トラブルを避ける為にも、メンテナンス不要です。)上のRAMSA WU-S911/16の事例が、この事に気が付いた最初です。他にも、ホールのオペレーターさんからも、暖気運転のような、鳴らし時間が無いと、いつもの音が出ないという話を耳にしたことがあります。このホールのスピーカーは、先頃、サイド上手とと下手のインピーダンス特性を採ってみたのですが、見事に違う特性となっており、ピンクノイズの音色もかなり異なった状態なので、故障判定としました。
故障して500Hzが全く出ないミッドホーンスピーカーの特性例
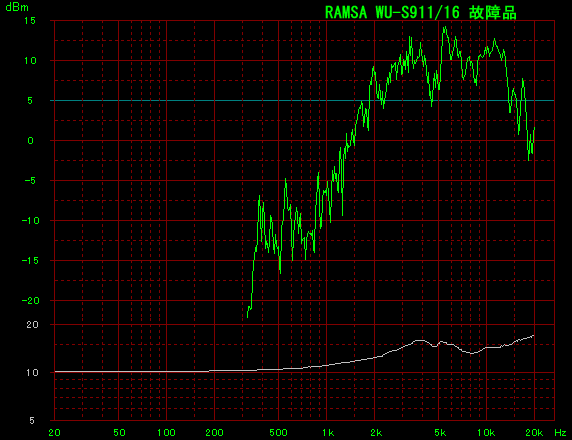 2009/02/28
2009/02/28WU-S911/16 磁性流体トラブル品の周波数特性とインピーダンス特性で、正常品と比較して、低域側の音圧低下と、ダイヤフラムの動作が圧迫される事で、インピーダンスが低下します。
手持ちのAR SRT170でも、磁性流体使用のコーン型ツイーターがトラブルを起こし、音圧低下を招いています。ALTECの高耐入力ドライバーも同様な現象があります。磁性流体の欠点は、ウレタンエッジと同様にスピーカーの寿命を短くする可能性が有ると断定的に捉えて良いでしょう。
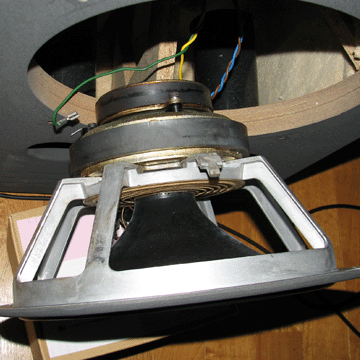
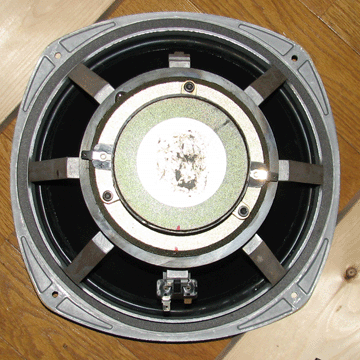
ユニット後方の小さいマグネットがHFユニットです。ユニットは、6角ネジ3本で取り付けられています。ミリネジを使用していますので、1.5mm〜6mmまでの7本組セットを使用して、ユニットを外しました。
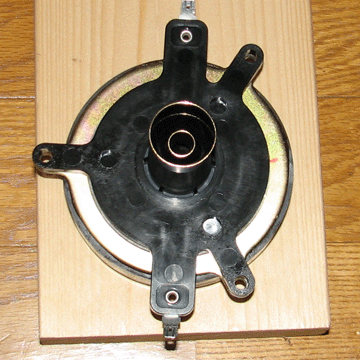
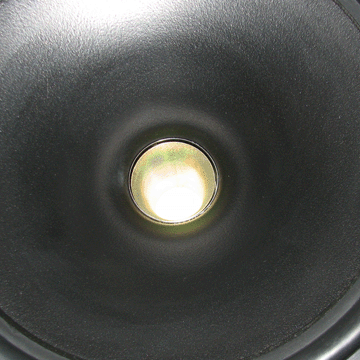
外したHFユニットとLFユニットで、ダイヤフラムを外す前に、赤色のマジックなどで、方向合わせのマーキングをしておくと良いでしょう。同軸ホーンの組合せがよくわかると思います。
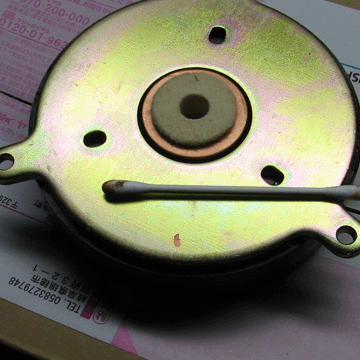
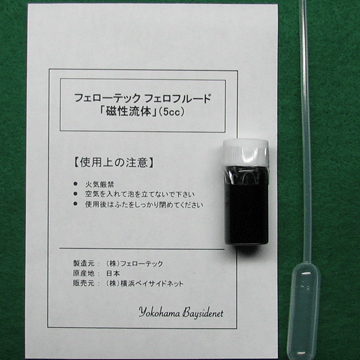
ギャップにある、古い磁性流体を取り除きます。この製品No,142030では、磁性流体が全周に行き渡っておらず、減量気味でした。右は、今回使用した磁性流体です。
RAMSAの大型ホーンのドライバーにも、このような磁性流体が充填されており、過大入力で、オイルが沸騰して飛び出した製品を修理した事があり、ギャップ内部で、固化した塊が有りました。(株)横浜ベイサイドネットさんの説明どおり、オカルト商品ではなく、JBL製品でも、常識的に使用されています。
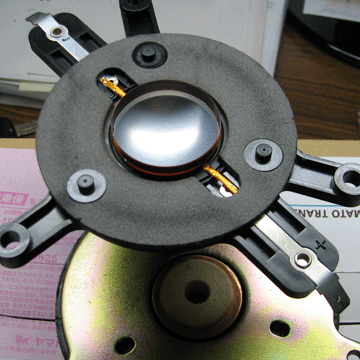
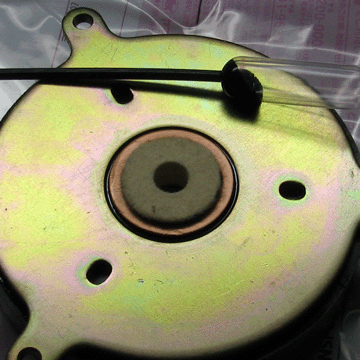
清掃を済まして取り付け前のダイヤフラムと、新しい磁性流体を充填した、ギャップ部です。ダイヤフラムは、面倒なセンタリング作業がいらないように、3カ所の突起が付いています。
ヤフーオークションで入手できる新品のダイヤフラムは、掲載されている写真によれば、磁性流体が入った注射器とセットになっています。
ダイヤフラム取付作業は、WaveSpectraで歪みを測定しながら行うと良いでしょう。取付時は、樹脂突起部が、磁気回路側にスムーズに入るように、清掃を入念に行います。特に綿棒などによる、繊維クズなどは、要注意です。
ダイヤフラムをセットする際は、4kHzぐらいの正弦波を鳴らしながら行います。コイルが、ギャップから離れていても、音が出ており、ギャップに近づくにつれ、音が大きく聞こえるようなります。ここでの組み立てに異常が無くても、下のネジ締め作業で又もや、歪みが発生することもあり、油断できません。
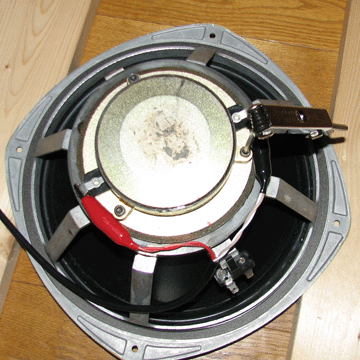
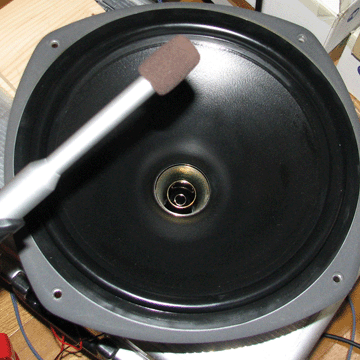 測定用マイクロホン ECM8000 無指向性なので、ご覧のような位置でもOKです。
測定用マイクロホン ECM8000 無指向性なので、ご覧のような位置でもOKです。4kHz正弦波を鳴らしながら、ネジ締めを行います。マグネット部のグレーの汚れのようなものは、箱との境目に防振の為にあるパテによるものです。
通常は、調整箇所が無い製品なので、これで作業が完了なのですが、困ったことに、ダイヤフラム取付時に、歪みが無かった事を確認したにもかかわらず、この3本のネジを締めた途端に、高調波歪みが発生してしまいました。ネジが3本しか無いとはいえ、ダイヤフラムの剛性が低いので、かなり神経質な作業となり、WaveSpectraにて歪みを確認しながら、締め加減を調節し、最終的に全部が締まった状態に持っていくと良いでしょう。
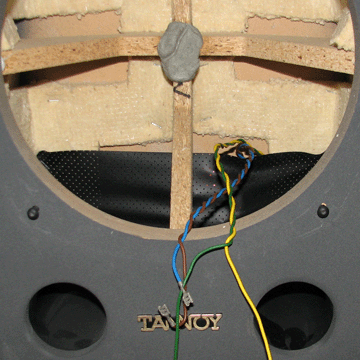
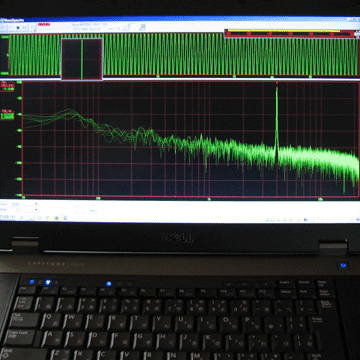 2014/12/23
2014/12/23測定用条件等:マイクロホン用ミキサー 01V96V2、オーディオキャプチャ UA-5、発振器AG-203、パワーアンプ AU-α607NRAにて、4kHz時 歪率0.017% と、アンプ並の低歪率です。よく注意して見れば、8kHzの第2次高調波が見えています。
使用した磁性流体の量は、約2mlでした。FFTソフト WaveSpectra がある事により、本当に助かっています。真空管アンプの位相反転回路のACバランス取りと、今回のダイヤフラム取付などには、変な高級測定器よりも、PCによる、FFTの方が適しています。
スピーカーユニットを外した写真から、30mm厚MDF材、十字型に組まれているキャビネット補強材、スピーカー後部に接触している、ダンピング用のパテが見えます。オリジナルのスピーカーコードは、捻りが無くストレートで配線されていましたが、ご覧のように、捻り配線として、LFとHFの干渉低減とインダクタンス低下をはかりました。ユニットへの接続は、ファストンコネクタです。スピーカーを自作される方には一種の参考例となります。
TANNOY System12 をマルチアンプ駆動
LF、HFユニットそれぞれの単体周波数特性で、4kHzの少し下で、音圧的なクロスをしています。HFは、保護の為、500Hzのフィルターを入れて測定しています。
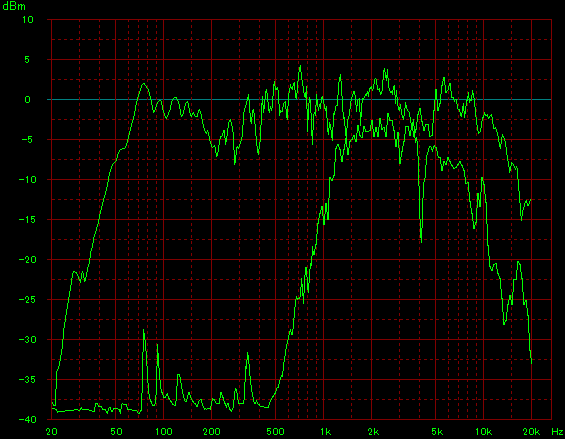
バタワース 18dB/octフィルターを使用した、周波数特性 クロスオーバー2.51kHz及び3.04kHz
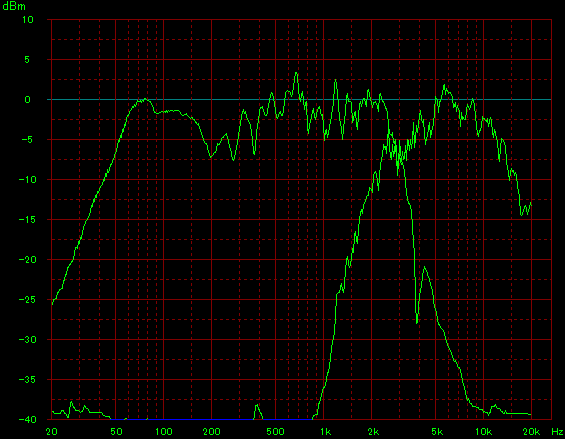
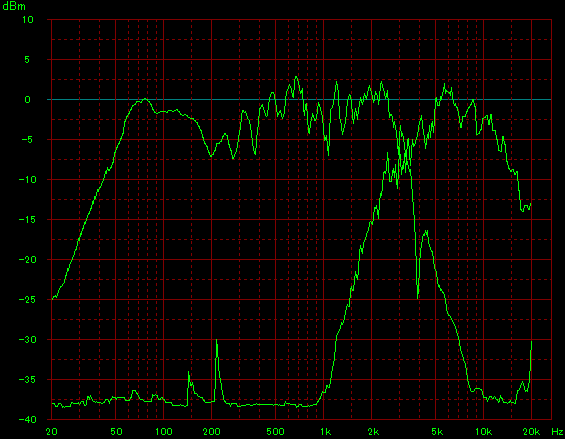
左右の違いは微妙で、耳では両者の違いは良く判りませんでした。そこで、1オクターブバンド特性を取りよりフラットな方を使用することとしました。よりフラットだったのは、左の2.51kHzでした。
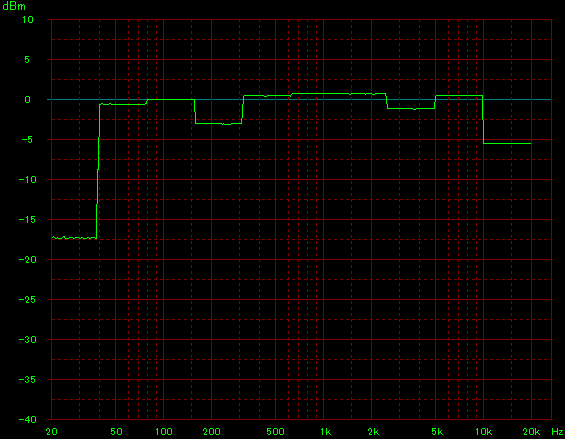
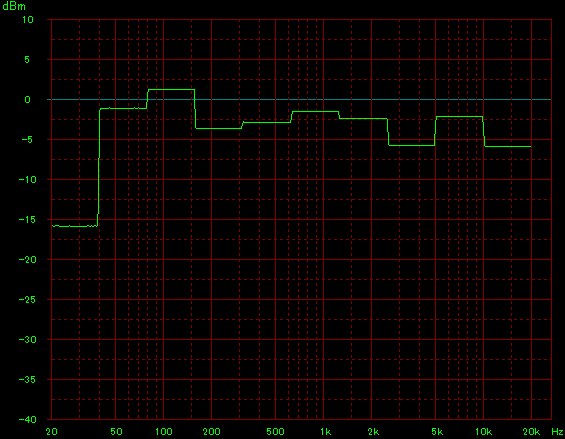
左がマルチアンプ駆動、右がオリジナルのオクターブバンド特性
マルチアンプ駆動は、コイルやコンデンサを介さず、アンプと直結にして行いました。やはり、ウーハーのコイルを外すと、低音が締まりますが、100Hz辺りのレベルもダウンしてしまいます。そこで、スピーカーボックスを床から35mmに落とし、低音が良く出るようにしたのが、上の左側です。全域で、かなりフラットになっている事が良く判ります。右側が、オリジナルのバンド特性ですが、ローがかなりブーストされています。フレッチャーマンソン特性を意識すれば、常識的な音量で使用した時、オリジナルの方が、支持率が高いでしょう。対して、マルチ駆動では、波形の良さはわかるが、音としては明るく、これがTANNOYかという評価ともなります。物理特性なのか、音楽特性なのかという、昔、流行った論点にまで、格下げになってしまいます。絶対を意識した、トランスジューサーとしてのスピーカーなのか、音楽を自分好みで鳴らす置物としてのスピーカーなのか、選択を迫られるでしょう。
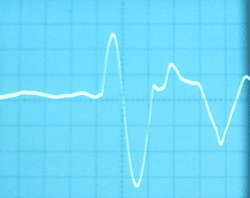
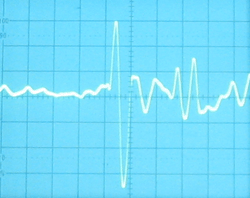
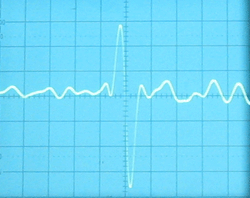 マルチ駆動時の 1kHz 2.5kHz 5kHzのトーンバースト波
マルチ駆動時の 1kHz 2.5kHz 5kHzのトーンバースト波バタワース18dB/oct クロスオーバー周波数2.51kHz 遅延 LF 44mm レベル LF -0.3dB HF -9dB 同相接続
3WAYマルチアンプ駆動
2WAYマルチアンプ駆動をしてみると、LFとHF間の微妙な位相ズレに悩まされます。おおよそクロスオーバー周波数から上ではうまく位相合わせができていても、LFの低い方と、HFの高い方では、合わない状態でした。そこで、クロスオーバー周波数帯を別のスピーカーに任せて、この微妙な周波数帯を、TANNOYから出ないよう、3WAY化して、全帯域の位相合わを行いました。使用したスピーカーは、JBL 2425J+2370Aと、2445J+2380Aです。大型の2380Aでは、位相合わせに苦労しまして、従来の1波トーンバースト波ではなく、400Hz-2kHz-10kHzを3波同時鳴らしで、400Hz1波で、ゲートを切り、その間に、2kHzが5周期、10kHzが25周期という波形を出し、並びの良さで、判定しました。結果的には、1インチモデルの方が、TANNOYにうまく合いました。
3WAYでの設定例(遅延時間は、ホーンが大型であり、取付位置により、変わりますので明記しません)
JBL 2425J+2370A L-R 24dB/oct 807Hz 5.08kHz
JBL 2445J+2380A L-R 24dB/oct 607Hz 5.08kHz
50cmぐらいのニアフィールドでは、2WAYのままで、3WAY化はあきらめた方が良いでしょう。
2WAYでの設定例 BT 18dB/oct 2.51kHZ LF -0.3dB 遅延44mm HF -9dB バタワースフィルターでは、クロス点の盛り上がりの影響で、HF= -9dBと多い目にATTを設定しました。
L-R 24dB/oct 2.51kHz LF -0.3dB 遅延32mm HF -7dB リンクウイッツフィルターの方が、落ち着きのある音質で、現在はこちらを使用中です。
冗談ではなく、JBL-TANNOYをテスト
 JBL 2445J+2380A TANNOY System12 3WAYマルチ テスト 2015/01/19
JBL 2445J+2380A TANNOY System12 3WAYマルチ テスト 2015/01/19テスト中のスナップですが、このような大型ホーンとの組合せでは、ニアフィールドがまるっきり駄目になってしまいます。せっかくの同軸スピーカーに対して、中音域が離れてしまい、リスニングポジションが2m以上離れないと音にはなりませんでした。そこで、実用バージョンでは、1インチの2425J+2370Aとして、音源を接近させ、ニアフィールドを改善する予定です。JBLとの組合せは、TANNOYファンから叱られそうですが、オールドタンノイとは違い、モニター用ですので、歪みの少なさと、定位の良さを保ち、位相特性を改善するのなら、ミッドホーンを入れるのは、有効な手段と思います。
 ←JBL-TANNOY試作品
←JBL-TANNOY試作品  使用中の写真で、保護ネットは自作しました 2015/02/15
使用中の写真で、保護ネットは自作しました 2015/02/15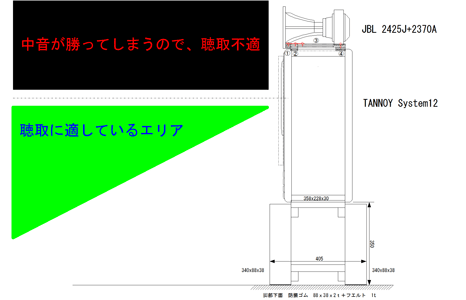
JBL-TANNOYは、上のような結果となり、メインユニットが同軸2WAYなので、ツイーターの位置が低く、立ったままで聴いた場合に難が出ました。このように、3WAY構成は、中音ホーンがどうしても最上段になりますので、お奨めではありませんでした。
メインユニットが同軸2WAYの場合、エンクロージャーの最上位に16cm程度のユニットを配した、トールボーイタイプが(例:KEF Q70)、リビングのような空間には、適しています。大口径ユニットは、どうしても、エンクロージャーの中心に来ますので、設置時の高さで苦労します。
KEF Q15.2 同軸型2WAYスピーカー 2000年頃の製品
ソフトドームツイータをコーンの中心に配置した本格的な同軸スピーカーです。タンノイでは、ホーンツイーターをセンターとし、コーンをウェーブガイドにしていますが、KEFのドームツイーターには、ウェーブガイドと言えるパーツはありません。タイムアライメント的には、合っていそうですが、それは、コーンの一番奥から音が出ていればの話で、そんな微妙さに、興味をそそられますが、遅延をかけてやると、音の透明感が増えます。小型スピーカーにありがちな、歪みの多い周波数帯は少なく、良く鳴るスピーカーです。低音は、サイズの割にローエンドまでしっかり延びており、ちゃっかりと、150Hzで、ブーストし、若者が低音として感じやすいところを補強しています。高音域もホーンツイーターのように、8kHzあたりをブーストして、いわゆるドンシャリタイプの音ですが、使用される音圧を考えれば、フラットな仕上げでは物足りない音となり、こういった手法は、オーディオ用スピーカーの宿命のようです。
 16cm PPコーンとソフトドームツイータによる同軸2WAY
16cm PPコーンとソフトドームツイータによる同軸2WAYバイワイヤリングに対応した2WAYスピーカーで、中側がHF、外側がLFで普段はジャンパー金具を付けておき、1台のアンプから1対のケーブルで接続します。10-100Wという表記から、入力は、HFが10W、LFが100Wと解釈して良いと思います。
バイワイヤリング接続の場合は、1台のアンプ出力端子から、スピーカー側のジャンパー金具を外して、HFに1対、LFに1対の、計2対のケーブルで接続をします。
バイアンプ接続は、このL,H用2対のケーブルを更にアンプに対して1対1、すなわち、2台のアンプと接続します。バイアンプ接続は、SPオリジナルのフィルター特性でも構わないのであれば、スピーカー自身にLFが6dB、HFに12dBフィルターが実装されているので、チャンネルデバイダー無しでも可能で、普通のアンプをそのまま接続するだけでも、マルチアンプ駆動が実現できます。AVアンプのバイアンプ接続などでも使用できます。
本格的なチャンネルデバイダーで、フィルターは無しで、HFを逆相、遅延時間22mmとすると、遅延ゼロ時に失われてしまっている音に気付きます。更に、レベル調整が可能になりますので、好みのバランスも得られると思います。
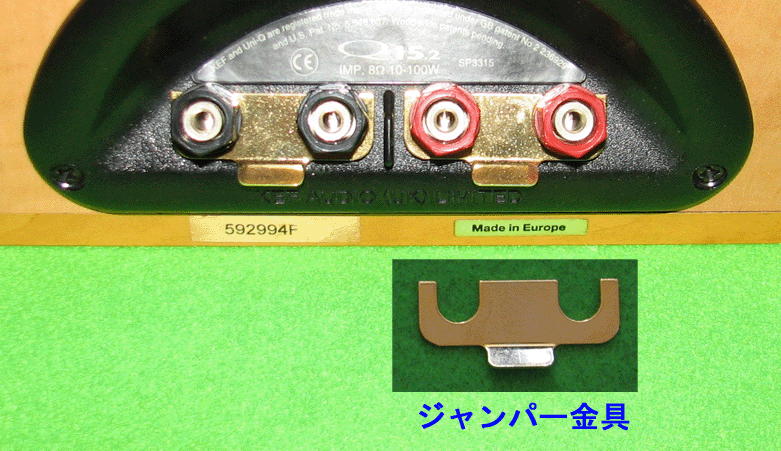
シングルワイヤー接続では、ジャンパー金具を付けて使用します。ジャンパー金具の抵抗値は、3.8mΩで、バナナプラグとジャンパー線では、実現できない低抵抗です。
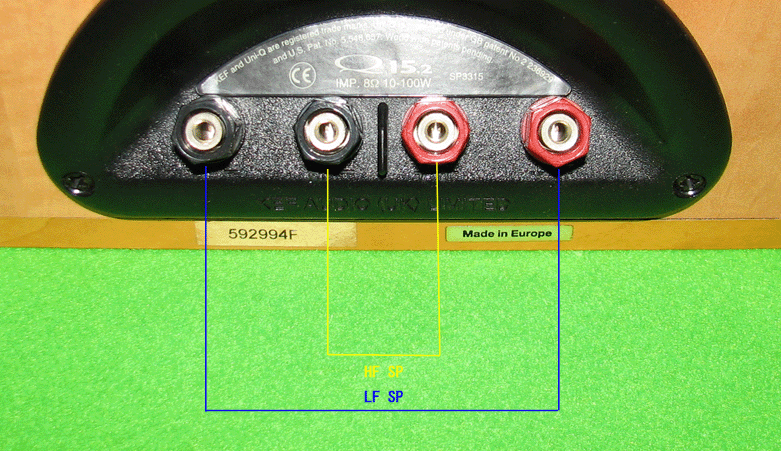
バイワヤリング接続は、内側がHF用、外側がLF用で、アンプまで別のケーブルで接続します。メーカーは、こうする事で、逆起電力の雑音が他のスピーカーに入り込まないと説明していますが、ケーブル抵抗が高い場合では、この説明にも一理あると思いますが、0.1Ω以内の低抵抗であれば、そのような心配は無く、アンプの低い内部抵抗により、雑音が目立つ事はありません。
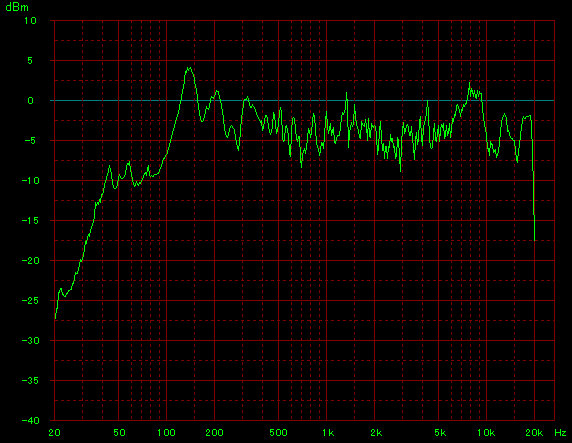
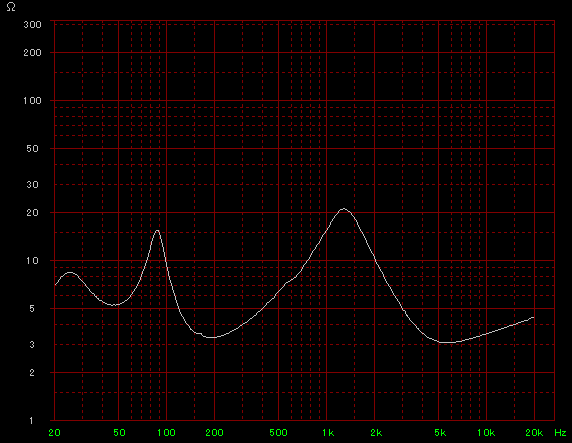
普通にジャンパーを付けた場合(シングルワイヤー接続)の音圧特性(フロアより80cm)とインピーダンス特性 最低共振周波数 25Hz バスレフポートチューニング周波数 88Hz 公称インピーダンス3.3Ω 最低インピーダンス3.1Ω at 5.5kHz
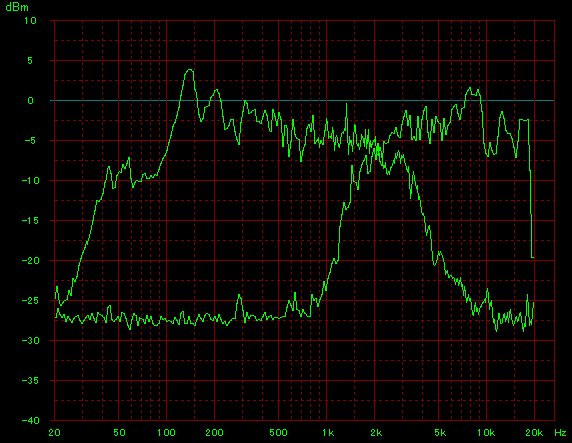 LF HFを別々に鳴らした音圧特性
LF HFを別々に鳴らした音圧特性音圧的には2kHz付近でクロスしていますが、カタログ定格値では、3kHzとなっています。
音質は、バイワイリング、マルチアンプ駆動のどちらも、中抜け傾向で、原因が、ウーハーと直列に入っているコイルにあると推論できます。写真右側の黒いのがウーハーに入っているコイルで、6dB/octで高音をカットしています。
このコイルの両端を0.5SQの電線で短絡し、コイルを効かなくした時の特性が、下の左側で、4kHzまでフラットになっています。これなら中抜けが解消されるものと期待できます。高音側にもコイルが有りますので、高音部は12dB/octとなっているようです。
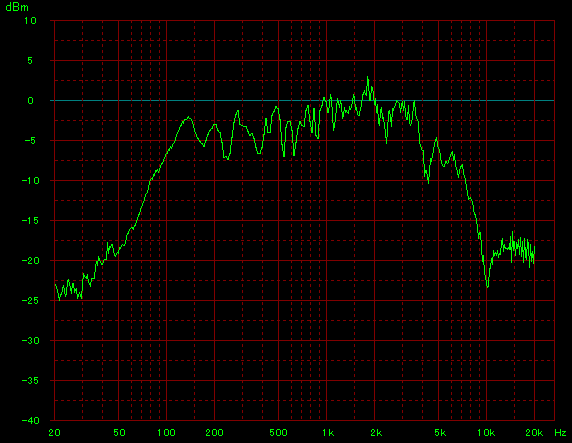
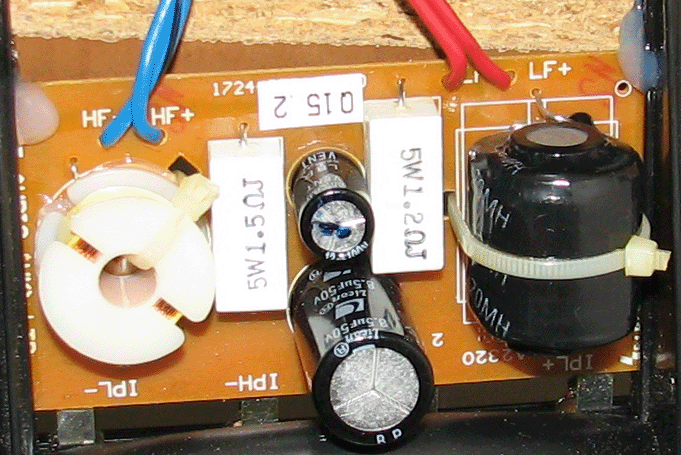
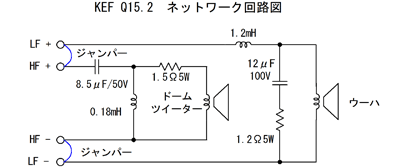
LFユニット及びHFユニット単体のインピーダンス特性 LFが3.27Ω HFが3.04Ωとかなり低い値です。
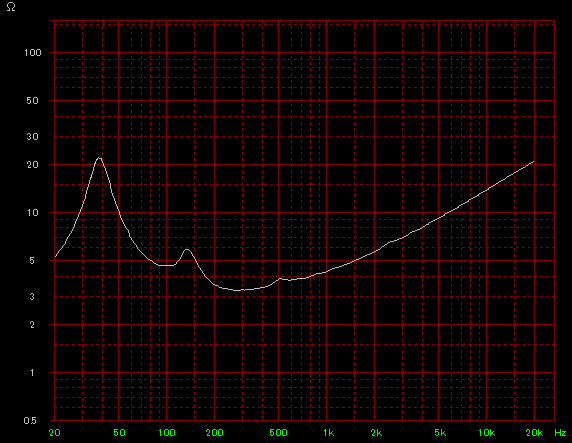
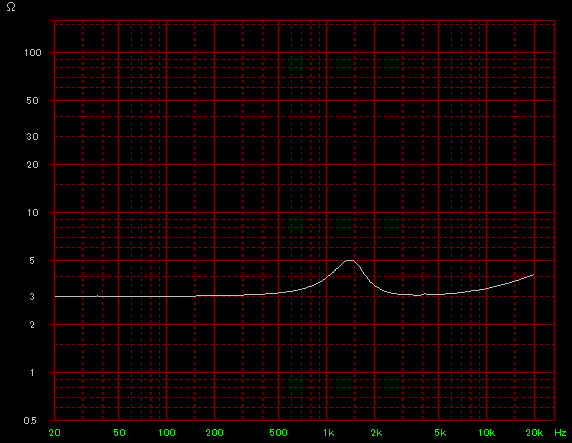
LF端子とHF端子からののインピーダンス特性で、LF側(左)には、コイル、HF側(右)にはコンデンサが入っているのが良く判ります。
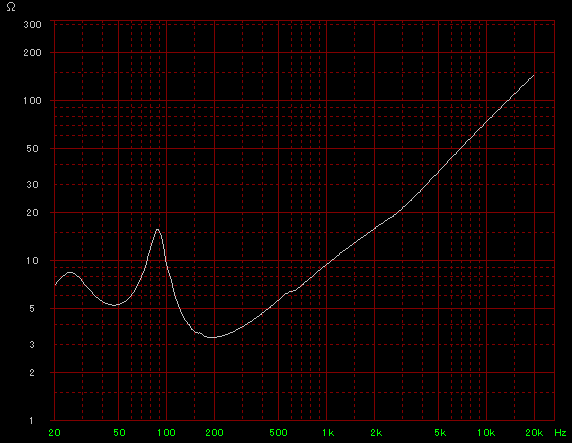
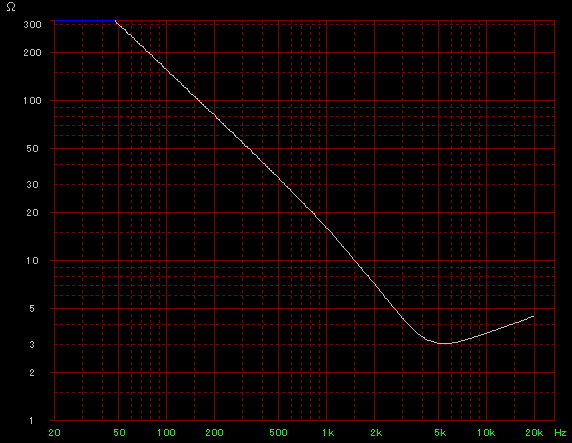
どちらのユニットも、インピーダンスは8Ωとは呼べず、3Ωまで落ちるところがあります。LF側を見れば、公称インピーダンスは、3.3Ωとすべきでしょう。それでは、アンプの定格負荷が8Ωとした場合、アンプに悪影響があるのではと、心配される方も有りそうですが、心配は無用です。過負荷と呼べる状態は、例えば、最大出力が出るボリュームポジションで鳴らし、最大音が入った時なので、普通に聴いている場合は、アンプに設計されている最大電流値を越えることは有りません。又、最大電流範囲内で有れば、歪みが多くなり過ぎる事も無いでしょう。アンプが危険レベルの時は、異常発熱をしますので、発熱に注意をします。半導体アンプの放熱設計は、60℃を上限とする場合が多く、放熱板の表面温度50℃を越えない範囲ならば、大騒ぎしなくても良いでしょう。
KEF Q15.2 1波トーンバースト波形
通常接続(シングルワイヤー) スピーカーケーブルは、4S6 2m (0.08Ω以下)を使用し、スピーカー正面50cmの波形です。
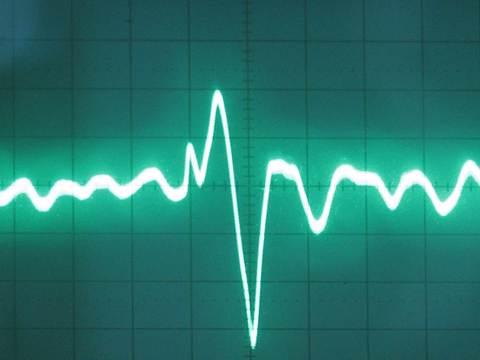 2kHz
2kHz 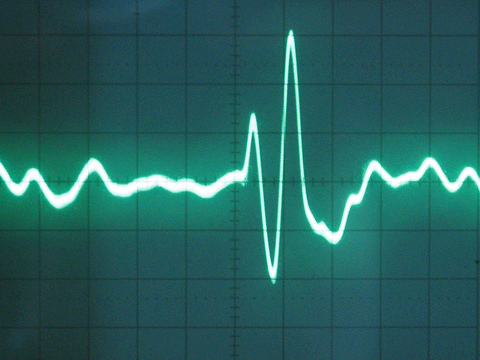 5kHz
5kHzバイワイヤリング接続 波形はシングルワイヤーの場合と大差ありません。この違いを聞き分ける凄い耳の持ち主に敬服です。
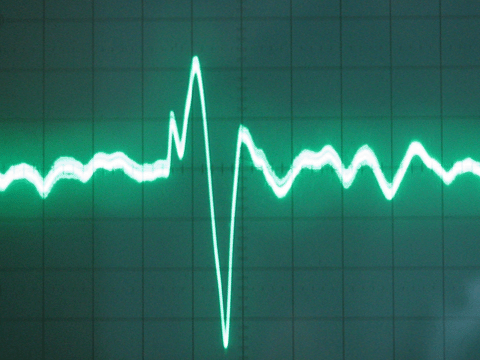 2kHz
2kHz 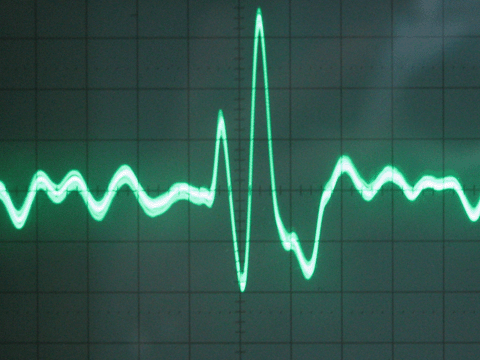 5kHz
5kHzバイアンプ駆動 遅延無し
撮影中
バイアンプ駆動 遅延あり、音量バランス調整あり 設定値 LF -0.3dB 、HF -2.5dB 遅延 22mm 極性反転
撮影中
KEF Q15.2を3WAY化したら
マルチアンプ駆動をしたついでに、JBL 2445J+2380Aホーン購入で浮いていた、2425J+2370Aホーンを、クロスオーバー周波数が曖昧な、Q15.2と組み合わせてみました。
影2013/05/06

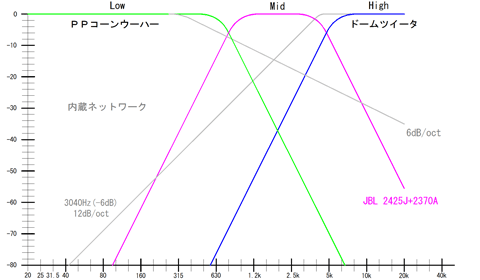 2015/05/06図面訂正
2015/05/06図面訂正バイワイヤリング用途で、フィルターが入っていますので、チャンネルデバイダーのフィルター選択がなかなかまとまらず、種々の組合せを試みた結果、バタワース18dB/Octで結果が最良となりました。クロスオーバー周波数は、805Hz、4.98kHzにて、200Hz〜10kHzまでの偏差が0.9dBと、フラットな特性です。遅延時間は、L側が238mm、H側214mmです。16cm同軸2WAYスピーカーと比べて、1インチドライバーといえども、ホーンスピーカーは巨大ですので、写真のように頭でっかちとなりました。上下関係を反対にしても良いのですが、手持ち品流用ですのでこのようになりました。音質は、解像度が上がり、2WAY時の痩せた中音でなく、音量が小さくてもはっきり聞こえる音になりました。定位も2WAY時より、小さい範囲で、音像がまとまり、明解です。バイワイヤリング対応の、一般的な2WAY小型スピーカーをこのようにして3WAY化し、その後、大型ウーハを入れて4WAY化するというようなステップアップも楽しめると思います。
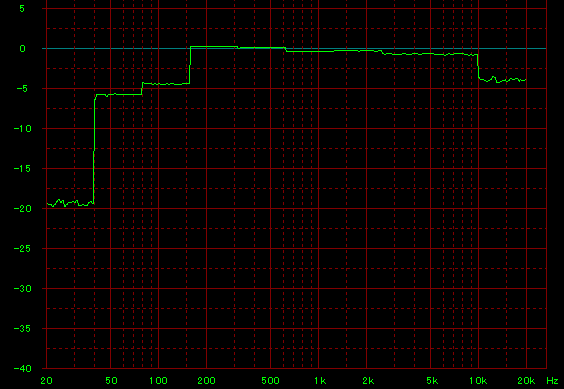 KEFQ15.2も、3WAY化でかなりフラットになります
KEFQ15.2も、3WAY化でかなりフラットになりますKEF Q70 4スピーカー構成トールボーイタイプ 1994年発売
Q15.2よりも前の製品です。Q10、Q30、Q50、Q70というシリーズ構成中、最上位となる機種です。同軸2WAY16cmスピーカーを上段に配し、その下には、16cmウーハーが2個、スピーカーBOXは、7リットル、11.7リットル、17.6リットルの3個で成り立っています。カタログの定格は、周波数特性は45Hz〜20kHzとあるのみで、クロスオーバー周波数や、ポートチューニング周波数のデーターもなく、いったいどうなっているのか興味を持ちました。なお発表されいる、BOX容量から計算した、ポートチューニング周波数は、11.7リットルの方が、61Hzで、17.6リットル側が50Hzとなりました。3個のユニットは、315mmで等間隔の配置であり、低域では、ラインアレイのように振る舞い、線音源的な減衰しにくい音源になる可能性を秘めています。故に、チャンネルデバイダーを使用しての積極的なマルチチャンネルではなく、AVアンプのバイアンプ接続に最適と推測しました。
 1018x190x273 16.9kg
1018x190x273 16.9kg 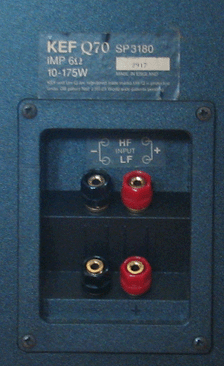 端子は、上がHF用で、Uni-Qスピーカー用、下はウーハー2個用です。
端子は、上がHF用で、Uni-Qスピーカー用、下はウーハー2個用です。接続端子に付属するショートバーが有り、1台のアンプで、HF、LFが並列で鳴るようになっていますが、ショートバーを使用しないで、アンプまで2対のケーブルで接続するバイワイヤリングや、2台のアンプでそれぞれを駆動する、バイアンプ接続もできます。バイアンプ接続では、スピーカー自身にフィルターが付いていますので、普通のアンプ2台や、AVアンプのバイアンプ接続でも、OKです。チャンネルデバイダーを使用して、さらに急峻なフィルターも使用可能ですが、それぞれのスピーカーの特性を熟知していないと、満足できる結果は得られません。
LF 部
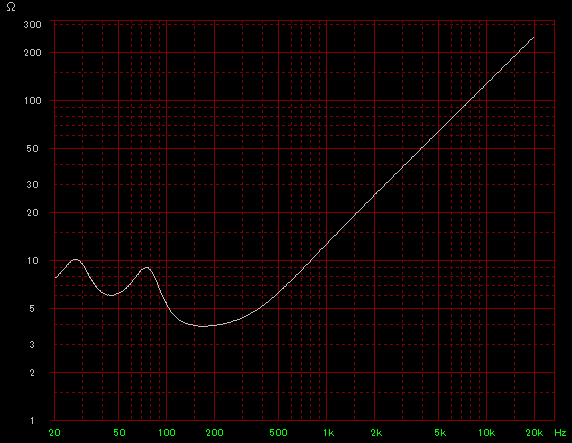
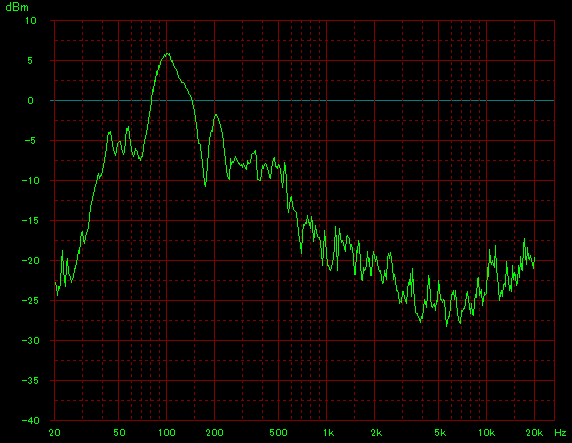
ユニットの最低共振周波数は、27Hzでインピーダンスが高域へ一直線に上昇していますので、コイルが直列に接続されています。フィルター傾斜 6dB/octで、100Hzで特徴的な盛り上がりがあります。
HF 部
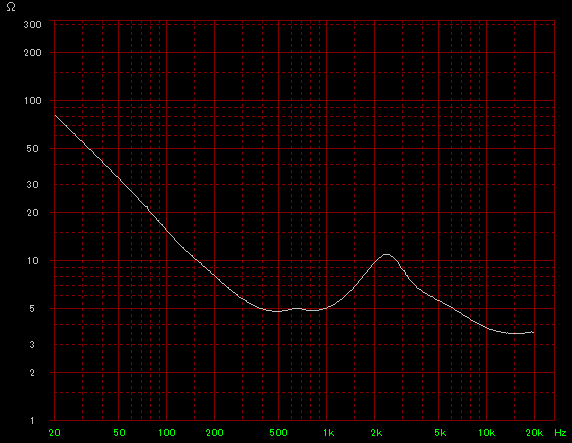
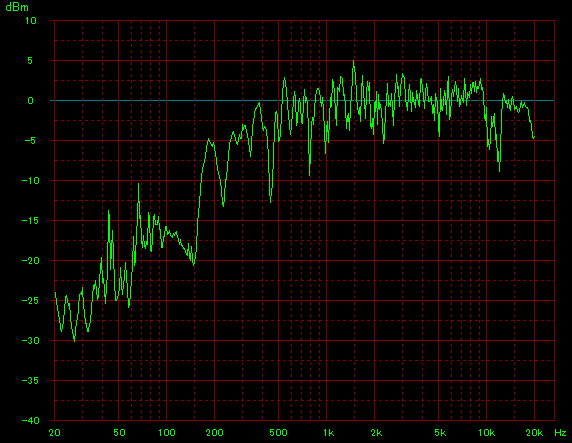
低域で、インピーダンスが上昇していますので、コンデンサが直列に入っています。
LF+HF
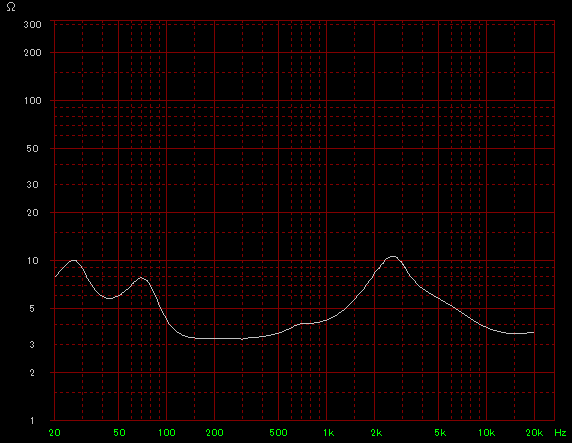
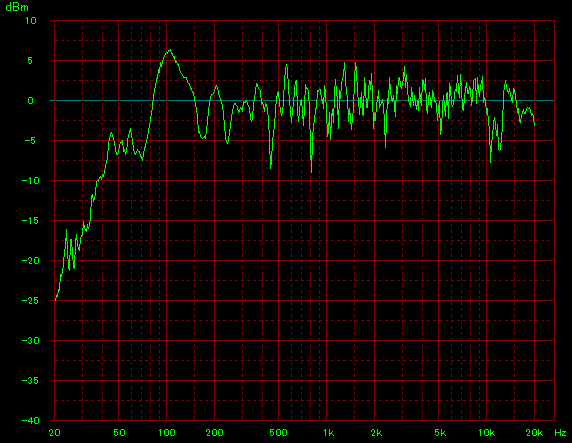
インピーダンス最低値は、3.2Ωですので、アンプ接続は、必ず1対1で行った方が良いでしょう。周波数特性や、インピーダンス変化を総合して、クロスオーバー周波数は、300Hzぐらいと推測しました。
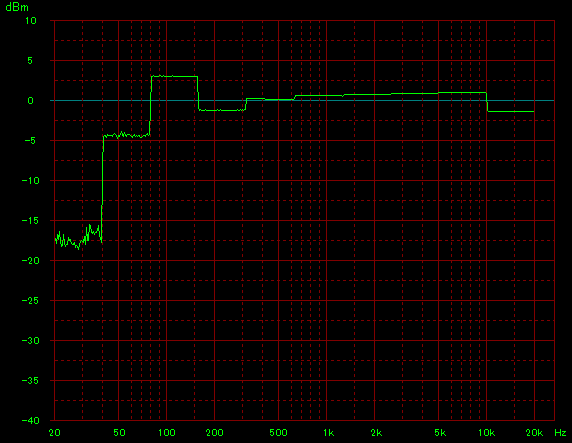 HFユニット正面1mでの特性は、低域がブーストされ、中高域は、フラットです。
HFユニット正面1mでの特性は、低域がブーストされ、中高域は、フラットです。KEFと非常に類似したスピーカーユニットがあるようで紹介しておきます。PARC Audio DCU-C172PPで、17cm同軸2WAYスピーカーで、ネットワークは付属しません。ドームツイーター前面には、お馬鹿な衝立もなく、好印象です。同社の新しい製品のようですが、詳しい事はまだよくわかりません。興味のある方は、リンクフリーとなっていますので、下のバナーから、訪問してみてください。
.jpg)
ディスクトップモニターとして、KEF Q15.2での使用実績では、某ハイビジョンシアター調整室のタンノイ モニターSPを聴いた時と同様の、シュアーな定位が確認できます。4WAYスピーカーシステムとの違いは、音の強弱表現だけがやや劣るのみで、満足度の高い物となっています。PARC Audio DCU-C172PPでも、同様の結果が期待できそうで、タイムアライメント調整が可能なマルチチャンネルでの使用をお奨めします。ウーハーをアンプ直結とするのは、問題なく行えますが、耐入力が15Wというツイーターを直結するには、勇気が要りますが、当方では、DENON製AVアンプ80W(8Ω)で、Q15.2を鳴らしていますが、3ヶ月程度使用しましたが、無事に動作しています。FOSTEX T90Aホーンツイーターを一度壊した事がありますが、100Wアンプの、入力ピンプラグをアンプ通電中に接続した時のショックノイズが原因で、それ以外では破損していません。
プロ音響に精通した方には、接続には、ノイトリック製スピコンをお奨めします。アンプは、特殊なアンプは必要なく、半導体式アナログアンプで十分と思います。スモールモニターとして、高い性能が期待できると思います。
ホーンの前面に障害物がある場合のインピーダンスへの影響
ホーンスピーカーは、ONKYO HM-450Aを使用し、障害物として、形状の複雑なコンセントや、開口部30cmに対して、幅10cmの板を、中央と、端に載せて行いました。
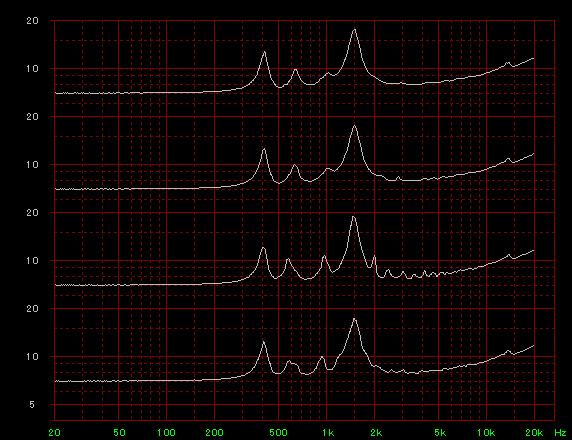
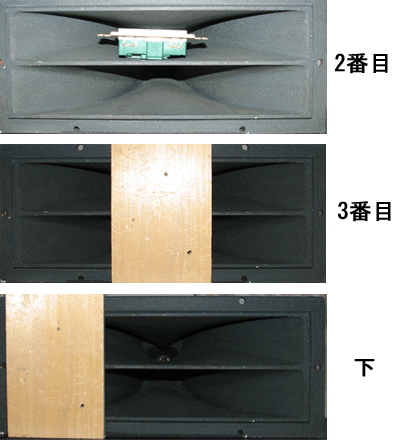
最上段 障害物なし
2番目 埋込コンセントを中央のフィンに載せた状態 障害物なしと比較すると、2つ目のピークを過ぎて若干のさざ波が立つくらいです。
3番目 中央に幅10cmの板を載せて見ました。理論どおり、反射による細かい波が、立っています。この中では最悪です。
下 段 ホーンの端に板を移動した場合で、中央と比較すると少なくなりますが、波立ちます。
JBL 2445J単体と、2380Aホーンを取り付けた場合のインピーダンス変化です。
上の実験と同じく、ホーンを付けると、障害物があるかのように、小さく波立つのがわかります。

次は障害物ではないのですが、同軸配置をするために、コーンスピーカー前面に構造物がある場合
業務用の同軸ドームツイータと16cmコーンスピーカーとの2WAYで、LF、HFスピーカーそれぞれに入力端子を持っています。
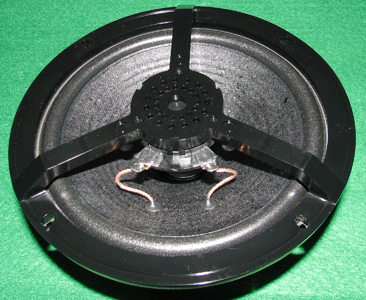
同軸配置されたドームツイータの特性です。スッリトが干渉して、櫛形フィルターが形成されたデップが連続しています。
マイクロホンではありませんので、中央に1個、周辺に15個2段の丸穴よりは、ウェーブガイドの方が、音響特性が良くなると思います。
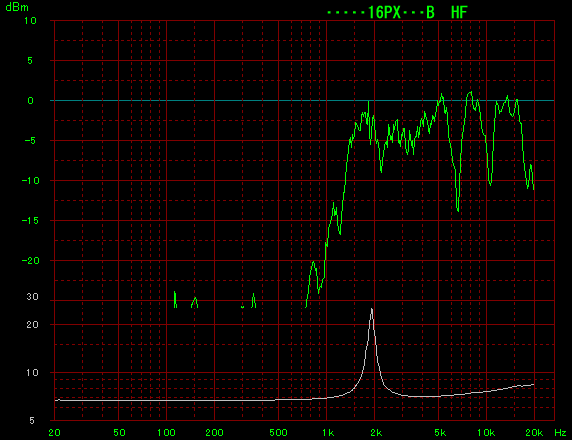
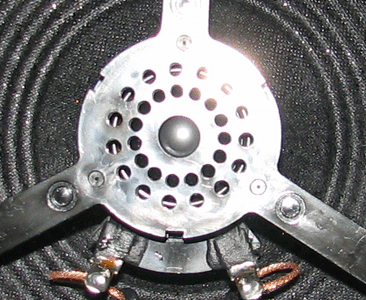
ホーンスピーカー複数設置
これは、アリーナやスタジアムでよく見かけるホーンの設置例ですが、ホーンの境界となる赤色の部分は、それぞれのホーンの干渉で、音が安定しません。室内でも、反射の無い屋外でも同じです。同じ帯域を複数のスピーカーで鳴らした場合、境界面では、必ずこのような干渉が起きます。サイドが良く切れる筈のホーンスピーカーであってもこのような干渉が起きてしまいますので、家庭用の場合、このような広範囲の音を狙っての複数設置は避けるべきでしょう。1個だけの設置では、このようなトラブルは発生しません。
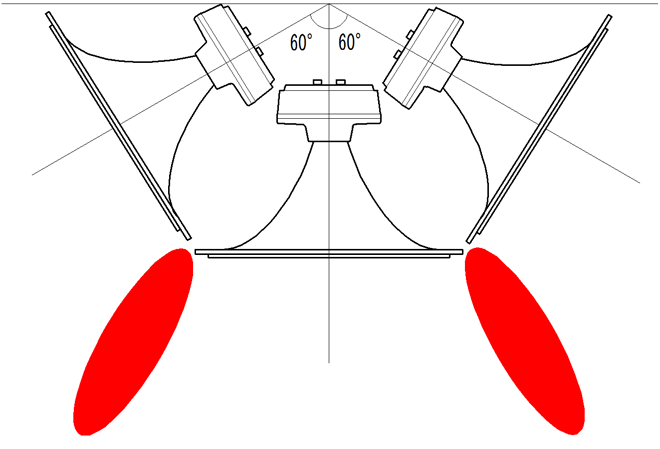
余談
ALTEC M500を最近修理しました。症状は、鼻つまみ声で、歪みっぽい音が出るという事で、前面ネットを外して、ホーンスピーカーを点検しました。大型のホーンでしたが、ドライバはそれほど大きな物はついておらず、カバーもないので、安っぽく見えてしまいます。インピーダンス特性を測定してみると、ボイスコイルの短絡等の兆候はみられず、正常でした。ダイヤフラムは、3本のネジ止めという、昔ながら方法でしたので、ひょっとしてと思い、発振音を鳴らしながら、芯出しを再度行ってみると、大当たりで、何事も無かったように、大きな音で鳴り始めました。ペイントロックされていないので、経年劣化でネジが緩んで、芯が狂ったのでしょう。M500ユーザーは要注意でしょう。ウーハのエッジもウレタン製なので、こちらも注意でしょう。
ウレタンエッジが破損したスピーカーの実例 右は、有名なフルレンジスピーカーで○の部分が、圧着のみ物で、接触不良事故あり、写真の物は、メーカー出荷時で、半田付け対策済みです
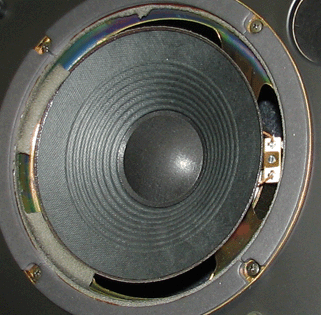 2014/10/20
2014/10/20 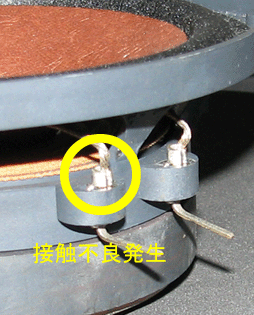 2015/0101
2015/0101TV制作現場PAでお馴染みの米国製2WAYスピーカーでは、ウーハーのファストンコネクタ端子での接触不良が時々発生しますが、事故にならないよう、時々端子をつぶしてやるか、半田付けをして、緩みが発生しないような処置も有効です。
次ページ デジタルライブラリー作りなど、ソフトのお話
トップページに戻ります