

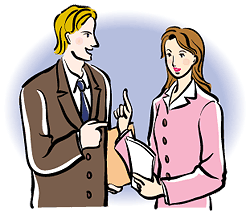


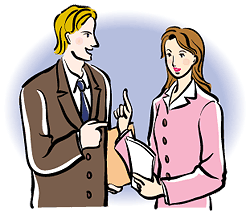
![]()
ここをクリックするとNO1へ
「十有五(じゅうゆうご)にして学に 志(こころざ)す。三十(さんじゅう)にして立つ。四十(しじゅう)にして惑(まど)わず。五十(ごじゅう)にして天命(てんめい)を知る。六十(ろくじゅう)にして耳順(みみしたが)う。七十(しちじゅう)にして、心の欲(ほっ)する所(ところ)に従えども、矩(のり)を踰(こ)えず。」
1.これは、孔子における年齢段階別の人格形成上の目標であるといわれる。
「わたしは数え年十五歳ではじめて学問の道に志し、三十歳自分の立場をかため、四十歳ではすっかり迷いがなくなり、五十歳では運命のなんであるかを知り、六十歳では他人の言を素直に受け取ることができ、七十歳では欲するままに行っても少しも行き過ぎがないようになった」というものであり、それは、数え年七十四歳で死んだ孔子が、晩年に自分の一生の経歴を振り返って述べた自叙伝のようなものである。
1、孔子における年齢段階別の目標が、人格の完成をめざすものであると考えるとき、その人格の特徴とするところが、自分の力で自分をいかに支配できるかいかにコントロールできるかにあるといわれており、人間を人間として善くするために働きかける教育の全ての営みにおいては、自主・自律の精神を養うこと、すなわち、自己教育力の育成が、中心的な課題である。
したがって、孔子における「七十にして、心の欲する所に従えども、矩を踰えず」は、修養の極致であり、人格の完成する姿であるともいえる。
2.教育の目的である人格の完成をめざして行われる教育においては、個々の子供における自主・自律の精神を養うこと、すなわち、自己教育力の育成が、すべての教育活動を通して、意図的に行われるこいとが肝要である。このことに関連するいくつかのいつもこころのおくにおいておきたい大切なことを述べたい。
① 「進んで行動したい。しかし、よく考えてから。」を認識させる。
それは、何事にも積極的に立ち向かい、自主的で、自律的に行動する人間への成長を願い、つねによく考えて、自らの責任において行動する人間にならなければならないと考える。
② 「親切の不親切、不親切の親切」を見極めて対応したい。
個々の子供の中に、自主・自律の精神を育てることの必要性は、だれもが協調するところであるが、教育の実際場面においては、そのことが結果として阻害されているような事実がある。
個々の子供が、自力でできるところまで立ち入って教えたり、助言したりすることがあるとすれば、それは明らかに、自主・自律の精神を育てるうえで、阻害条件になるということができる。
教育の具体的な過程には、親切のように見えて、不親切であったり、不親切のように見えるが、それが親切であったりといった事実がしばしば見られる。
③ 「その子のできることには、手を貸さない」ようにする。
このような教師になる道は、実際には、簡単に切り開くことのできない困難な道である。それは、端的に言って、個々の子供が、自力でできる、その力についての理解と見通しが、教師になければ、「その子供のできるところまでは立ち入って教えることができない」という教師の教育的行為は、成立しないからである。
しかも、このことは、子供は、一人ひとりみな違うということを前提にして対応しなければならのであるから、いっそう簡単なことではないのである。
したがってこのむずかしく、困難な教育の道を切り開くうえで、基本的に大事なこととしては、何よりも、「個々の子供に対する、より深く、確かな理解への努力」であるといえる。
そして、具体的な過程においては、個々の子供の理解に配慮しつつ、「学習を可能にする適切なヒントを与える」ことに努めることが、必要であり、大切である。