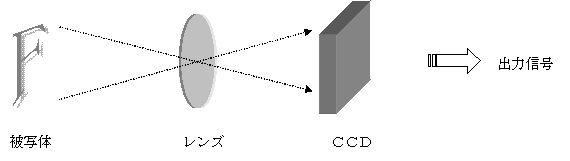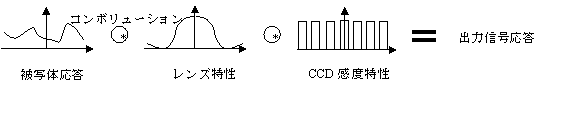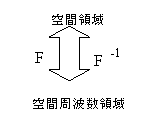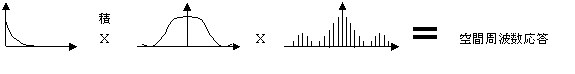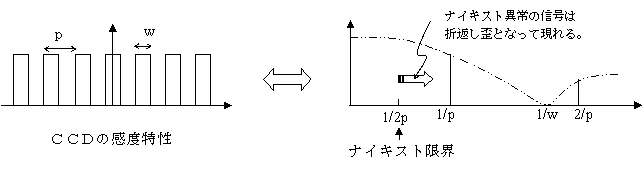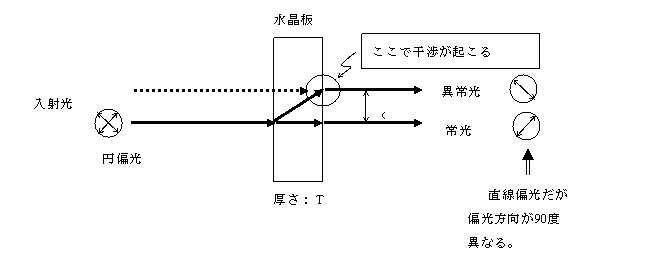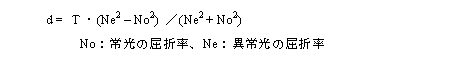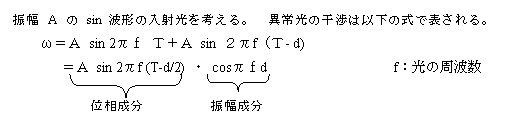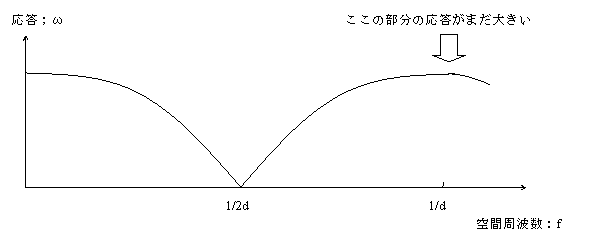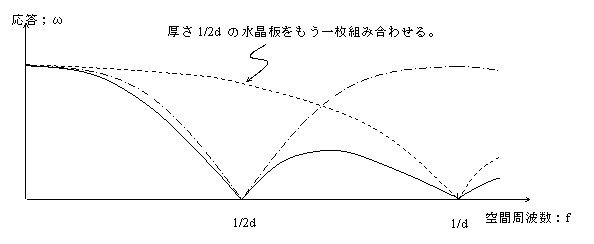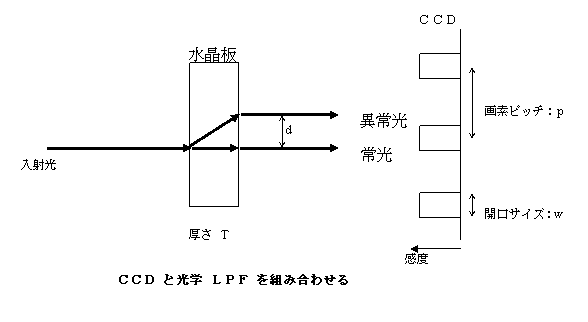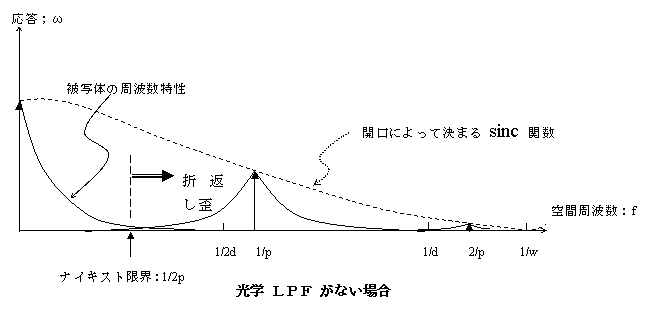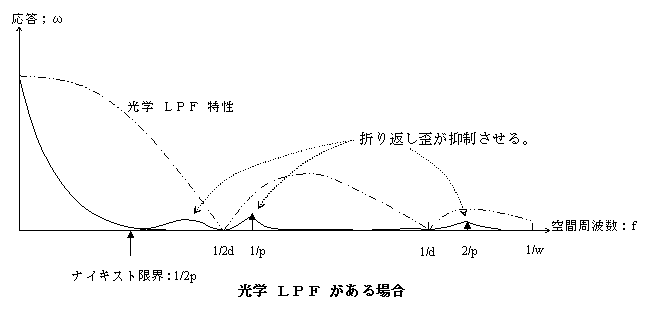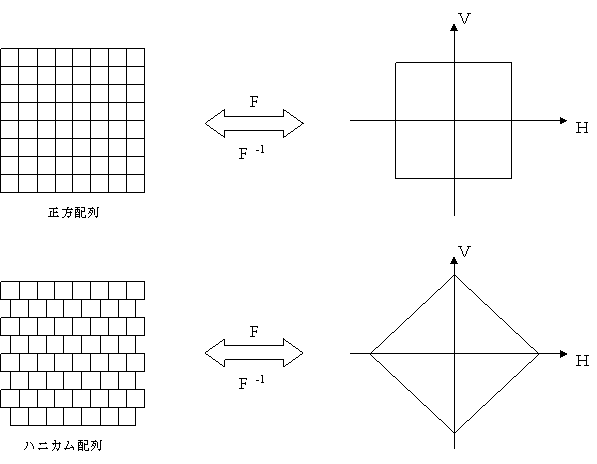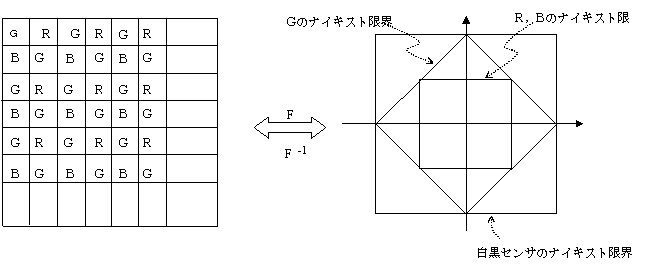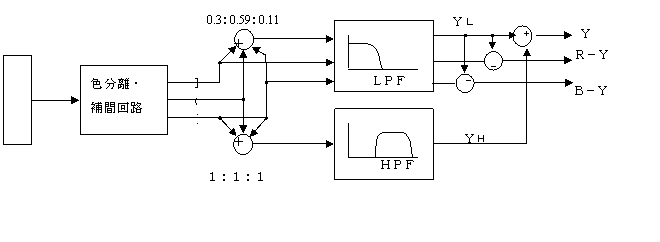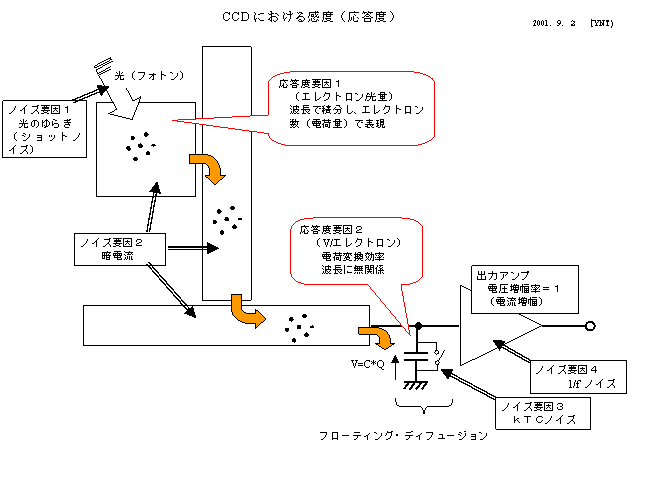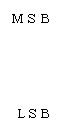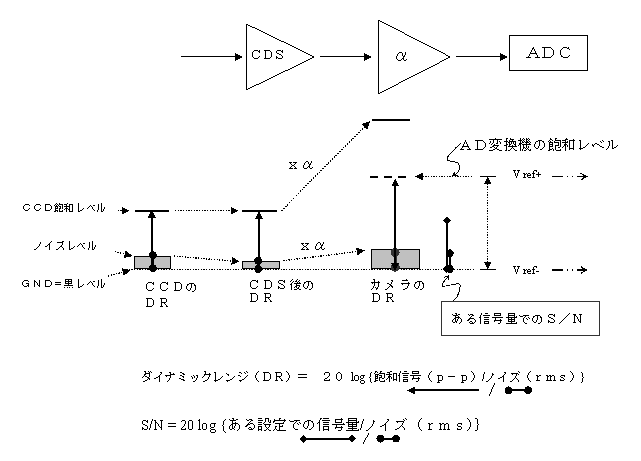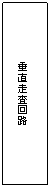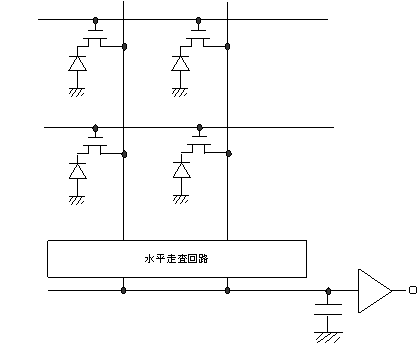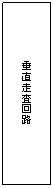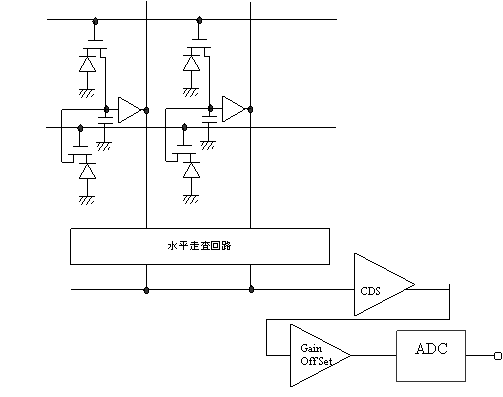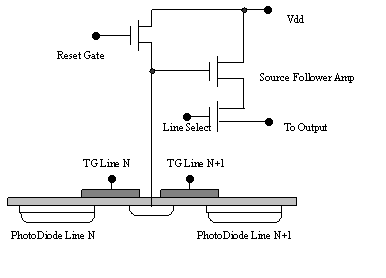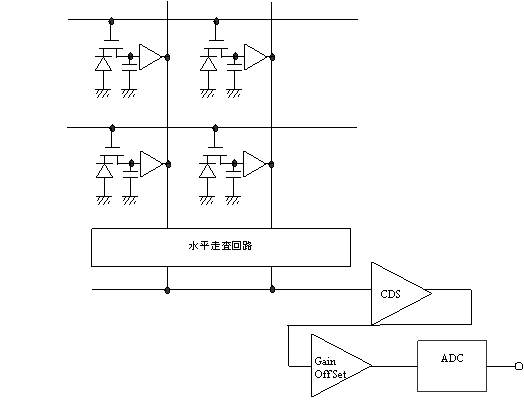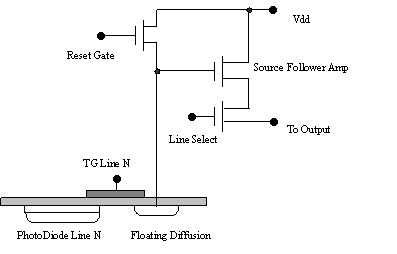CCDに関するセミナー
1. 空間サンプリング
CCDで撮像するということは、2次元空間において、離散系のサンプリングをおこなうことである。これはデジタル信号処理における、ナイキストの定理を応用できることを意味する。フーリエ変換を⇔で表すと、
f(x) ⇔ F(ω)、 g(x) ⇔ G(ω) としたとき、
{ f(x) ※ f(x) }⇔ { F(ω) x G(ω) }、 ここで※はコンボルーション。
1.1カメラシステム
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
折返し歪
空間サンプリング周期の1/2で決定されるナイキスト限界以上の周波数成分を持つ信号は、低周波成分に折り返され、モアレやエッジの偽信号となる。これを防ぐためには、電子回路の信号処理と同様に、AD変換器の前にLPFを入れて折返し歪を軽減するのと同様に、光学的なLPFを入れることで軽減する。
|
|
|
|
1.3
光学ローパスフィルタ
|
|
|
|
|
水晶板に入射された光は常光と異常光に分かれる。光の干渉により、以下のような空間周波数応答を持つ。これを利用して、光学的なLPFとして利用する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
正方配列とハニカム配列
画素配列を一ラインごとに位相を180度変えることにより、空間周波数帯域の垂直・水平方向の帯域を広くできる。一般的な被写体(特に人造物)は水平・垂直方向に高い周波数成分を含んでいることが多く、これにより再構築された画像がより自然となる。
|
|
|
|
|
|
1.5
ベイヤ配列
単板式のカラーカメラには色々な方式があるが、原色系の代表的なフィルタ配列がベイヤ配列である。下図のように、色信号単色の解像度を考えると、グリーンをモザイク状にとっても斜め方向の解像度は減少する。
|
|
|
|
|
|
上記のように、輝度信号の高周波成分を、R:G:B=1:1:1で構成することにより、無彩色な被写体に対して、白黒センサと同等のナイキスト限界を持たせることができ、被写体の白黒エッジに発生する色偽信号をなくすことができる。
2. 感度とノイズ
2.1応答度とノイズ
|
|
従来の感度という表現は、光に対する出力信号量とノイズの両方を考慮した、漠然とした出力量の表現である。ノイズの概念を考慮しない、純粋に出力信号量を応答度と定義する。
応答度=
応答度要因1 x 応答度要因2
=(エレクトロン数/光量)x
電圧/エレクトロン数)
ノイズは rms で表記するのが一般的である。ノイズ要素としては:光ショットノイズ、暗電流、リセットノイズ、1/fノイズの4つが主体である。
2.2 CCD内部のノイズ
リセットノイズは、フローティングディフージョンのキャパシタンスをリセットする時に発生するもので、温度とキャパシタの容量に比例するものでkTCノイズとも呼ばれる。1/fノイズはFETトランジスタが発生する、低周波ノイズである。この二つのノイズはCDS回路によりかなり低減できるものとされている。暗電流は半導体内部で発生する熱電子で、これがフォトダイオードやCCDに蓄積されるものである。温度に強い依存性があり(7~9℃の温度上昇で2倍になる)、これのノイズを減らすために、CCDを冷却して使うこともある。
ノイズ量は各ノイズ成分の二乗平均(rms)で表される。
ノイズ量=SQRT{(ショットノイズ)2 +(暗電流)2
+(リセットノイズ)2 +(1/fノイズ)2}
2.3 ダイナミックレンジとSN比(S/N)
ダイナミックレンジは飽和信号量にい対する、ノイズの量を表すものであり、下記の式で定義される。
DR=20 log{飽和信号量/ノイズ量(rms)}
S/Nはある信号量に対する、信号量とノイズの比である。
SNR=20 log{現在の信号量/ノイズ量(rms))
下図に、カメラ内部における信号量とノイズの様子を模式的に示した。
|
|
|
|
3. 新しいタイプのイメージセンサ
3.1 CMOSイメージセンサの構造
|
伝統的なMOSセンサの構造 |
|
Shared Pixel タイプのCMOSセンサ |
|
|
|
|
|
2.5 Transistor Shared Pixel |
|
4 Transitor CMOS Sensor |
|
|
|
高集積度 4トランジスタ画素構造 |
|
|
3.2 グローバルシャッタとローリングシャッタ
グローバルシャッタ:全画素同時に光電荷の蓄積を開始する。
インターラインCCDのシャッタ動作と同じ。
計測応用にはこちらのタイプが望まれている。
ローリングシャッタ:ラインごとに順次シャッタがきられる。
撮像管のような露光、走査動作。
動く被写体に対し、画像が流れる。
3.3 CMOSセンサの特徴
① オンチップ周辺化回路、デジタル信号出力
② 低消費電力
③ 部分読出し、可変フレームレート
④ サブサンプルによるズーミング
⑤ 上下、左右反転読出し
3.2
CMOSセンサの今後の傾向
① 非線形(log)感度特性により高ダイナミックレンジ化
ミノルタ/ロームの共同開発:
ログ変換ダイオードにより従来の1,000倍のダイナミックレンジを実現
320x220画素、 1/2“光学サイズ
20μx 20μ画素サイズ
0.1~10,000Lux
http://www.minolta.com/japan/release/f_top.html
② 高感度
APS(Active
Pixel Sensor)タイプ:画素単位でアンプを持つ。
積層形イメージセンサ: HARP膜積層形(NHK)
③ 低ノイズ化
CDS回路の内臓
④ 演算処理、
人口網膜: 三菱の三次元サンサ
http://www.semicon.melco.co.jp/product_cata/assp/pdf/moumaku.pdf
⑤ 高速読出し
複数ラインの同時読出しによる高速化: PhotoBit等
4M画素、240fps
http://www.photobit.com/News/News_Releases/PB-MV40_News_Release.pdf
1M画素、500fps http://www.photobit.com/Products/High-Speed_Sensors/high-speed_sensors.htm