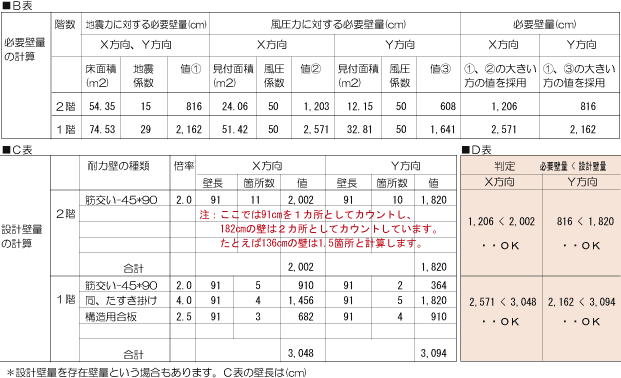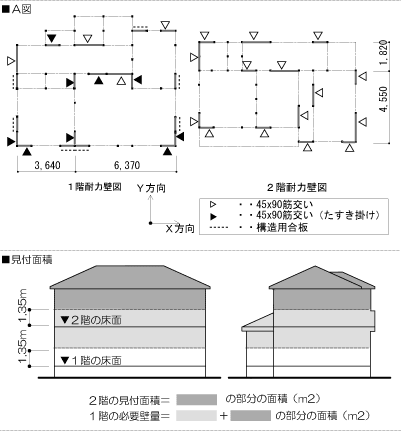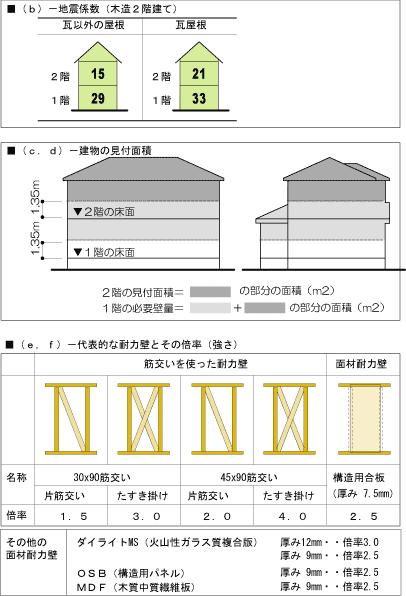壁量計算書 (へきりょうけいさんしょ) 壁量計算書とは、建物に建築基準法で定められた必要な耐力壁の量と実際に設計し、配置した耐力壁の量が建築基準法よりも越えているかどうか、あるいはどの程度の余裕があるのかを表した図面で、このページ自体は説明用に簡略化していますが、次のような構成となっています。 A図のようにその建物に配置された耐力壁の種類と位置が記された図面があり、風圧力算定用の立面図の略図が設けられ、建物の見付面積(正面の面積)を算定する図があります。 そして、B表でその建物に必要な耐力壁の量が地震力と風圧力の両方を計算して、高い数値の方を、その建物の必要壁量としています。 さらにC表で、その建物に配置された耐力壁を合計する計算表があり、最後にD表として、その建物に必要な壁量よりも、設計壁量が多ければ、建築基準法はクリアしたことになります。 |
注:A図、B表という表現はわかりやすくするための便宜上の名前です。図面にこの名前が付いているわけではありません。
|
|